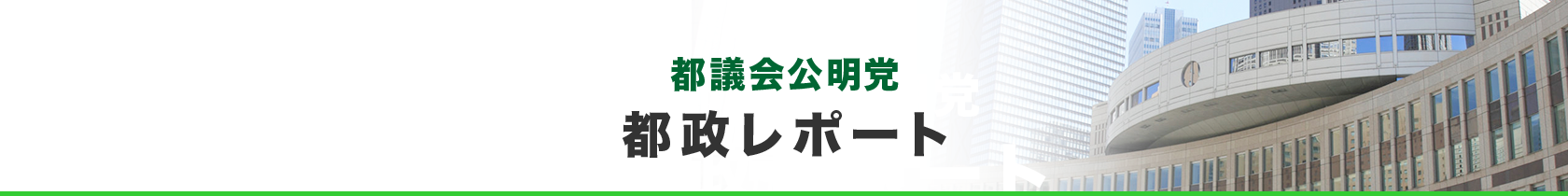まちづくり
① 木造住宅密集地域の不燃化の促進を
【質問】
令和6年の能登半島地震では、輪島市の朝市通り周辺において、大規模な火災が発生した。都内には、木密地域が広範囲にわたって存在しており、切迫する首都直下地震に備え、市街地の不燃化などの対策が急務である。
能登半島地震の教訓を踏まえ、木密地域の解消に向けた新たな施策を展開すべきと考えるが、知事の見解を伺う。
【知事】
いつ起きてもおかしくない首都直下地震などの脅威から、将来にわたり都民の生命と暮らしを守り抜くこと、首都防衛が、都政に課せられた使命である。
木密地域の解消を加速させていくため、令和7年1月、「防災都市づくり推進計画の基本方針」の改定案を公表した。
改定案では、能登半島地震における輪島市での延焼被害の状況などを踏まえ、局所的に対策が必要な地区を新たに防災環境向上地区として指定した。
指定された地区では、地元自治体によるきめ細やかな取り組みを令和8年度からの10年間集中的に支援するなど、木密地域の解消に向け、ギアを一段引き上げていく。
災害の脅威から都民を守る強靭な東京の実現に向け、燃えない、燃え広がらないまちづくりを強力に推進していく。
② 不燃化整備地域の防災性強化について
【質問】
都は、全ての整備地域において、不燃領域率70パーセントの目標を目指すとしており、不燃化特区制度を活用しながら、2021年時点で約66パーセントまで向上してきたが、地元の世田谷区北沢地域などでは、いまだに不燃領域率が59パーセントと、目標の70パーセントとは隔たりがあり、地元自治体による取り組みの促進が不可欠である。
そこで、この度の「防災都市づくり推進計画の基本方針」の改定により、整備地域において強化する具体的な取り組みについて伺う。
【東京都技監】
整備地域においては、不燃化特区制度を活用することなどにより、防災性は着実に向上しているが、地域特性の違いなどにより、不燃化の状況に差が生じている。
このため、基本方針の改定案では、特区制度を5年間延長し、無接道敷地の解消や高齢者世帯の建替えなどの促進に向けた制度拡充を図るとともに、不燃化の進捗状況の公表などにより、区市の取り組みを促すこととしている。
また、輪島市の大規模火災は、消火栓の断水などが延焼拡大の要因とされていることを踏まえ、耐震性貯水槽や防災井戸などの防災機能を備えた公園整備への支援を拡充することで、整備地域の防災性を高めていく。
③ ホームドア整備を加速する予算案について
【質問】
都議会公明党は令和7年第1回定例会の代表質問で、ホームドアの整備加速には国と連携した技術的な対応の強化や補助制度の拡充による、より踏み込んだ実効性のある支援をすべきと取り上げ、都からは、令和7年度から事業者に直接補助を行う制度を創設するとの答弁があった。
令和7年度予算案におけるホームドアの整備に係る予算総額と今後の見通しについて伺う。
【東京都技監】
令和7年度予算案においては、ホームドア等整備促進事業として、7億6,600万円を計上している。
加えて、都が鉄道事業者に直接補助を行うホームドア整備加速緊急対策事業を新たに創設し、6億4,000万円を計上している。
また、ホームドア整備加速緊急対策事業においては、年度にとらわれず工事を進められるよう、令和8年度から10年度まで213億5,000万円の債務負担行為を設定している。
④ 世田谷区内の小田急線のホームドア早期整備を
【質問】
ホームドア整備加速緊急対策事業では、既存補助対象外駅でも5駅以上連続して整備する場合には直接補助の対象となる。小田急線は、未整備の駅が5駅以上あるので、この補助制度を活用して、世田谷区内も早期に設置を進めるべきと考えるが、都の見解を伺う。
【東京都技監】
世田谷区内の小田急線の駅は10駅あり、4駅では整備済み、3駅ではホームドア等整備促進事業を活用して整備中であり、残りの3駅は未整備であるが、そのうち経堂駅については、令和7年度整備に着手する予定となっている。
新たに実施する補助制度では、事業者が令和10年度までのホームドアの設置を整備計画として公表することを前提条件としている。
そのため、都は、鉄道事業者に対し、未整備駅について、新たな補助制度を活用できるよう、整備計画の策定を働き掛け、ホームドアの整備を加速していく。
⑤ 踏切道の早急なバリアフリー化を
【質問】
奈良県で全盲の女性が踏切内で列車と接触して亡くなるという痛ましい事故が発生した。高齢者や障がい者等が安全・安心に外出するためには、世田谷区内の奥沢1号踏切を含む踏切道のバリアフリー対策について、早急に取り組むべきと考えるが、都の見解を伺う。
【建設局長】
高齢者や障害者等全ての人が安全で円滑に移動するためには、踏切道を含めた道路のバリアフリー化を進めていくことが重要である。
指定された踏切道の整備に向け、都は、改定された移動等円滑化ガイドラインを踏まえた対策方法等について鉄道事業者と調整を進めている。
奥沢1号踏切では、視覚障害者団体の意向を確認しながら、既設誘導ブロックの付け替え等について鉄道事業者と意見交換を実施している。
今後とも鉄道事業者と連携し、誰もが安全で安心して利用できる歩行空間の確保に取り組んでいく。
医療施設整備
① 新興感染症等の発生時に臨時の医療施設の設置を
【質問】
東京都医師会は、令和7年度の予算要望で、感染症パンデミックや大規模災害時の臨時の医療施設の創設を要望している。
新興感染症等の発生時に一気に増大する医療需要に対応するためには、患者を速やかに収容するための臨時の医療施設の設置が必要と考える。見解を伺う。
【保健医療局長】
都は、新型コロナ対応において、感染状況等に応じて酸素・医療提供ステーションや高齢者等医療支援型施設等の臨時の医療施設を戦略的に設置した。
これらの施設は、患者の治療のほか、介護度の高い高齢患者等の受入れやリハビリテーションの実施、24時間の救急受入体制の確保、症状が軽快した患者の転院受入れなど、時々の状況に応じて医療機関の病床を補完する役割を果たしてきた。
今後の新興感染症等の発生時には、感染症予防計画に基づき、感染症の特性や地域の状況等を踏まえ、臨時の医療施設を機動的に設置し、医療機関の協力も得ながら必要な医療提供体制を確保していく。
② 平時から臨時の医療施設での運営・設置訓練を
【質問】
感染症有事に臨時の医療施設を円滑に設置・運営するために、都として平時からの臨時の医療施設の訓練等に取り組むべきと考えるが、見解を伺う。
【保健医療局長】
都は令和6年度、感染症発生時に臨時の医療施設を迅速に開設し、円滑に運営できるよう、都医師会と意見交換を実施するとともに、都内の病院等と調整を行い、候補となる施設とその運営を担う法人を選定した。
また、有事に人材派遣を行う協定を締結した医療機関等を対象に、臨時の医療施設の運営に関する講演や、感染防護具の着脱訓練などの研修を開始した。
令和7年度は、候補となる法人を対象に、臨時の医療施設における患者の入所対応や施設のゾーニングなどの実践的な研修を新たに実施する。
こうした取り組みにより、有事の際に臨時の医療施設を機動的に設置・運営できる体制を整備していく。
③ 大規模災害時における臨時の医療施設の必要性について
【質問】
現在、重傷者を受け入れる災害拠点病院等が指定されているが、避難所等で体調を崩す人が想定され、悪化すれば災害関連死につながる。大規模災害時には、体調が悪化した避難者などの傷病者を収容するため、臨時の医療施設が必要になると考えるが、都の見解を伺う。
【保健医療局長】
都は、大規模災害時において、多数の傷病者に対応するため、都内全ての医療機関に、有する機能に応じてあらかじめ役割分担を定めている。
発災時に、症状に応じた必要な医療を提供するには、医療機関において入院患者を確実に受け入れる体制に加え、避難所等で体調が悪化しても入院までは必要のない避難者や、入院していた患者で避難所等での生活が難しい方などの受入体制を整備することが重要である。
このため、都は令和7年度、有識者や医療関係者等で構成する災害医療協議会の下に新たな部会を設置し、区市町村や関係機関と連携して、臨時の医療施設を含め、こうした災害時要配慮者に対する医療救護体制を検討していく。
子育て支援
① 子供への虐待リスクを未然に防ぐ子育て世帯訪問支援事業への支援を
【質問】
令和6年度よりスタートした子育て世帯訪問支援事業を都内では、現在47の自治体で実施している。小中学生がいる家庭に対し、訪問支援員が継続的に、親のみならず子供にも関わりを持つことで、不登校の子供が学校への復帰が可能になったとの事例も多く報告されている。
都として、更なる区市町村における人材の確保と育成を支援していくべきと考えるが、見解を伺う。
【福祉局長】
都は令和7年度、訪問支援員の確保と育成を図るため、保護者とのコミュニケーションや、子育て家庭が抱える不安や悩みを傾聴し、適切な支援につなげるスキルなどに重点を置いた都独自の研修カリキュラムを作成する。
また、このカリキュラムに基づく支援員への研修の実施や、研修を受講した支援員に対し、報酬の上乗せを行う区市町村を支援する。
② 子育て世帯訪問支援事業の利用者負担軽減策を
【質問】
現在、国の仕組みでは、本事業には一定の利用者負担が必要とされている。
本事業の利用促進のため、区市町村が行う利用者負担の軽減策について、都として一層支援を行っていくべきと考えるが、見解を伺う。
【福祉局長】
国は、本事業について、利用者が所得に応じた利用料を負担することを基本としている。
都は、利用者一人ひとりのサポートプランの作成や、ヤングケアラーコーディネーターの配置などを要件に、利用者負担の軽減に取り組む区市町村に対し、必要な経費の2分の1を独自に補助している。
令和7年度は、区市町村の取り組みが更に進むよう、都の負担割合を2分の1から3分の2に拡充する。
③ 子育て世帯訪問支援運営事業者支援のための実態把握を
【質問】
本事業による対象を広げていくには、現在の補助基準額では運営が厳しいとの声がある。
今後、本事業による支援の拡大を図っていくためにも、都として訪問支援の事務管理に係る課題等を把握し、運営事業者が安定的に運営するために必要な支援を検討すべきと考えるが、見解を伺う。
【福祉局長】
都は令和7年度、訪問支援員に対する研修カリキュラムの策定に向け、学識経験者や民間団体等からなるワーキンググループを設置する。
このワーキンググループでは、区市町村や事業を受託した事業者へのヒアリングを予定しており、事業の運営に関する課題について更なる実態の把握に取り組んでいく。
特別支援教育
① 医療的ケア児の通学専用車両の増加を
【質問】
現在、都立特別支援学校に在籍する医療的ケアの必要な児童生徒数が増加している。
医療的ケアの必要な児童生徒に対して、令和7年度にも、現在取り組んでいる医療的ケア児通学専用車両をさらに増やしていくべきと考えるが、見解を伺う。
【教育長】
医療的ケアを必要とする児童や生徒の増える中、そうした子供たちが特別支援学校に安全で確実に通うための仕組みを充実することは重要である。
これまで都教育委員会は、肢体不自由のある児童等が医療的ケアを受けながら学校に通うことのできる専用の車両について、平成30年度より運行を開始している。また、知的障害のある児童等について、令和6年度より同様の対応を行っている。
こうした中、今後とも特別支援学校で医療的ケアを必要とする児童等の増加は見込まれる。このため、令和7年度、通学で医療的ケアを必要とする子供に対応できる専用の車両を10台増やし134台とする。
これにより特別支援学校での医療的ケアの充実を図る。
② 医療的ケア体制の充実のため看護師増員を
【質問】
医療的ケア児専用通学車両の運行や新たな医療的ケアの実施など、校内の医療的ケア体制を充実させるためには、看護師対応は必須である。看護師増員についての見解を伺う。
【教育長】
特別支援学校における医療的ケアを行う上で、校内や通学時の対応を適切に進める体制の充実は重要である。
これまで都教育委員会は、特別支援学校に非常勤の看護師を配置し、児童や生徒が医療的ケアを必要に応じ受けることのできる環境を整えてきた。また、そうした児童等を送迎する車両に看護師が乗り、ケアを行う仕組みも実施している。
特別支援学校での医療的ケアに係るニーズの高まる中、令和7年度、児童等への対応を行う非常勤看護師の体制の充実を図る。具体的には、専門性の高い対応を行う看護師を5名増やすほか、その他のケアに必要な人件費を1割以上拡充する。
医療的ケアが必要な重度障がい者の地域生活支援
【質問】
特別支援学校に通うお子さんをお持ちのご家庭から、卒業後、医療的ケアに対応できる生活介護事業所は数が少なく、不安があると聞く。また、医療的ケア児者親の会の方からは、医療的ケアが必要であっても、将来は自立して自分らしく暮らしていくためのグループホーム等の整備をしてほしいとの声がある。
医療的ケアが必要な障がい者の日中活動の場や生活の場の整備について、今後の都の取り組みを伺う。
【福祉局長】
都は、令和6年度からの障害者・障害児地域生活支援3か年プランにおいて、医療的ケアが必要な重度障害者等を受け入れる日中活動の場やグループホームの利用者数の目標を定め、施設を整備する場合の補助基準額を1.5倍とするなど、設置を促進している。
令和7年度は、医療的ケアが必要な重度障害者の受入れが更に進むよう、グループホームや短期入所の施設整備に併せ、医療用モニターや人工呼吸器等の整備を行う場合の加算を新たに創設する。
こうした取り組みにより、医療的ケアが必要な重度障害者の地域生活を支援していく。
防災対策
① 世田谷区内の多摩川の排水樋門について
【質問】
現在、世田谷区内の多摩川には、排水樋菅が2か所、下水道の排水樋門が4か所ある。樋門の開閉等は区に委託されており、水防活動を行う区との連携は重要と考える。
世田谷区内の排水樋門について、下水道局と区の役割分担と、これまでの取り組みを伺う。
【下水道局長】
世田谷区内の4か所の排水樋門は、下水道局が設置したものであり、区が協定に基づき、日常の維持管理に加え、河川の水位が一定の高さに達した場合の樋門の閉鎖作業などを行っている。
下水道局では、これまでに排水樋門の操作の安全性を向上させるため、堤防から河川に張り出した通路を通らなくても、宅地側から遠隔操作ができるよう対策を実施した。
また、区と合同で樋門の操作訓練を実施するとともに、ホームページやSNSを活用して、樋門の操作状況を広く周知するなど、区との連携を強化した。
② 下野毛排水樋門におけるポンプゲート新設について
【質問】
現在、整備中の下野毛排水樋門以外の世田谷区内3か所の排水樋門にもポンプゲートの整備が必要と考える。下野毛排水樋門におけるポンプゲート新設について、令和7年度の取り組みを伺う。あわせて、多摩川沿いにおけるポンプゲートを始めとする対策について、認識を伺う。
【下水道局長】
下野毛排水樋門では、区が用地を確保できたことから、下水道局がポンプゲートの整備を行い、区で維持管理を行うこととしている。
これまでに、既存の樋門に設置可能なポンプゲートの詳細な仕様を決定し、現在、河川管理者をはじめ関係機関との協議を進めており、令和7年度の工事着手につなげていく。
多摩川沿いの低地部における対策については、引き続き、地元区など関係機関と調整していく。
トイレ対策
① 災害用トイレの整備方針について
【質問】
災害時トイレ空白エリアを解消するための災害用トイレの整備に当たっては、都全体でかなりの数のトイレが必要となると思われるが、整備主体となる区市町村をどのように支援し、トイレを整備していくのか、見解を伺う。
※災害時トイレ空白エリア…令和7年2月公表の「東京都トイレ防災マスタープラン素案」で、災害時に使用できるトイレがある施設の徒歩約5分圏外を設定している。区市町村における災害用トイレ確保を促進し、2030年度までに解消を目指すとしている。
【総務局長】
都は、東京トイレ防災マスタープランで、災害用トイレの整備方針を示すとともに、不足数量を算出するシートを提供するなど、区市町村が地域の実情を踏まえ、トイレ確保に向けた計画を策定できるよう支援していく。
さらに、区市町村に対し、発災直後、復旧期それぞれの段階や、被害想定等に応じて必要となる様々な災害用トイレ整備の補助を行うとともに、区市町村の意向を踏まえ、学校や公園などの都立施設においても、マンホールトイレなどの災害用トイレを確保していく。
② 避難所環境整備等の区市町村支援について
【質問】
令和7年度から実施される避難所の環境整備等の区市町村補助制度は、区市町村等が活用しやすくすることが不可欠である。区市町村が補助を活用し、資器材を適切に整備できるよう支援すべきだが、見解を伺う。
【総務局長】
避難所の環境等の整備に向けて区市町村が主体的に取り組むためには、使いやすい補助制度とすることが重要である。
そのため、新たに創設する補助制度では、区市町村がより効果的、効率的に整備できるよう、地域の特性や区市町村のニーズにあわせて、適切な資器材を柔軟に選択できるような仕組みとする。
さらに、他自治体における資器材の導入事例を紹介するなど、区市町村を支援していく。
③ 災害用トイレの質の確保について
【質問】
災害時に衛生的なトイレ環境が保たれなければ、避難者等の健康への影響も懸念される。そこで、災害時におけるトイレの質を確保するため、衛生的なトイレ環境を維持する取り組みについて、見解を伺う。
【総務局長】
災害時において、被災者がストレスなく快適にトイレを利用するためには、衛生的なトイレ環境を確保することが重要である。そのため、避難所運営指針の素案においては、発災直後から水洗トイレを使用できることを都独自の基準として示している。
また、東京トイレ防災マスタープランの素案において、施設管理者や避難所運営者等が災害用トイレの使用手順や清掃の実施体制、必要備品などの項目をチェックするアセスメントシートを作成し、適切な維持管理に活用できるようにしている。
今後、アセスメントシートの活用を区市町村等に丁寧に働きかけていく。