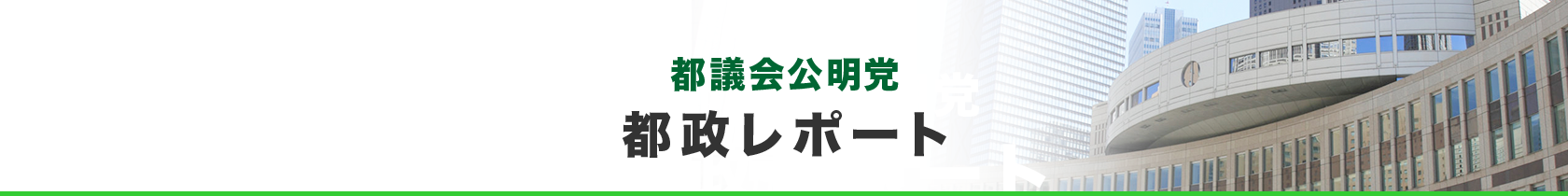事業評価の更なる深掘りを
【質問】
都議会公明党が提案したバランスシートと行政コスト計算書、キャッシュフロー計算書作成による財政の見える化で、都は2006年度から約1兆円の隠れ借金の解消などを行ってきたが、今一度、原点に立ち返り、新公会計制度の発生主義による行政コストを活用した事業評価を行っていくべきと考える。都の見解を伺う。
【財務局長】
事業の効率性や実効性の向上のため、新公会計制度を活用し、減価償却費や金利等を加味したフルコストでの比較など、多面的に事業の分析を行うことは重要である。
こうした観点から、都は、国や全国の自治体に先駆けて導入した新公会計制度を、事業評価にも活用しながら事業の見直し・再構築に取り組んできた。
今後、新公会計制度の更なる活用を図るため、減価償却費等のコスト全体を踏まえた分析などの好事例を各局と共有し、事業評価の深化に取り組むことで、事業の見直しを一層推進していく。
子育て・若者・教育施策
① すべての子どもが英語を話せる東京へ
【質問】
都議会公明党は、すべての子どもが英語を話せる東京を目指すべきと考える。日本人が苦手だと言われている「話す」こと、使える英語力を身に付けるためには、マンツーマン英会話レッスンなどの先進事例も含め、各区市町村立小中学校で英語を母語として話すネーティブ人材を一層活用できるよう都教育委員会が支援していくことが重要であると考える。見解を求める。
【教育長】
東京の将来を担う子供たちの英語の聞き取りや会話の力を高める上で、小中学校で、ネーティブ人材の活用を進めることは重要である。
これまで都教育委員会は、小中学生に対しTOKYO GLOBAL GATEWAYにおいて海外の店舗での場面等を想定し、ネーティブと会話のできる機会を提供してきた。また、外国人を小学校に派遣し、学校生活の中で児童と英語のやりとりをする取り組みを行っている。令和7年度は、小中学校で英語を担当する教員向けに子供が自然に英語で会話をする方法をネーティブから学ぶ講座を新たに行う。これに加え、区市町村のネーティブの活用に係る課題やニーズの把握を行っていく。
② 小中学校における空調設置・更新への支援
【質問】
都は、体育館等の空調の補助事業を令和6年度で終了するとしているが、未完了の自治体もあり支援期間を延長すべきである。また、令和8年度から一斉に行われる普通教室の空調の更新に向け、体育館の空調設置と同様、都の財政支援の制度を検討すべきである。あわせて都教育委員会の見解を伺う。
【教育長】
これまで都教育委員会は、小中学校に係る普通教室の空調機器の導入を支援し、全校での設置を実現した。また、特別教室や体育館等について、早期の導入に向けた助成を行っている。令和7年度から、特別教室等に係る空調の導入を計画的に集中して進めることができるよう、区市町村への助成を3か年延長する。
なお、普通教室の空調の更新に関し、区市町村の実態や整備に必要な現場の経費の動向等を調べ、課題整理を行う。
③ 受験生チャレンジ支援貸付事業の対象要件緩和
【質問】
都議会公明党は、令和6年の予算特別委員会で、中学生時代に不登校であった生徒が多く通うサポート校を、受験生チャレンジ支援貸付事業の対象とするよう検討を求めたが、対象となる塾の経営の経費的な立て分け等を条件としたため、活用できていなかった。サポート校での努力を通し、受験に挑戦し、自己実現を図ろうとする生徒を、受験生チャレンジ支援貸付事業で具体的に応援できるよう、対象要件の緩和を図るべき。令和7年度の制度拡充内容と併せて見解を求める。
【福祉局長】
都は、低所得世帯の子供の進学を支援するため、高校や大学等の受験料及び学習塾の受講料の無利子貸付けを行っている。都が令和6年度実施した調査によると、近年、大学受験料や学習塾代が上昇していることから、令和7年度、大学受験料は8万円から12万円に、学習塾代は20万円から30万円に貸付上限額を増額する。
また、通信制高校の生徒が通うサポート校の多くでは、生徒の進路希望に応じて個別に進学支援を行っていることを踏まえ、受験用コースの有無にかかわらず進学支援を行う全てのサポート校に貸付対象を拡大する。こうした取り組みを通じて、低所得世帯の子供を一層支援していく。
④ 教員の業務負担軽減策
【質問】
教員の長時間勤務の大きな原因の一つは、保護者や地域からの苦情等への対応である。こうした業務は、教員が個人として行うのではなく、学校や教育委員会が行政の責任として対応する体制が必要であり、特に、専門的な知識が求められる法務相談については、弁護士、司法書士、行政書士と連携し、的確に対応できる体制を整備するべきと考える。教員に集中している業務を、それぞれの専門的な技能をもったスタッフと分業化すれば、教員の業務負担を軽減できるとともに、学校の機能の向上にもつながる。都教育委員会の見解を伺う。
【教育長】
都立学校では、保護者や住民等からの要望に関し、複雑で高度な内容のものが増え、法律の専門的な知識が必要な場合も生じている。こうした状況に適切に対応する上で法律等の専門家を活用することは効果的である。
このため都教育委員会は、都立学校からの相談に弁護士が助言をする窓口を東京都教育支援機構に設けている。
令和7年度は、都立学校からの要請に応じ、教員が保護者等と面談をする場合、弁護士が同席し法務的な対応をする支援の仕組みを導入する。また、そうした弁護士が事例に応じ、保護者等との交渉を直接に担うサポートも実施する。
民間病院への財政支援
【質問】
都議会公明党は、令和6年第4回定例会で、都内一般病院の過半数が赤字になっている、東京の地域医療提供体制の維持に向けた取り組みを行うべきと要望し、都は「将来にわたって地域医療を提供できるよう取り組みを検討していく」と答弁した。これを受け、今回、入院患者1人当たり580円の支援金を交付するという、国の診療報酬の上乗せともいえる都政史上初めての支援金を決断した理由について、知事の見解を求める。
【知事】
本来、こうした課題は、診療報酬制度の改善や必要な財源措置を講じるなど国が対応すべきものであるが、国の診療報酬は、物価等の地域差が十分に加味されていない。また、都内では全国と比べて、民間病院の占める割合が高い状況にある。
こうした状況にあっても、地域医療提供体制を維持し、都民の命と健康を守っていかなければならない。
このため、都は令和7年度、緊急的かつ臨時的に、全ての民間病院を対象として、都内の物価等を考慮した支援金を入院患者数に応じ交付する。都内に多くある中小病院を例にとると、病床数が100床で、病床稼働率が90%の場合、年間1,900万円の支援となる。
誰もが住み慣れた地域で安心して必要な医療を受けられるよう、地域医療を力強く支えていく。
福祉・高齢者施策
① 介護DXでビジネスケアラー支援を
【質問】
働きながら家族の介護を担うビジネスケアラーがマイナンバーカードを活用して、自身のスマートフォンやパソコンから高齢者施設の検索や、自治体・施設への手続きを行えるようにする、介護DXに取り組むべきである。こうした優先度の高い分野から政策DXを推進していくべきと考えるが、知事の見解を伺う。
【知事】
介護DXについてであるが、将来を見据え、組織や分野を越えて横串・縦串を刺し、多様な主体が知恵を出し合い、サービス変革を実現することで、都民の貴重な「手取り時間」を増やす。それが政策DXの目指すものである。
政策DXの推進に当たっては、国や区市町村と密接に連携し、ライフイベントごとに手続を一気通貫でまとめ、必要なサービスをより簡単、便利に利用できるようにする。
子育て世代の利便性向上に加え、今後、働きながら介護に取り組む忙しいミドル層の負担軽減につながる介護DXを進めていく。
デジタルの力で都民サービスを飛躍的に向上させ、全ての人が輝き、一人ひとりが幸せを実感できる東京を実現していく。
② 強度行動障害を有する方への支援
【質問】
強度行動障害は、重度の知的障害等で噛みつき・頭突きなどの他害や自傷行為等が頻繁に現れる状態をいい、これに関する正しい知識がないため、適切なサービスが提供できていない。入所施設やグループホームなどで、強度行動障害を有する方が適切な支援を受けられるよう、都として受入体制の強化を図っていくべきと考える。都の見解を伺う。
【福祉局長】
都はこれまで、自傷や他害など強度行動障害を有する重度障害者のグループホームでの受入促進のため、事業者の整備費負担を軽減する特別助成や、国の基準以上に手厚く職員を配置する事業者への支援を実施してきた。
令和7年1月からは、特に支援が困難な方を受け入れるグループホーム等に対し、適切なアセスメントと障害特性に応じた支援方法等について助言を行うアドバイザーを派遣する取り組みを2区市で開始した。
令和7年度は、この取り組みの対象を全区市町村に拡大し、強度行動障害に対応できる事業所等の受入体制の強化に取り組んでいく。
③ 強度行動障害の専門性を有する人材の育成を
【質問】
国の中核的人材の育成は人数が限られている。強度行動障害を有する方が安心して穏やかに暮らしていけるよう、都が主体となって中核的人材の育成の仕組みを構築するとともに、心理学に基づいたABA(応用行動分析学)の手法を用いるなど、より専門性の高い人材を育成すべきと考える。都の見解を求める。
【福祉局長】
強度行動障害を有する方が安心して生活するためには、適切な支援を行える人材の育成が重要である。
このため都は、障害福祉サービス事業所等の職員向けに、強度行動障害の特性や支援方法を学ぶ研修を実施してきた。
令和7年度は新たに、心理学の観点から問題行動を分析し、適切な支援につなげる応用行動分析学等の手法をカリキュラムに盛り込んだ、独自の研修を実施する。
この研修を通じて、各事業所で中核的な役割を担う、より専門性の高い人材を年60人程度養成し、強度行動障害を有する方への支援を強化していく。
④ シルバーパスの利用者負担の軽減とバス事業者支援を
【質問】
都議会公明党は、高齢者の社会参加と健康増進のため、シルバーパスの重要性を踏まえ、現行制度を抜本的に改善すべきと提案してきた。令和7年度予算案で、ICカード化と利用者負担軽減が盛り込まれた。特に、都議会公明党が具体的に求めたことにより、利用者負担を引き下げることを高く評価する。そこで、利用者負担の軽減とともに、各バス事業者の厳しい状況を鑑み、円滑にシルバーパス事業が実施できるよう早急に支援を行っていくべきである。知事の見解を伺う。
【知事】
シルバーパス制度導入以降の高齢者像や交通事情の変化を踏まえ、高齢者施策全体を総合的に議論する中で、利用実態を把握しながら、制度の抜本的な見直しを検討する必要がある。このため、令和7年度は、ICカード化に着手し、令和8年度の一斉更新以降、できるだけ早期の導入を目指す。
抜本的な見直しまでの間、高齢者の社会参加促進に向け、年間20,510円の利用者負担額を令和7年10月から12,000円に引下げ、負担の軽減を図る。
また、運転手の確保や物価高騰など、バス業界を取り巻く環境が厳しいことを考慮し、東京バス協会に対し、緊急的措置として支援を行う。
こうした取り組みを進めながら、アクティブな「Choju社会」の実現を目指し、高齢者の社会参加を支える事業として、制度の改善に向けて検討していく。
産業労働政策
① 現役世帯の年収を増やす取り組みを
【質問】
中小企業の生産性を向上させる支援と従業員のリスキリング(学び直し)支援が重要である。また、都と経営者、労働者が集まる「公労使会議」を活用し、物価高に負けない賃上げへの合意形成を知事のリーダーシップで進めていくべきである。知事の見解を伺う。
【知事】
都は令和7年度、中小企業がDX活用等の支援により成果を賃上げにつなげた場合に補助率を引き上げる。また、リスキリングに向けた休暇や資格取得などの制度を設けた際に新たな奨励金による後押しも行う。
都や経済団体、労働団体のトップが集まる公労使会議など様々な場で意見交換を活発に行い、持続的な賃上げの実現に向け、着実に歩みを進める。
② 就職氷河期世代に寄り添う支援と待遇向上を
【質問】
就職時に不景気で不本意ながら非正規雇用を選ばざるを得ず、キャリア形成の機会を逃した就職氷河期世代の安定就労を確実に前へ進めるとともに、高齢期を見据えた人生設計に寄り添う支援を進めるべきである。また、就職氷河期世代の労働環境の整備に取り組む中小企業を支援し、この世代の待遇向上を図るべきであるが、併せて都の見解を伺う。
【産業労働局長】
都は令和7年度、就職氷河期世代の採用に前向きな企業との合同面接会について、対象年齢を引き上げるとともに規模を拡充し、都内各地で計18回開催する。
就職氷河期世代の相談に、きめ細かく対応する専門家を、区部に加え多摩にも配置し、高齢期を見据えた経済面や生活面などの支援も強化する。採用後の賃金引上げなどを行う中小企業には、新たに助成金の加算を設ける。
これにより、就職氷河期世代の将来の安定を後押しする。
③ 建築を担う人材のリスキリング支援を
【質問】
建物や設備等の設計を担う技術者は、資格取得の難しさもあり、人材の裾野となる若年層の確保や在職者のスキルアップが急務である。
一方、建築分野の中小企業では、新人を採用しても育成の余裕がないため、資格の取得を応援できるよう、行政に対して支援を求める声が高まっている。
職業能力開発センターにおいて、建築業界で働く人に対する訓練の充実を図るとともに、従業員が資格取得の勉強に打ち込める社内の環境づくりが進むよう支援すべきであるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
建築分野の中小企業で働く人のスキルアップを支援するとともに、主体的にリスキリングに取り組む従業員を応援する職場環境づくりを促すことは重要である。
都は、職業能力開発センターで実施する従業員向けの訓練において、時間を有効に生かして建築士の資格取得に挑戦できるよう、令和7年度からオンライン訓練を実施し、建築設備の設計などを担う人材の裾野を拡大する。
また、リスキリングの環境づくりを後押しするため、休暇制度の整備や資格取得講座の受講に必要な経費の支援などを導入する企業に対し、奨励金の支給も開始する。
これらにより、中小企業の人材育成を支援する。
住宅施策
① 子育て世帯等に配慮した低廉な住宅供給を
【質問】
都議会公明党は、住宅価格の上昇によって子育て世代が都内に住みにくい状況から、市場価格よりも安い家賃で入居できる「アフォーダブル住宅」を提案した。令和7年度予算案において、アフォーダブル住宅の供給のために都が100億円、民間が100億円の合計200億円のファンドを立ち上げ、令和8年度から供給を開始するとしたことを高く評価する。都は、家賃を市場家賃の8割程度と想定しているが、まだ高すぎる。都の収益を最小限にするなどして6割程度まで引き下げていくべきだが、知事の見解を伺う。
【知事】
都民にとって住まいの確保は、欠くことのできない重要な要素だ。安心して子供を産み育てられる住環境を整えるには、官・民の知恵とノウハウを最大限生かして取り組まなければならない。
このため令和7年度、都の出資を呼び水に民間資金を呼び込み、アフォーダブル住宅を供給する官民連携ファンドを総額200億円規模で立ち上げる。住みやすい住宅提供というファンド理念に共鳴する民間事業者の創意工夫を生かし、中古ビルや空き家の活用など様々な形での住宅供給を支援する。
今後、事業提案の審査に当たっては、家賃の引下げ幅に応じたファンドの出資利回りの設定や、審査での重点評価項目とするなどを通じて、事業者の家賃が可能な限り引き下げられるよう、インセンティブを高めていく。
これらの取り組みを通じて、子育て世帯等に配慮した住みやすい住宅が極力低廉に供給されるよう取り組んでいく。
② 都営住宅の共用部の維持管理
【質問】
都議会公明党は、令和6年の第2回定例会で、都営住宅の名義人の約7割が65歳以上となった今、自治会役員による管理業務の負担の軽減が不可避であると考え、抜本的な改善を求めた。
都営住宅では、共用部の維持管理を自治会役員が中心に担っているが、高齢化やコミュニティ意識の希薄化が進み、都は平成29年から維持管理業務の一部を外部に委託できる方式を導入した。
しかし、委託化は住民合意を得る困難さや委託費用などの課題があり、加えて共益費の徴収を住民が担うという、民間とは異なった取り組みが原則とされ、この点も自治会役員の負担感の一因となっている。
都は、民間でいう家賃に当たる使用料を口座振替等の方法で徴収しているが、共益費や委託料も使用料と一緒に徴収可能であることを全面的に打ち出すべきである。さらに、委託化の推進に際しては、自治会役員が居住者を説得するのではなく、都が積極的に説明に当たるべきである。加えて、委託料の低減化にも取り組むべきである。併せて見解を伺う。
【住宅政策本部長】
都営住宅の居住者の高齢化が進む中、その負担を軽減するため、都が居住者から事務費を含む共益費を使用料と一緒に徴収し管理の一部を代行できることとしており、今後このことを改めて全ての居住者や自治会に積極的に周知する。
また、都が令和5年に実施した自治会等へのアンケートでは、この仕組みの利用に当たり、居住者間の合意形成が困難、費用面が不安などの声があったことから、今後、こうした声のある自治会等に個別に説明を行っていく。費用面についても、単価や作業の範囲、回数等の見直しを行う。
これらの取り組みの強化により、居住者の良好な居住環境を確保していく。
防災施策
① 防災対策の更なる強化
【質問】
首都直下地震など大規模災害が懸念される東京において、ハード対策はもちろんのこと、TKB(トイレ・キッチン・ベッド等)に加えて、子どもの居場所の確保など、女性や子どもの多様な視点での避難所環境改善の取り組みも重要であり、様々な角度からソフト対策を進めてくことが必要である。
都は、都市の強靱化を進めているところだが、今こそ、知事が先頭に立ち、発災後の対応も含め、防災力を更に向上させていくことが重要と考えるが、知事の見解を伺う。
【知事】
都は、燃えない・燃え広がらないまちづくりや、調節池の整備などを一層加速するとともに、能登半島地震の教訓も踏まえ、雑魚寝の解消、トイレ環境の確保など避難所改革に着手する。さらに、マンション防災や防災DXの推進、女性や子供のほか、要配慮者への対応などハード・ソフトの両面から防災対策を強化する。
首都東京を守るためには、オール都庁の取り組みが不可欠であり、今般、防災アクションプランの素案を取りまとめ、事業を計画的に推進していく。都の防災力を一層高めることで、首都防衛を実現し、都民一人ひとりの命と健康を守り抜いていく。
② 木密地域の課題に対応した不燃化の推進
【質問】
令和7年1月に公表された防災都市づくり推進計画の基本方針の改定案において、都議会公明党が提案した、令和7年度終了予定の不燃化特区制度を継続することなどが反映されたことを評価する。
これまでの取り組みにより、整備地域の不燃化は着実に進展しているものの、地域によっては、敷地が十分な幅員の道路に接していないなどの理由で、老朽建築物の建て替えが進みにくいなどの課題があり、目標達成に遠く、不燃化の取り組みを加速していくことが重要である。
都内の木密地域における防災都市づくりを更に推進していくには、区市の取り組みへの支援を一層強化していく必要があると考えるが、見解を伺う。
【東京都技監】
今般公表した基本方針の改定案では、整備地域においては、特区制度を5年間延長した上で、地域の実情に応じた支援の拡充などを図っていくこととしている。
加えて、新たな防災環境向上地区の指定により、防災生活道路などへの支援を開始し、国と合わせて補助率を最大で4分の3とするなど、区市の負担を軽減する。
こうした取り組みにより、都内の木密地域の不燃化を一層加速させ、東京の強靭化を進めていく。
③ 介護等が必要な高齢者の住宅耐震化支援の強化
【質問】
改修等が必要な旧耐震基準の住宅の所有者の多くは高齢者である。過去の震災を踏まえると、こうした方々への住宅耐震化は待ったなしの状況である。介護や支援が必要な高齢者等に対し、これまで以上に踏み込んだ住宅耐震化への支援を強化すべきと考えるが、見解を伺う。
【東京都技監】
高齢者の中でも介護や支援が必要な方は、避難生活の長期化による影響等も懸念されることなどから、住宅の耐震化への支援を強化することが重要である。
このため、令和7年度は、要介護者等が居住する世帯の負担低減に向け、国と区市町村を合わせた補助限度額を178万円から300万円へ増額するなど支援を拡充し、補助率を最大で10分の10とする。
増額分のうち、都費の61万円については、区市町村負担がない場合でも活用を可能とする。
あわせて、新たに、新聞折り込みなどを活用した広報を展開し、住宅の耐震化を推進していく。
④ 災害用のモバイルファーマシーの導入
【質問】
東日本大震災を契機に、調剤設備を持たせた災害対応医薬品供給車両、いわゆるモバイルファーマシーの整備が全国で進んでいる。
能登半島地震では全国から13台のモバイルファーマシーが活用され、被災者に対する医薬品提供に寄与した。都においてもモバイルファーマシーを導入し、災害時の円滑な運用に向け、関係機関との連携体制を構築する必要があると考える。都の見解を伺う。
【保健医療局長】
医療救護所等において、都は、被災者に必要な医薬品を提供する体制を整備している。
これに加え、能登半島地震でも有効に活用された、医薬品や調剤設備等を搭載する車両で、被災地において医薬品を供給するモバイルファーマシーを令和8年度導入する。
モバイルファーマシーは、薬剤師会と連携して運用する予定であり、活用実績のある他自治体等との情報交換や訓練などを通じて、都における運用方法を検討するとともに、災害発生時には被災状況に応じて現地に派遣することで、医療救護所等に必要な医薬品を供給する体制を強化していく。
⑤ 八潮市の道路陥没事故を受けた対応
【質問】
令和7年1月28日に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、下水道管の老朽化による破損が原因と報じられているが、こうした事故は他人事ではなく、首都東京に目を向けると、都内の道路下にも、下水道管が網の目のように張りめぐらされており、事故防止対策は喫緊の課題である。
八潮市の道路陥没を受けた緊急的な取り組み状況を伺う。あわせて、都は衛星やAIなどの先端技術を活用して、効果的な保守点検や更新に取り組んでいくべきと考えるが、見解を求める。
【下水道局長】
八潮市の道路陥没を受けた対応についてであるが、直ちに国道及び都道を巡視するとともに、腐食のおそれが高い箇所等の下水道管の緊急点検を進め、現時点で異状がないことを確認している。
将来にわたる安定的な流下機能の確保と下水道に起因する道路陥没防止のため、きめ細かな維持管理が重要である。そのため、日頃の巡視と管の内部をテレビカメラ等で確認し、状態に応じた補修の実施に加えて再構築を計画的に進めている。
これにより、整備年代の古い都心部のエリアの陥没は約9割減少している。また、AIなどの先端技術を活用した効果的な手法の技術開発も進めている。今後、予防保全を重視した取り組みを一層推進し都民の安全・安心を確保していく。
⑥ 都道における道路陥没の未然防止
【質問】
道路陥没事故を防止するためには、路面の下の隙間の発生を迅速に把握し、路面が陥没する前に対応することが大切である。
都道において、道路陥没を未然に防止するため、各路線における陥没リスクを踏まえ、優先度を設定しつつ、点検や調査を効果的に徹底して取り組むべきと考える。見解を求める。
【建設局長】
都は、全ての都道を対象に、日常的な巡回点検により路面の僅かな変化などから異常を発見し、迅速に埋戻し等を行っている。さらに、路面下の空洞を早期に発見するため、地下埋設物の状況やこれまでの空洞の発生実績等を踏まえ、都道約1,100キロメートルを対象に、地中レーダーによる調査を定期的に実施している。
こうした取り組みを着実に推進するとともに、適宜、対象路線や調査頻度の見直しを行い、都民の安全・安心を確保していく。
⑦ 八潮市の災害と類似した災害への対応
【質問】
万が一、都内において、八潮市と同じような道路の大規模陥没による災害が発生した際に、人命救助を確固たるものにすべく、新たな資機材を導入するなど、東京消防庁の対応を伺うとともに、八潮市で行った東京消防庁による救援活動について、消防総監の見解を伺う。
【消防総監】
大規模な道路陥没災害では、隊員の安全を確保しつつ早期に救出活動を行うことが重要である。
八潮市の災害では、事故発生の翌日に要請を受け部隊を派遣したが、時間の経過とともに道路の陥没と下水の流入が拡大していたことから、救出活動は困難を極めた。
都内で類似災害が発生した際は、同様の災害で効果が期待できるドローン、クレーン車及び土砂吸引車を有するハイパーレスキューなどの部隊を即時投入し、救出活動にあたる。
現在も災害は継続しているが、今後、本事案の検証を進め、消防活動体制に生かしていく。
交通施策
① 補助制度の拡充等でホームドア整備の加速を
【質問】
ホームドアの整備には、技術的な課題への対応に加え、財源の確保が不可欠であり、整備の加速には、国と連携し技術的な対応の強化や補助制度の拡充による、より踏み込んだ実効性ある支援をすべきと考えるが、見解を伺う。
【東京都技監】
ホームドアは都民の命を守る重要な施設であり、整備の加速には官民の連携による課題解決が不可欠である。
都は協議会において、駅の構造や利用者の特性を踏まえ、補助の重点化や、工期とコストの縮減に向けた検討を進めてきた。令和7年度から、都が事業者に直接補助する制度を創設し、特別支援学校の最寄駅では、番線当たりの補助上限額を1億7,000万円に引き上げる。また、国が協議会で示したホーム通路幅の基準の運用に対する考え方や対応事例を共有し整備を促す。
新たな補助制度の活用や、国と連携した技術的支援により、ホームドア整備の更なる加速を実現していく。
② 高速道路の本線料金所の早期撤廃で渋滞の緩和を
【質問】
長年にわたって都議会公明党は、渋滞の要因となっている高速道路の本線料金所の早期撤廃を実現するため、料金所のETC専用化を強く求めてきた。
令和7年1月のETC専用化連絡調整会議において、首都高のETC専用化を令和7年度末に73箇所まで増やす計画を公表した。
この機会を捉え、永福料金所をはじめとする都内高速道路の本線料金所を早期に撤廃する取り組みを開始すべきであるが、知事の見解を伺う。
【知事】
ETC専用化及び本線料金所の撤廃は、交通の円滑化や事故の低減につながるため、早期に実現することが重要である。
令和6年7月には私自ら、国土交通大臣にETC専用化及び本線料金所撤廃を要望し、国や首都高などと協議を加速してきた。
その結果、令和7年度末には、首都高において、現在3割程度である都内のETC専用化の整備率が、約8割まで拡充するとともに、関係者間で本線料金所撤廃に向けた取り組みを開始する。
都としては、これらを踏まえ、予算を新たに計上し、永福料金所をはじめとする本線料金所撤廃の早期実現に向けた取り組みを強力に推進していく。
③ 羽田空港アクセス線西山手ルートの早期整備
【質問】
現在、JR東日本は、2031年の完成を目指し、羽田空港と東京駅を結ぶ羽田空港アクセス線東山手ルートの整備を行っている。併せて、羽田空港と新宿駅を結ぶ西山手ルートを整備していけば、中央線沿線及び青梅線沿線の住民は、乗り換えなしで羽田空港まで行ける可能性が広がる。
都議会公明党が令和6年の第1回定例会において、西山手ルートの早期整備を求めたのに対し、知事からは、羽田空港アクセス線西山手ルートの整備に向けて、国、JR東日本と協議を行っていくと踏み込んだ答弁があったが、現在の協議の状況と今後の取り組みについて、知事の見解を伺う。
【知事】
羽田空港の機能を最大限に発揮していくためには、鉄道によるアクセスの充実を図ることが重要である。西山手ルートは、中央線や埼京線等と接続することで、多摩方面も含めた広範囲にわたる空港アクセス利便性の向上が期待される。
都は、政府提案要求や国の検討会などの場において、都市鉄道の整備に必要な財源確保を含む整備促進策を要請し、国からは、新たな利用者負担制度の方向性などが示されたところである。
また、これまでのJR東日本との連携に加え、令和6年度からは、国の助言や協力を得ながら、事業スキーム等の具体化に必要な検討を実施している。
引き続き、東山手ルートの進捗状況を勘案しながら、国やJR東日本等との協議調整を積極的に進めるなど、空港アクセス利便性の向上に取り組んでいく。
④ 貸切バス事業者への燃料費支援
【質問】
都は、都議会公明党の強い要望を受け、中小貨物運送事業者、乗合バス事業者及び中小タクシー事業者に対する燃料費の支援を行っている。
令和6年第4回定例会の代表質問で、都民生活や都内経済と密接にかかわっている貸切バスについても、燃料費の支援が必要であると訴え、都から、貸切バスについても必要な対応を検討していくとの方針が示され、令和6年度最終補正予算に盛り込まれた。速やかに支援を実施するべきと考えるが、都の見解を伺う。
【東京都技監】
貸切バスは、ニーズが多様化する観光客の移動手段として経済活動を支えるほか、高齢者や障害のある方々の福祉施設への送迎に利用されるなど、都内の円滑な人の移動に貢献している。
燃料費の高騰や人手不足等の影響を受けている貸切バス事業者についても、都民生活において果たす役割等を踏まえ新たに対象に追加し、令和7年9月末までを支援期間として実施することとした。
今後は、貸切バス事業者へ速やかに支援が行き届くよう、必要な手続を進めていく。
都政課題
① 農地の保全のための相続税猶予等の施策展開の加速を
【質問】
東京農業が直面する最大の課題が、相続に伴う農地の減少である。兼業農家が大半を占める東京の農家では、相続時には、比較的に利幅が少ない農地を宅地に切り替えて売却する相続税対応が常態化している。
都内農地の減少をいったん食い止めるためには、中小企業での事業承継において、承継する株式にかかる贈与税・相続税のすべてが納税猶予の対象となる10年間限定の措置などの対策を参考に、都内の兼業農家において、期間を限定してでも、相続税の対象外とする措置を実現し、その効果の検証を国に求めるなど、農地の保全に向けた施策展開を加速すべきと考えるが、知事の見解を伺う。
【知事】
都市と共存する東京の農地は、新鮮な農産物の供給とともに、緑の確保や防災など多面的な機能を有する大切な財産であり、次の世代に確実に引き継いでいかなければならない。
この貴重な都市農地を保全するため、都は、様々な機会を通じて、国に働きかけを行ってきた。国は、都市農業振興基本法を制定し、税制上の措置などを講じているが、相続を契機とした農地の減少は、いまだ、歯止めがかかっていない。
都は、全国に先駆け、生産緑地の貸借を奨励する制度を開始しており、令和7年度はこの取り組みについて思い切った拡充を図る。生産緑地を買い取り市民農園等に活用する自治体への支援も進めていく。
今後こうした取り組みに加え、農業関係者の意見を聞き、相続税の猶予などを国へ要望する等あらゆる手立てを講じ、東京の農地を守り抜く。
② 農業の後継者への助成規模拡充支援等の強化
【質問】
都はこれまで、農業未経験者による農業参入に重点をおいて支援してきたが、今後は、営農を続けてきた農家についても、後継者が相続を乗り越え、安心して農業を継続できるよう支援を強化していくべきである。
また、資材や燃料価格の高騰が農業経営を圧迫する中、化学肥料や農薬などの削減につながる環境配慮型農業への転換を進めるべきと考えるが、併せて都の見解を伺う。
【産業労働局長】
東京農業が着実に承継され、魅力あるものとして発展していくためには、コスト削減による経営の安定化と、環境配慮型への転換等、新たな取り組みを促すことが重要である。
都はこれまで、認定新規就農者等に対し栽培施設の整備を支援しており、令和7年度は、親元で就農する後継者も利用できるよう見直すほか、農業機械も補助対象とする。
また、環境に配慮する農業者に対し、有機質肥料等の購入や遮熱カーテンを備えた施設の整備に助成している。
今後は、この助成規模等を拡充するほか、農薬削減効果の高い防虫ネットの購入やハウスを覆うビニールの長期間使用可能なものへの転換等の取り組みの支援も開始する。
③ 農業における暑さ対策支援
【質問】
近年、東京の夏は、連日のように熱中症警戒アラートが発表される異常な暑さであり、新鮮な食材を食卓に届ける東京農業においても、品質低下などの影響が出始めている。
また、猛暑は、農業者にとって命に係る重大な問題であり、作業中の熱中症による死亡事故がしばしば報道されている。
暑い中でも安定的に生産できる栽培方法や、安心して仕事ができる環境改善への支援など、効果的な暑熱対策を講じるべきと考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
都は、本格的な暑さを迎える前に収穫できる品種を開発するとともに、普及指導員による農作業中の熱中症に関する注意喚起などを行ってきた。
令和7年度は、暑さの影響を受けにくい野菜等の更なる品種の選定や最適な資材の活用方法など、高温障害の抑制に効果がある技術開発に取り組む。また、快適に農作業ができるよう、生産施設への空調設備の設置等に係る費用への補助を拡充し、農業経営を後押しする。
④ 民間路線バスの運転士不足
【質問】
都議会公明党は、令和6年の第4回定例会において、運転手不足を背景としたバス路線の廃止や運行回数の削減といった事例が顕在化していることから、運転士確保に向けた運輸業界の取り組みを積極的に支援する施策について、迅速に取り組むべきと質問し、都からは、運転士確保に向けた対策を検討するなど、積極的に取り組んでいくとの答弁を得ている。
そこで、その後の検討を踏まえ、都が運転士確保に向けた支援を具体的に行っていくべきと考える。都の見解を伺う。
【東京都技監】
不足するバス運転士を確保するためには、官民が一体となり、2024年問題などを踏まえた多角的な対策を早急に進めていくことが重要である。都は、政府提案要求等において、技能を有する人材の活用や、運転士養成機関の設立等を要望するとともに、乗合バス事業者連絡会議において、運転士確保についての情報共有を行った。
令和7年度は、外国人乗客向けAI翻訳等のDX技術の試験導入など、運転士の負担軽減への支援に取り組む。また、連絡会議において運転士確保策の議論を進めるとともに、交通局とも連携し、バス事業の魅力発信など、東京バス協会や事業者の取り組みを国と共に強力に後押ししていく。
⑤ 都営バスの運転手不足の対策
【質問】
都営バスにおいては、応募者の大幅な減少や中途退職する乗務員の急増により、今後、乗務員が不足する見込みとのことである。こういった状態を放置しておくと、路線の休止や減便につながり、民間バスと同様に都民に大きな影響を及ぼす。
今後、乗務員が不足した場合には、都民に大きな影響を及ぼさない対応策を検討するべきである。また、働き方改革に対応した柔軟な働き方を検討するとともに、新卒人材への育成にも力を入れていくべきである。都営バスの運転手不足対策について、都の見解を求める。
【交通局長】
都営バスは、地域の身近な移動を支える重要な役割を担っている一方、民間バス事業者と同様、乗務員不足により路線の維持が困難となってきている。
このため、若年層の乗務員の採用に向けて養成型選考を拡充するとともに、多様な働き方に対応すべく、短時間勤務を導入する。今後、こうした乗務員確保の裾野を広げる取り組みを一層進め、路線の維持に努めていく。
また、乗務員が不足する場合にも、朝ラッシュ時間帯の運行本数を極力維持するほか、時間帯別の利用状況をきめ細かく把握し、利用者への影響に最大限配慮しながら、ダイヤを設定していく。
⑥ 行政手続における郵送申請時のキャッシュレス対応の強化
【質問】
司法書士などの代理人による不動産の相続登記の代理申請の際に、必要となる住民票や戸籍等の関係書類を、自治体から郵送で取得する場合がある。
都議会公明党が令和6年の第3回定例会で、郵送申請時の証明書発行手数料のキャッシュレス化に取り組む自治体を支援することを求めたのに対し、都は、GovTech東京と連携し、多くの都内自治体が導入している手続きのクラウドサービスでキャッシュレス化を導入する方針を明らかにした。
そこで、多くの都内自治体が、キャッシュレス化への対応が進むよう、取り組みを強化すべきと考える。都の見見解を伺う。
【デジタルサービス局長】
利用者の利便性向上に向け、窓口職員の負担軽減を図りながら、区市町村での導入を広げることが重要である。
このため都は、多くの区市町村が導入している手続きのクラウドサービスを活用した申請の仕組みを新たに整備し、キャッシュレス化を希望する自治体への技術的支援を開始した。さらに、令和7年2月、約30自治体が参加する担当職員向けの研修会を実施し、先行自治体のノウハウ共有や意見交換、課題解決に向けた相談を行う中で、複数の自治体が導入意向を示している。
今後は、DXの責任者である区市町村CIOへの働きかけや、Gov Tech 東京の技術力を活かしたきめ細かなサポートを実施していく。
⑦ ローン・オフェンダー対策
【質問】
最近の犯罪の傾向として、SNSを利用した闇バイトにより、時には殺人まで犯す凶悪な強盗事件、いわゆる匿名・流動型犯罪や、同じくSNSを利用したロマンス投資詐欺、仮想通貨投資詐欺など、従来の犯罪の枠組みを超えた犯罪が増加してきている。
さらには、予見することが難しいテロ組織に属さない個人による単独テロ行為、いわゆるローン・オフェンダーによるテロ行為なども起こっている。
その背景には、SNSによるデマや虚偽の情報の流布を信じ込んでしまうという要因があり、都民には、いつ自身が被害の当事者になるかもしれないと不安が広がっている。これらの対策は、複雑で、かつ専門的な知識も必要だが、警視庁において総力を挙げて対応して頂きたい。
そこで、ローン・オフェンダーによるテロ行為に対する取り組みについて、警視総監の見解を伺う。
【警視総監】
警視庁では、現実空間とインターネット空間の両面において、種々の警察活動を通じて不審情報を収集し、脅威の度合いを精緻に分析することで、不法事案の「兆し」の段階からの把握を徹底しているところである。
また、関係機関や民間事業者等と連携して横断的なネットワークを構築し、テロ等不法事案への危機意識の共有を図るとともに、合同訓練等を実施するなど、それら事案の未然防止に向けた対策を推進している。
さらに、令和7年度には、公安部内にローン・オフェンダー対策に専門的に従事する部署を新たに設けた上で、情報の一元的な集約・分析、部門を横断した的確な対応など、各種対策の実効性を一層強化する。
引き続き、都民、国民の安全、首都東京の安全を確保するため、警視庁の総合力を発揮し、ローン・オフェンダー対策にあらゆる手を尽くしていく。
⑧ 個人住宅における防犯機器等の支援拡大
【質問】
都議会公明党は、令和6年第4回定例会で、都民の防犯意識の高まりを踏まえた支援策が急務であり、個人住宅などへの防犯カメラなどの補助を実施すべきと訴えた。これに応え都は、令和7年度予算案に防犯機器等購入緊急補助事業を盛り込んだことを高く評価する。
この補助事業について、居住実態に応じて、大勢の都民が購入しやすい制度設計に努めるべきである。
また、闇バイトに誘導する手口を高校生、中学生等にわかりやすく示し、闇バイトに引き込まれない取り組みが必要と考える。都の見解を伺う。
【生活文化スポーツ局生活安全担当局長】
令和7年度、個人住宅における緊急の防犯対策として、防犯機器等を購入・設置する都民に対し、都が1世帯当たり2万円を上限に、経費の2分の1を補助する事業を実施する。地域の実情や居住形態を踏まえ、防犯カメラやカメラ付インターホン、防犯フィルムなど、侵入盗被害防止に効果的なものを幅広く補助対象とする。
また、未成年者が闇バイトに関わらないよう、令和6年秋から、若者向けの加害防止特設サイトやリーフレット等の活用を中学・高校にも広げており、令和7年度は啓発漫画を新たに作成するなどコンテンツを充実させる。
こうした取り組みにより、都民の安全安心を確保していく。
⑨ 民間資金を活用した市場施設の機能更新
【質問】
中央卸売市場では、施設の老朽化が進む中、各市場の立地特性に応じた民間活力の取り込みが必要。民間資金の活用を図り、建替費用に都財源の投入を極力抑えるべきである。市場会計の40年後の行き詰まりを回避すべく、民間活力とのコラボに向け、計画の立案に取り組むべきと考える。見解を伺う。
【中央卸売市場長】
中央卸売市場が、将来にわたって、生鮮品等流通の基幹インフラとしての役割を果たすため、市場業者を含めた民間の力も活用し、老朽化した市場施設の機能強化や施設の有効活用を進めていかなければならない。
こうした観点に立ち、都は、豊洲市場において、地域のまちづくりや活性化に貢献するため、千客万来施設を民設民営で整備した。また、淀橋市場の再整備に当たり、狭隘な市場施設の高度利用を図るため、市場業者による自動立体冷蔵倉庫の整備を進めている。今後、各市場の立地や特性を踏まえた、民間の力の更なる活用について検討を重ね、持続可能な市場経営を実現していく。
⑩ スマホを持たない人にも物価高対策の手立てを
【質問】
都議会公明党は、全ての都民を対象にした物価高騰対策を、令和6年第4回定例会代表質問や予算要望においても提案してきた。
こうした中、都は東京都公式アプリを活用した「つながるキャンペーン」として、15歳以上の全都民に対し、1人当たり7000ポイントを支給する補正予算を計上した。
しかし、本キャンペーンは、スマホ所有とマイナンバーカードと連携することが前提条件であり、操作が不慣れな方だけでなく、スマホを持っていない方も少なくない。
こうした都民の方々も物価高騰に苦しんでおり、本キャンペーンに参加できるよう、都として手立てを講じるべきと考えるが見解を伺う。
【デジタルサービス局長】
東京アプリを活用して、都民サービスの質を向上していくためには、幅広い都民が利用できるよう、支援策を講じることが重要である。
こうした観点から、令和7年度は、デジタルに不慣れな方を対象とした区市町村のスマホ相談会への支援の拡充などを図るとともに、新たにスマホをお持ちでない高齢者の購入費を助成するため、高齢者施策推進区市町村包括補助の先駆的事業による支援を検討していく。こうした取り組みを通じ、現下の厳しい経済情勢の中、都民生活の応援にも資する「つながるキャンペーン」の浸透を図り、東京アプリの利用拡大に取り組んでいく。
⑪ 高額宿泊者の宿泊税の見直しと税収の活用を
【質問】
インバウンド(訪日外国人観光客)の増加により、近年、外資系ホテル等が進出し、高額な宿泊が増加している。併せて、ゴミの問題やマナー違反など様々な問題も増えている。これらの課題解決の対策費に充てるためにも、宿泊料金15,000円以下を免税とし、15,000円を超える料金については定率課税とするなど、宿泊税の見直しについて、改めて、知事の見解を伺う。
【知事】
宿泊税制度の創設から20年以上が経過する中、高額な宿泊の増加や他の自治体における制度の導入など、宿泊税を巡る状況は大きく変化している。
こうした中、令和6年度、東京都税制調査会から、定率制や定額制といった課税方式も含め、宿泊税のあり方について報告をいただいた。この間、都は、都税調の報告も参考にしつつ、宿泊料金の調査などを進めてきた。
今後は、納税者や宿泊施設事業者の負担感にも十分配慮しながら、課税のあり方や使途について検討を更に進め、令和7年内を目途に、宿泊税の見直しについて、素案をお示ししたいと考えている。