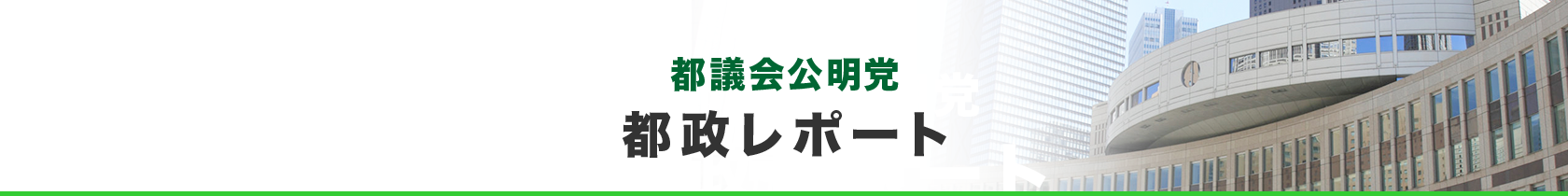中小企業支援策
① 廃業時の土壌汚染対策における事業者の負担軽減について
【質問】
メッキや金属加工などの町工場、個人経営のクリーニング店などは、後継者不足や原材料費の高騰等により、やむなく廃業する事例が増えている。
法令では、有害物質を取り扱う工場や事業場の廃止時には、事業者が土壌汚染の調査の実施や汚染状況に応じた対策が義務付けられているが、事業を継続できない中小事業者等は、廃業時に初めて土壌汚染への対応を知る場合が多く、調査・対策の検討や事務手続き等が負担になっていると聞く。都は、技術的な支援や届出手続きの効率化などを行い、中小事業者の負担軽減を図るべきと考えるが、見解を求める。
【環境局長】
中小事業者の負担を軽減し、円滑な土壌汚染対策を進めるためには、届出手続きから対策に至るまで事業者の実情に応じた丁寧な対応を行うことが重要である。
これまで都は、土壌汚染対策を解説する事業者向け講習会の開催、ガイドラインの作成・配布等、様々な機会を捉え、分かりやすい情報発信に努めてきた。
また、対策を検討する中小事業者に専門アドバイザーを無料で派遣し、技術的助言や土壌調査を行ってきた。
これらに加え、DX推進の観点から、今後新たに届出手続きのデジタル化とともに、土壌汚染情報のオープンデータ化等を迅速に進め、事業者の負担を軽減していく。
② 操業時からの土壌汚染対策の支援について
【質問】
土壌汚染対策として慣例的に行われている汚染土壌の全量掘削には高額な費用がかかり、廃業時の中小事業者にとって経済的に大きな負担となっているため、工場等跡地の売却や土地利用の転換が円滑に進められない事態が頻繁に生じている。
都は、令和5年度から、土壌汚染が引き起こす地下水汚染について、都が認定した拡大防止技術を実証する中小事業者に対して最大3,000万円を支援するという全国初の取り組みを実施しているが、土壌汚染対策は操業中から時間をかけて行うことで、コスト低減や選択肢が広がり、より合理的な対策が可能となることから、廃業時に加え、操業中の事業者も地下水汚染拡大防止技術実証事業の支援対象とすべきである。
都は、操業中からの対策も含め、環境にやさしく経済性を備えた土壌汚染対策を進められるよう取り組むべきと考えるが、知事の見解を求める。
【知事】
中小事業者が、環境への負荷が少なく経済合理性を兼ね備えた土壌汚染対策を行うことは、将来の土地の有効活用の観点からも重要である。
このため都は、土壌汚染による地下水汚染の拡大を防止する先進的な手法を認定し、その技術を活用する事業者に対し経費を支援している。これにより、効果的な対策の確立とコスト負担の軽減を図り、持続可能な土地利用の転換を進めている。
今後、操業中であっても実施可能な土壌地下水汚染対策を新たに後押しすることで、将来のリスクに備えていく。
こうした取り組みにより、健康被害の防止に加え、不動産取引の円滑化を図り、社会や経済に配慮した対策を推進していく。
③ 小規模企業が共同で行う技術開発・設備導入支援について
【質問】
高い技術力を持つ小規模・零細企業の多くは、大手からの第4次・第5次などの下請けとしてサプライチェーンを支えている。こうした企業が都内で事業継続していくためには、脱炭素化やデジタル技術の進展などの変化に対応し、各社が持つノウハウやアイディアを相互に結集して新たな取り組みにチャレンジするなど、企業の変革を進めていく必要がある。
都は、サプライチェーンを支える企業の経営を後押しするため、小規模企業がグループで行う設備の導入や販路開拓などへの支援を行うべきと考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
中小企業が経営環境の変化に適応し、東京の産業活力を維持・発展させるためには、サプライチェーンを形成する中小企業の対応力を高めることが重要である。
そのため都は、専門家が経営計画の策定を伴走支援するとともに、企業間のネットワーク構築につなげる継続的な勉強会や交流会を開催してきた。
令和7年度は、新たにサプライチェーンを担う小規模企業が共同で行う技術開発や受注の確保に必要な設備導入のほか、取引先の多様化に向けた販路開拓などの取り組みに対し、最大2,000万円を上限に助成する。
これらにより、都内の産業基盤の強化につなげていく。
就業支援
① 若者の自律的なキャリア形成への支援について
【質問】
近年、キャリアを築く選択肢として転職が一般的になりつつあるが、雇用の流動化も進む中で若者が、同期や先輩と出会い将来のビジョンを共有したり、キャリアのモデルを見つけたりすることが難しくなってきている。
都はこれまで、東京しごとセンターで就職後の定着支援を行ってきたが、この支援を就職活動中の学生や再就職を目指す若者などにも拡大し、仕事探しの段階からキャリア形成のサポートをする新たな支援を展開するべきと考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
新卒一括採用の見直しなど雇用の流動化が加速する中、若者が将来に目標を持ち、職業人生を自ら設計できるよう後押しすることは重要である。
都は、しごとセンターにおいて、入社後3年までの若手社員を対象に、職場で活躍するスキルを磨くセミナーや若者同士の交流会を実施している。令和7年度は、これに加え、学生を含む求職者に対し、就職前から継続的に支援するプログラムを新たに開始する。
また、キャリアカウンセラーがライフプランなどの相談に応じるほか、異業種交流や先輩と触れ合う機会を増やしていく。
これにより、若者の主体的なキャリア形成を促進する。
② 短期の就業体験の活用について
【質問】
若者の間では、隙間時間を活用したスポットワークが広がっていて、人材確保・定着の新たな手法としても注目されている。
就職後「仕事が自分に合わない」などの理由で早期に離職してしまう割合は依然として高く、事前の理解が不足していることが窺える中、こうしたリスクを軽減する手法として、スポットワークや職業体験は有用である。
社会経験の少ない若者が自分に合った仕事に巡り合えるよう、短期・単発で様々な仕事を体験できる仕組みを通じ、より多くの若者に選択肢を見つける機会を提供していくべきと考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
若者の就職後のミスマッチを防ぐため、実際の仕事を体験する機会を通じて、業界や職種への理解を促すことは重要である。
都は、学生等に対し、短時間の仕事を3日間で3社体験できる機会を提供し、インターネットを介して幅広い会社の中から自分の都合に合わせて、いつでも気軽に選択し申し込める仕組みとしている。
この支援について令和7年度は、国の新卒者向けハローワークとも連携して周知を強化し、より多くの若者と企業の参加を促していく。
これにより、若者の企業への円滑な就職を後押しする。
高齢者施策
① 老朽化が進む特別養護老人ホーム等の改築・改良工事支援について
【質問】
2025年、いよいよ団塊の世代が後期高齢者となる年を迎え、介護サービス基盤の整備がますます重要になっているが、介護保険制度導入前から地域の高齢者福祉を支えてきた特別養護老人ホームの中には、建物や設備の老朽化が進んでいるものの、物価高騰などによる運営費の増加や、建築費の高騰もあり、必要な工事をなかなか行うことができない施設があると聞く。
特別養護老人ホームなどの介護保険施設が、入所者に安全で快適な環境を継続して提供できるよう、効率的に設備更新や内装・外壁等の改良工事を行うための支援が必要と考えるが、都の見解を求める。
【福祉局長】
都内では、老朽化のため、今後改築等が必要となる施設が増加している一方、近年の建築費高騰等により、整備をためらう事業者も多くある。
都は、令和6年度から建築費高騰の状況を反映できるよう、施設整備費の補助に物価スライド方式を導入している。令和7年度は、工事に係る費用や期間を抑えながら建物の長寿命化が図れるよう、施設入所者を一時的に移転させつつ、建物の構造部分を残して行う全面的な改良工事に対し、1床当たり最大834万円、定員100名で最大約8億円の補助を新たに開始する。
こうした取り組みにより、事業者が、入所者の生活環境に配慮しながら整備を進められるよう支援していく。
② 特別養護老人ホーム等の空調設備の更新支援について
【質問】
近年の夏は災害級の猛暑となり、特別養護老人ホームでも空調設備がフル稼働しているが、空調設備が老朽化し、故障するようなことがあれば、入所者の命にかかわる事態になりかねない。
暑さ対策として、特別養護老人ホームが、必要な時期に空調設備を更新できるよう支援すべきと考えるが、見解を求める。
【福祉局長】
近年、記録的な猛暑が続く中、要介護高齢者が入所している特別養護老人ホーム等で安心して生活するためには、空調設備を適切に利用できる環境が重要である。
都はこれまで、施設が大規模改修を行う際、空調設備を含め、その費用を補助してきた。
令和7年度からは、老朽化した空調設備の更新について、次の大規模改修に係る補助が活用可能となる時期が到来する前でも補助制度を活用できるようにし、1施設当たり最大3,500万円の支援を行う。
こうした取り組みにより、入所者が安心して暮らせる環境の整備を推進していく。
災害対策
① 浄水場の震災対策の強化について
【質問】
令和6年1月に発生した能登半島地震では、最大約14万戸で断水が発生するなど、上下水道施設に甚大な被害が生じたが、東京においても切迫性が指摘される大地震に備え、上下水道の強靭化を進めていかなければならない。
都内の4割の水を供給する金町及び三郷浄水場は、荒川区民はもとより、区部東部に暮らす人たちにとっては極めて重要な浄水場であり、大規模な地震が発生したとしても水を作り続けなければならない。そこで、金町及び三郷浄水場における震災対策を強化すべきと考えるが、見解を伺う。
【水道局長】
震災時でも浄水処理を継続するためには、施設の耐震化が重要であり、水道局では、安定給水を確保しながら両浄水場の耐震化を計画的に推進している。
合わせて、停電時にも継続的な電力供給が可能となるよう常用発電設備の整備を進めており、三郷浄水場では令和6年4月から運用を開始した。また、令和7年度には、金町浄水場において、発電効率の良いガスエンジン方式を初めて採用した、当局で最大規模となる設備の整備に本格的に着手する。これらにより、両浄水場における震災への備えを更に強化し、荒川区を含めた区部東部の給水安定性を向上させていく。
② 下水道管の耐震化の加速について
【質問】
公明党能登半島地震災害対策本部の報告によれば、耐震化が実施されていた下水道管では排水機能が概ね確保されるなど、対策の有効性が改めて確認されたが、大規模な地震が発生した場合においても、防災上重要な役割を担っている施設は適切に機能を確保しなければならない。
防災・減災の要の拠点となる、避難所や災害拠点病院等から排水を受ける下水道管の耐震化を加速すべきと考えるが、都の見解を伺う。
【下水道局長】
過去の震災を踏まえ、下水道機能や交通機能を確保するため、対象施設を重点化し耐震化を実施している。具体的には、避難所等の排水を受け入れる下水道管の耐震化や、液状化の危険性が高い地域における緊急輸送道路等でマンホールの浮上抑制対策を実施している。
令和7年度は、荒川区の防災拠点である「あらかわ遊園」等を対象とし、下水道管の耐震化に新たに着手するなど、整備を進める。さらに、地元区のマンホールトイレ要望箇所における下水道管の耐震化等を新たに検討し、対策の強化を図る。
今後、これらの対策を積極的に進め、安全・安心なまちづくりに貢献していく。
③ 区道における無電柱化の促進について
【質問】
荒川区は、区内の6割が木造住宅密集地域であり、防災力の更なる向上には、無電柱化が急務であり、地域の方々が日々の生活で使用する区道の無電柱化が非常に重要である。
荒川区は、国と都の財政支援を受け、令和あらかわ病院周辺等で事業を進めているが、令和元年に策定した荒川区無電柱化推進計画によると、総延長197kmの区道における無電柱化の整備済み路線は10kmであり、整備率は5%という状況である。
荒川区道は道幅が狭く、技術的な課題が多いことが要因の1つとなっているが、木密地域を多く抱える荒川区において無電柱化を進めるためには都の技術支援が不可欠である。
荒川区道の無電柱化促進に向け、更なる技術支援が必要であると考えるが、都の見解を伺う。
【建設局長】
東京全体の防災機能を強化するためには、都道のみならず区市町村道の無電柱化を促進することが重要である。
荒川区は現在、都のチャレンジ支援事業制度を活用し、8路線で事業を実施しており、さらなる促進に向けては、狭隘な道路において、地上機器の設置場所を確保するなどの課題を解決する必要がある。
このため都は、公共用地活用などのノウハウに加え、研修会等を通じて最新の技術動向や整備事例の情報共有を一層充実させるなど、技術支援を強化していく。
今後とも、安全安心な東京の実現に向け、積極的に区市町村を支援し、都内全域の無電柱化を推進していく。
都立公園の防災機能と回遊性
【質問】
荒川区にある都立尾久の原公園の新しい管理所の整備にあたり、来園者がより便利で快適に利用できる機能や、避難場所としての防災機能を充実させるべきと考える。また、現管理所の跡地と区立公園を接続し、両公園の回遊性を高めるべきであるが、併せて都の見解を伺う。
【建設局長】
尾久の原公園は、区部東部の水と緑のネットワークを形成する拠点であるとともに、避難場所として防災上も重要な都立公園である。
新しい管理所は、授乳室や救護室を備え、イベント時には会議室と屋外テラスを一体的に活用できる仕様とする。あわせて、非常用発電設備や避難者等に情報を提供するデジタルサイネージの整備など防災機能の充実を図ることとしており、令和7年度から工事に着手する。
また、来園者の回遊性向上と避難ルートの充実を図るため、現在の管理所撤去後、隣接する区立公園に接続する。今後、地元区と連携しながら取り組んでいく。
小児インフルエンザ経鼻ワクチンの任意接種補助
【質問】
都議会公明党の要望により、令和6年度より実施している小児インフルエンザワクチンの補助を令和7年度も継続するとともに、経鼻ワクチンも補助対象にすべきと考えるが、見解を伺う。
【保健医療局長】
都は令和6年度、子育て支援の観点から、注射による2回接種が必要な13歳未満の自己負担額が、1回接種の13歳以上と同程度となるよう、接種費用を助成する区市町村への補助を開始し、42自治体が活用している。
補助事業は令和7年度も継続し、様々な機会を捉え、区市町村に事業の趣旨や仕組みを丁寧に説明していく。
また、令和6年10月から新たに流通が始まった、鼻の中に噴き付ける経鼻ワクチンは、接種回数が1回で、注射に比べ、特に小さなお子さんの身体的負担も軽いと期待されており、都は、令和6年度の接種実績や今後の流通状況等を注視していく。