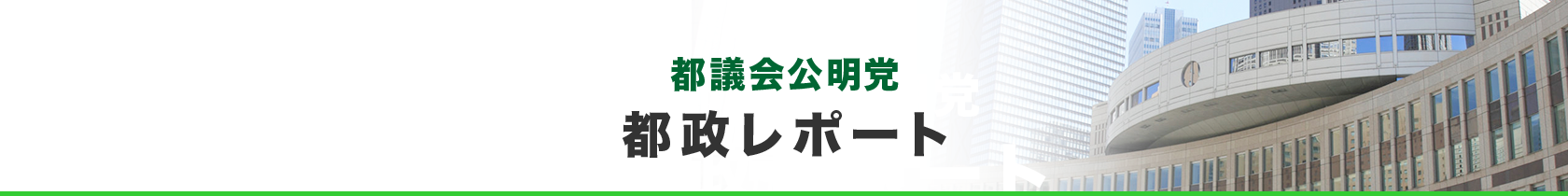医療・福祉
① NICU入院児への支援について
【質問】
早産などで小さく生まれた赤ちゃんは、NICUでの入院が必要となり、家族は子どもの健康状態、将来への不安などを抱えていることが多く、心理的なサポートが必要である。また、子どもへの親の関りが親子の愛着形成にとって重要であり、入院中に子どものケアを習得し、退院後、自宅で安心して育児ができるよう、入院時から退院以降も切れ目ない支援が必要である。
NICUに入院された子どもが安心して在宅療養に移行できるよう、都としてNICU入院児への継続した支援を充実させていくべきと考えるが、知事の見解を伺う。
【知事】
NICUに入院した子供が在宅療養に円滑に移行するためには、保健、医療、福祉の関係機関の連携を強化し、家族へ包括的なケアを提供することが重要である。
このため都は、NICU入院児の在宅移行支援や退院後の生活支援を担う人材を育成するとともに、NICUを有する医療機関と地域との連携強化を進めている。
また、医療機関にNICU入院児支援コーディネーターを配置し、入院後早期からの支援はもとより、退院後も必要に応じて家庭訪問などを行っている。
令和7年度からは、家族への支援を更に充実し、NICUに入院した時から退院後まで、安心して療養生活を送れるよう切れ目のない支援を一層推進していく。
② ファミリーセンタードケアによる入院児と家族への支援について
【質問】
NICUにおける入院児と家族への支援として、「親と子のきずな」を育むファミリーセンタードケアが注目されている。赤ちゃんの成長や発達を助け、退院を早め、両親の気分の落ち込みやストレス、不安などをやわらげ、母乳の分泌がよくなるといわれている。
都内のNICUにおける入院児と家族に対する支援の充実に向け、ファミリーセンタードケアが進むよう、都として取り組んでいくべきと考えるが、都の見解を伺う。
【保健医療局長】
NICUで家族が子供と一緒に過ごし、子供のケアに積極的に関われるようにするには、医療機関によるきめ細かなサポート体制が重要である。
一方、医療機関では、家族支援を担う人材の不足や財源面の課題などから、家族が子供と過ごせるファミリーセンタードケアの取り組みが進んでいない。
このため都は、国内外の先進事例を参考にしながら、令和7年度から新たに、医療機関での取り組みを進めるリーダー的人材を育成するとともに、その人材を配置する医療機関を支援する。今後、ファミリーセンタードケアを推進し、NICU入院児の家族を支える取り組みを充実していく。
③ 小さく生まれたお子さんの退院支援手帳「のびのび」について
【質問】
都では、周産期医療対策の一つとして、リトルベビーハンドブックともいえるNICU退院支援手帳「のびのび」を平成23年に作成した。この手帳は、小さく生まれたお子さんの退院準備から成長発達を継続的に記録できるもので、退院後の外来の記録や地域での情報などを家族が記録するノートになっている。
医療機関等に配布してきたが、あまり活用されていない現状があった。現在、改定が進められていると思うが、実際に利用する当事者の声を踏まえ、より使いやすく、手帳が活用される渡し方の工夫をしていくべきである。都の見解を伺う。
【保健医療局長】
NICU入院児の家族の不安を解消することは重要であり、都は、子供の成長や発達を継続的に記録できる手帳を配付している。この手帳を利用した家族からは、専門的な内容は医療従事者に記録してほしい、退院後に利用できる子育てや療育などの相談先の情報を掲載してほしいなどの意見をいただいた。
このため、家族とともに医療機関等の関係者が共同で記録できる構成に見直すほか、地域の医療や福祉サービスに関する情報を掲載するなど、より使いやすい内容に改定する。また、医療機関等で家族に配付する際、記録方法を丁寧に説明することで手帳の活用を推進していく。
④ 産婦健康診査の共通受診票の導入について
【質問】
産後うつの早期発見のために、産後2週間、産後1か月など、産後間もない時期の健診が重要である。都議会公明党は、全ての産婦が産婦健康診査を受けられるよう、都内共通受診票の導入を提案し、都からは、都内共通の仕組みの構築に向け、区市町村を後押ししていくとの答弁を得ている。
都は、区市町村など関係者の理解を得ながら、共通受診票の導入の実現に向けた取り組みを一層進めていくべきと考えるが、見解を伺う。
【福祉局長】
産婦健康診査は、産後うつや新生児への虐待の予防等を図ることを目的としており、実施主体である区市町村が医療機関や助産所に委託して実施している。
都内では居住自治体以外での出産が約半数であることから、都は、産婦が分娩を行った都内の医療機関等で、引き続き産婦健診を受診できるよう、区市町村や都医師会と協議し、都内共通受診票の導入の検討について、令和6年12月に合意した。
今後、産婦人科医などの関係者による会議において、健診費用や区市町村と医療機関等との情報連携など、導入に向けた課題等について議論し、検討を進めていく。
⑤ 電子カルテの推進で質の高い医療サービスへ
【質問】
高齢化の進展や働き方改革に対応する中で、質の高い医療サービスを提供するためには、電子カルテの導入によりデジタル化を進め、身近なかかりつけ医から救急医療機関、高度医療を提供する大規模病院など、医療機関同士で医療情報を共有することが重要である。
医療DXの基盤である電子カルテについて、十分に理解し導入が進むよう、医療機関の個々のニーズに寄り添った支援を行うべきと考えるが、見解を求める。
【保健医療局長】
電子カルテの導入にあたっては、医療機関のデジタル化への理解促進を進めることが重要である。
都は医療機関に対して、電子カルテの導入等に関するセミナーを開催しており、令和7年度は新たに、各地域で出張講習会を実施し、デジタル技術の利便性など更なる情報発信を行うとともに、導入に係る相談窓口を開設する。
また、医療機関においてデジタル技術を活用できる人材の育成を進めるため、新たにDX関連の研修の受講や資格取得に関する経費の補助を行っていく。
こうした取り組みにより、電子カルテの導入をより一層促進していく。
⑥ 病院の看護職員宿舎の借り上げ支援について
【質問】
都内は他県と比べ、家賃は高いこともあり、看護職員を安定的に確保していくためには、居住面の支援は重要であり、令和7年度予算案に看護職員の宿舎借り上げ支援を盛り込んだことを評価する。
多くの医療機関に速やかに周知を図るとともに、令和7年4月から支援が開始できるようにすべきである。また、活用にむけた医療機関からの相談にも丁寧に対応すべきと考えるが、事業内容と併せて見解を伺う。
【保健医療局長】
病院による看護職員への居住面の支援は、本人負担の軽減や通勤の容易さなどのメリットから、看護職員の安定的な確保・定着に有効な取り組みである。都は、病院が行う宿舎の整備を支援しているが、物価高騰等の影響から建設費用や施設の継続的な維持管理等が課題となっている。
このため都は、令和7年度、病院が看護職員や看護補助者向けの宿舎を借り上げた場合、令和7年4月から1戸当たり月額82,000円を上限に、病院負担額の4分の3を補助する取り組みを行う。病院に対しては、令和7年3月に説明会を開催するほか、専用の受付窓口を設置し、個別の問合せにも丁寧に対応するなど、多くの病院に活用されるよう取り組みを進めていく。
⑦ 区市町村の看護小規模多機能型居宅介護の新規開設支援について
【質問】
看護小規模多機能型居宅介護は、退院後の在宅生活への移行等、地域包括ケア・在宅療養の推進において、地域密着型サービスとして重要な介護保険サービスである。
設置にあたっては区市町村の計画や指定が必要であるが、都においても更なる設置を促進するべきと考えるが、見解を伺う。
【福祉局長】
看護小規模多機能型居宅介護は、通い、泊まり、訪問介護、訪問看護を一体的に提供することで、高齢者の自宅での療養を支える重要な役割を担う地域密着型サービスである。
都は現在、開設時の整備費について、区市町村に対し独自の支援を行うほか、新規参入と安定的な運営を行う管理者の育成を目的とした研修などを実施している。
令和7年度は、新規開設に向けた支援を更に強化するため、新たに土地賃借料や事務職員雇用経費に対して補助を行う。
今後も区市町村と連携し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう取り組みを推進していく。
⑧ 災害時の潜在看護師等登録制度について
【質問】
近年は日本各地で自然災害が起きており、発災後、看護師を派遣できる体制を整備しておくことは重要である。
都議会公明党は、令和6年第4回定例会の一般質問で、災害時、潜在看護師等を活用し、医療救護活動に従事できるよう体制を構築すべきと提案し、活用に向けた方策について検討していくと答弁があった。
災害時はもとより、新興感染症などの有事にも、活躍できる体制整備を急ぐべきである。見解を伺う。
【保健医療局長】
災害時やパンデミック時に、看護活動に従事するより多くの職員を迅速かつ的確に確保することは重要である。
このため、都は令和7年度、有事の際に、身近な地域における避難所での軽症者対応や健康観察などに従事することを想定した潜在看護師等の登録制度を独自に創設する。
登録希望者に対しては、都の災害医療体制や有事における看護活動等に関する研修を実施するとともに、登録を促すインセンティブとして、東京ポイントを5,000ポイント付与する。
今後、区市町村とも十分に連携しながら、登録制度を運用していく。
防災対策
① 東京都災害情報システムの区市町村連携の強化について
【質問】
東京で巨大地震が発生した場合、被害状況をいち早く把握することは重要である。国道、都道、区道の被害情報を一元管理し、迅速かつ的確な災害対応を行えるよう、最先端技術を活用し、区市町村とのシステム連携がスムーズに図れるよう、東京都災害情報システムを改善していくべきと考えるが、見解を伺う。
【総務局長】
都は、発災時に国や区市町村をはじめとする関係機関等と災害情報を共有するため、東京都災害情報システムを平成3年から運用しており、これまでもハード・ソフト両面の改修を重ねてきた。
災害対策業務の更なる迅速化・効率化に向けて、令和7年度からシステムの再構築に着手する。具体的には、入力画面の改善など操作性の向上、道路や避難所の情報など区市町村等とのデータ連携の強化、地図やグラフなどの必要な情報の視覚化などに取り組んでいく。
DXをより活用することで、迅速な状況把握・分析を実現し、更なる災害対処能力の向上に繋げていく。
② 不燃化への合意形成支援について
【質問】
都議会公明党の令和7年第1回定例会代表質問を受け、都からは「防災都市づくり推進計画の改定案」には、新たに整備地域外の木密地域において防災環境向上地区を指定するとともに、防災生活道路の整備などに対し、国と合わせて補助率を最大で4分の3とし、区市の負担を軽減するという答弁があった。
これから防災まちづくりの検討を開始する地区などは、住民の理解と協力を得ながら丁寧に進めていくことが重要である。
新たに指定する地区における防災まちづくりについては、地元自治体と地域住民がコンセンサスを築きながら進めていけるよう、きめ細やかに支援していくことが必要と考えるが、見解を伺う。
【東京都技監】
都は、令和7年1月、防災都市づくり推進計画の基本方針の改定案を公表した。改定案では、整備地域外において、局所的に対策が必要な木密地域を、新たに防災環境向上地区として指定し、細街路の拡幅や公園整備等を支援することとした。
このうち、新たに取り組みを開始する地区では、防災意識の啓発に向けた専門家の派遣や、住民との協働によるまちづくりの方針策定など、地域に密着した区市の取り組みを支援することで、不燃化への合意形成を促進させていく。
こうした取り組みにより、東京全体の木密地域の解消を進めていく。
③ 東部低地帯の大規模水害時支援物資の水上輸送について
【質問】
ゼロメートル地帯が広がる東部低地帯では、江東5区を中心に大規模水害が発生した場合には、2週間、浸水が継続することが想定されている。
大規模水害時に物資を避難住民に円滑に届けることができるよう、区と連携して、水上ルートを活用した物資輸送の新たな仕組みづくりが必要と考えるが、見解を伺う。
【総務局長】
都はこれまで、大規模地震を想定した水上ルートの活用に向け、関係区、警察、消防等で船舶の確保手順や防災船着場の運用手順を定めるなど、取り組みを進めてきた。
大規模水害時においても、地震を想定した対策を参考に、垂直避難した住民への物資支援等を行うため、地域内の水上輸送について、関係区等と連携し、検討を進めていく。
具体的には、船舶や船着場の運用が可能となる条件や関係機関の役割分担などを定めるとともに、図上訓練等で検証し、大規模水害時においても、確実に物資輸送手段を確保できるよう取り組んでいく。
特別支援学校の増改築
【質問】
特別支援学校に通う児童・生徒数は増加傾向にあるが、都議会公明党は、あらゆる手段を講じて教室の確保に取り組むべきであり、特別支援教育推進計画の第二期第三次実施計画に新築や増改築を位置付けていくべきと求めてきた。
教室不足への対応を一層進める上で、新築に加え、増改築などにおいて、迅速に子供たちを受け入れるための対策に取り組むべきと考えるが、見解を伺う。
【教育長】
知的障害のある児童や生徒が特別支援学校に通学するニーズが増える中、受入れのできる施設を確保する取り組みを速やかに進めることは重要である。
こうした特別支援学校の新設に当たり校舎を建築する場合、基本的な計画を作成し、設計や工事を終えるまで相当の期間を必要としている。
知的障害のある児童等を速やかに受け入れるため、今後、現在の学校の敷地の一部を利用し、短い期間で校舎を建築する方法による整備を行う。この緊急的な対応を含め新築や増改築等に関し、特別支援教育の新たな計画に盛り込み、生徒等の受入れ環境の向上に結び付ける。
環境施策
① きめ細かな食品ロス対策の推進について
【質問】
都内では、外食産業からのロス削減が大幅に進み、令和4年度の推計で31.7万トンとなり、2030年度に半減する目標を達成しているが、新型コロナウイルス感染症が5類に移行した令和5年度からは、宴会などの外食の機会が増えるとともに、食文化の異なるインバウンドがコロナ禍前を上回っており、外食におけるロスの増加が懸念される。
都は、ファミリーレストランやファーストフード店等、都内に数多くある飲食店等において、効果の高い対策が広く浸透するよう、きめ細かな取り組みを進めるべきと考えるが、見解を求める。
【環境局長】
飲食店における更なる削減に向けては、業態や客層に応じた対策と来客者の意識変化を促す取り組みが重要である。
都は令和6年度、業態の異なる複数の店舗において、デジタル技術を活用して食品廃棄物を発生段階毎に分別・計量することで、ロスの削減に有効な対策の実証を行った。
これを踏まえ今後、食べ残し削減やインバウンド対策を含む実践的なコンテンツを作成し、業界団体等と連携したセミナーを継続的に開催する。加えて、持ち帰り容器の利用キャンペーンにより、消費者の行動変容を促す。
こうした取り組みを通じて、外食産業における食品ロス対策の浸透を図り、食品資源の廃棄を一層削減していく。
② 脱炭素化へ家庭からの廃食用油の回収拡大を
【質問】
令和6年12月、堺市に国内初の廃食用油を原料とするSAFの大規模プラントが完成し、令和7年4月以降順次、国内エアラインへの供給が始まる見込みである。
このプラントは、国内で発生する廃食用油だけを原料としており、今後大きな需要が見込まれる。しかし、飲食店等の事業系のものは回収が進んでいるのに対して、家庭からの廃食用油の多くは捨てられているのが現状である。
未だ捨てられている家庭の廃食用油について、さらに回収を進めていくべきだが、都の見解を求める。
【環境局長】
航空分野の脱炭素化に必要なSAFの原料となる廃食用油の回収拡大を図るため、取り組みやすい仕組みを構築し、都民理解を促進することが重要だ。
都はこれまで、大手スーパーとの連携による専用ボトルを使った回収や、航空会社や石油元売会社と連携したPRイベント等を通じ、都民の行動変容を促してきた。
加えて令和7年度は、世界陸上の開催を契機とし、区市町村と協働して回収拠点の拡大を図るなど、集中的なキャンペーンを実施する。これにより選手の移動に伴う実質的なCO2削減に貢献し、SAFの認知度向上に繋げる。
こうした取り組みをオール東京で展開することで、家庭からの廃食用油の回収ムーブメントを醸成していく。