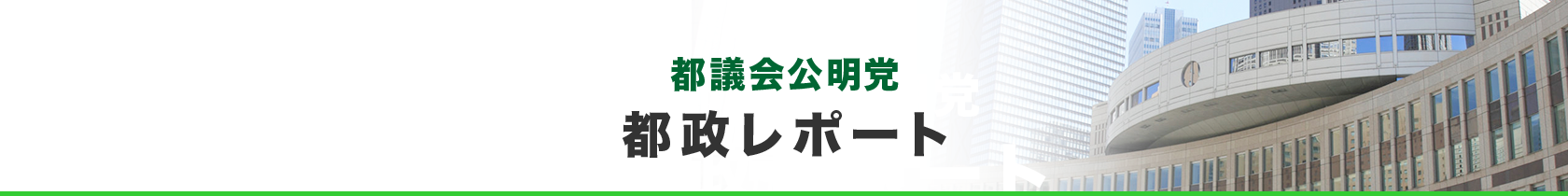防災対策
① フェーズフリーについて
【質問】
フェーズフリーとは、平時と災害時の垣根を取り払い、身の回りにあるものやサービスを日常時はもちろん、非常時にも役立てるという概念である。都は、「2050東京戦略」において、都市の強靭化や防災など、都民の安全・安心の確保に向け、災害対策を強化することとしているが、この戦略の推進にあたり、フェーズフリーの概念や考え方を取り入れ、広くこの概念を周知すべきだが、見解を伺う。
【政策企画局長】
普段使っているモノやサービスを非常時にも役立てる、いわゆるフェーズフリーの考え方は、防災対策を行う上で有効である。
これまで都は、災害時も見据えた公園の整備や、普段使っているモノを多めにストックする日常備蓄などの取り組みを促進してきた。さらに、今回策定した2050東京戦略において、災害から命を守るための備えとしてフェーズフリーの取り組みを掲げた。
今後、新たな戦略の下、災害に強い安全・安心な東京を実現していくため、こうした取り組みをホームページや防災ブック等を通じてわかりやすく発信していく。
② 避難所運営のリーダー育成について
【質問】
避難所を取り巻く状況は地域により異なるため、避難所の運営は、地域の実情に明るい住民が主体となることや女性視点での運営も重要と考える。
地域住民が主体となる適切な避難所運営体制の構築のためには、都が積極的にリーダー育成を図るべきである。都の見解を伺う。
【総務局長】
都は今般、避難所運営指針の素案を公表し、避難所は住民リーダーが中心となって、円滑に運営されることを目指すべき基準として示した。
本指針では、運営ノウハウを習得した住民リーダーの育成や、運営メンバーの4割を女性とし、正副リーダーのいずれかに女性を配置する等、区市町村が直ちに取り組むべき具体的方策をガイドラインとしてまとめている。
令和7年度は、こうした取り組みが着実に進むよう、専門家によるセミナーのほか、地域住民との避難所開設準備訓練などにより住民リーダーの育成を図り、避難所運営体制の構築を支援していく。
③ ペットの災害対策について
【質問】
近年、ペットと一緒に避難したいと考える住民ニーズが高まっており、飼い主がペットを連れて避難所まで安全に避難する「同行避難」について、飼い主はもちろんのこと、ペットを飼っていない方々も含めた地域全体の理解を深める取り組みが必要である。
ペットと一緒に避難し、ペットが避難所で飼い主以外にも受け入れられるよう、飼い主による日頃の基本的なしつけなどの備えが重要である。都は、災害への備えについて、飼い主への情報提供を進めるべきと考えるが、都の見解を伺う。
【保健医療局長】
飼い主が平時から災害に備えることができるよう、都は、ペットの身元表示の方法や備蓄品の確保、同行避難に必要なしつけや健康管理、避難所での注意点などをまとめたリーフレットを作成し、区市町村の窓口や動物病院で配布するほか、イベントやホームページを通じて、広く都民に情報提供している。
また、身近な地域で都民の相談に応じる動物愛護推進員等を対象として、災害時の同行避難等をテーマとしたシンポジウムを獣医系大学と連携して開催している。
今後、飼い主の意識の向上を更に図るため、災害への備えの重要性について普及啓発を一層推進していく。
④ ペット同伴避難への区市町村補助の創設
【質問】
避難所での混乱を防ぎ、円滑な避難生活を実現するためには、避難所でペットと飼い主が同じ場所・同じ空間で避難生活を送ることができる「同伴避難」を行えるよう、避難所でのペット受け入れ体制を強化することが不可欠である。区市町村の取り組みを都として支援すべき。また、都は避難所運営指針の素案を公表したが、避難所の環境を整えるだけでなく、訓練なども実施していくことで実効性を上げるべきと考える。あわせて都の見解を伺う。
【総務局長】
都は、全ての避難所でのペット受け入れ体制確保を支援するため、区市町村が同伴避難に必要な資機材の整備を進められるよう、令和7年度、新たな補助金を創設する。
また、今般の避難所運営指針の素案においては、区市町村が直ちに取り組む具体的方策として、同伴避難訓練の実施を掲げており、先日、板橋区との合同防災訓練では、ペット同伴避難訓練を実施した。
今後、その成果や課題をとりまとめ、区市町村に共有するとともに、更なる訓練の実施を促していくことで、同伴避難の実効性を高めていく。
朝の子供の居場所づくり
【質問】
都は、始業前の2時間を対象として、地域住民や民間事業者を活用した朝の子供の居場所づくりを行う区市町村を支援するとしている。
安心して子供を育てられる東京の実現に向け、都は、教育と福祉の分野等で連携し、各区市町村がより良い事業が行えるよう支援を進めるべきと考える。都の見解を求める。
【教育長】
授業の始まる前や夏休み等の期間に保護者が出勤をする事例は増え、そうした小学生が朝の時間を安全で安心に過ごす場所を確保することは重要である。
このため都は、令和7年度、始業前の時間に関し、地域住民や民間等の力の活用により、小学校に児童の居場所を提供する区市町村の取り組みへの支援を開始する。具体的には、子供を見守る人材の確保など、運営に必要となる経費の一部について地元自治体へ助成を行う。また、新たに開始する認証学童クラブ事業において、夏休み等に朝の時間延長を始める自治体への支援も行う。
これにより、関係局が連携し、朝の子供の居場所の確保を進める。
福祉施策
① ディスコを通じた高齢者の社会参加の推進について
【質問】
フレイルの予防には「運動」「栄養」「社会参加」が不可欠。シルバーディスコのような、高齢者の社会参加、通いの場をより広く展開し、団体や各自治体等が積極的に導入できるよう支援すべき。こうした長寿社会に向けた取り組みについて、知事の見解を求める。
※シルバーディスコ・・・70年代、80年代の音楽で、高齢者を中心にディスコの体験をする一部の自治体におけるイベント。音楽に合わせて楽しく身体を動かしながら、高齢者が交流を深める場となっている。
【知事】
都は、人生100年時代において、活力に溢れるアクティブな「Choju社会」の実現を目指し、文化・芸術・スポーツなど、高齢者の生きがいづくりや自己実現、フレイル予防につながる区市町村の取り組みを支援している。
令和6年度は、高齢者が楽しみながら体を動かすシルバーディスコや多様な教養講座を提供するシルバー大学など、様々な取り組みに対し補助を行っている。
こうした区市町村の取り組みを更に促進するため、令和7年4月に開設するオンラインプラットフォーム「100年活躍ナビ」において好事例を発信するなど、多様なニーズに合わせて高齢者の社会参加を推進していく。
② ディスコを通じた障がい者の社会参加について
【質問】
老若男女、年齢や性別を問わず、障がいやハンデを負った人たちが差別なく楽しめる「ユニバーサルディスコ」というイベントがある。外出機会が限られがちな障がい者にとって、このようなイベントが社会参加のきっかけになることは、大変意義深いことである。
障がい者の社会参加を進めていくために、このように障がい者が楽しめる取り組みを障害福祉の観点からより広く展開できるよう、文化芸術活動やレクリエーションを積極的に実施する各自治体を支援するべきと考える。都の見解を求める。
【福祉局長】
障害者の社会参加を促進するためには、文化芸術に親しみ、創作や発表等の多様な活動の機会を確保することが重要である。
そのため都は、障害者による絵画や造形などの作品を展示する美術展や、障害のある人とない人が共に歌や演奏を発表する音楽会などのイベントを開催している。また、誰もが楽しめるダンスなどのレクリエーション活動を実施する区市町村を支援している。
今後、好事例を他の区市町村に周知するなど、障害者が豊かで潤いのある生活を送ることができるよう、障害者の社会参加を一層促進していく。
職場における睡眠環境整備への支援
【質問】
短時間仮眠をサポートできる機器を職場に導入できれば、勤務時間内に従業員の健康改善や作業効率の向上などに取り組むことが可能となる。
都は、中小企業がこうした環境作りに取り組めるように、社員満足度を向上させる事業を拡充すべきと考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
仕事中に、仮眠を含めた適度な休息が従業員の仕事の能率を高めることを中小企業に普及し、社員満足につなげる後押しは重要である。
都は、ライフ・ワーク・バランスを推進するイベントにおいて、仕事の合間に仮眠をとることのできる時間帯やスペースを設けた会社を紹介している。
今後は、セミナー等で仮眠などが生産性や働きがいを高める効果を伝える。また、そのための機器の導入など職場環境の整備に関するノウハウを紹介していくとともに、こうした社員満足度向上の取り組みも支援する。
これらにより、働く方の健康確保を促進していく。
公衆浴場・銭湯クーポン事業の新展開
【質問】
コロナ禍、原油高、燃料価格の高騰で苦境を強いられていた銭湯の利用者を増やしていく持続可能な支援策として、令和4年夏から、「東京1010クーポン」の配布事業が始まっている。今後は、例えば、世界陸上やデフリンピックを応援することで、クーポンが取得できるなど、ひと工夫加えていくべきである。
この3年間の銭湯クーポン事業の総括とともに、さらなる新たな取り組みを加えて展開をすべきと考えるが、都の見解を求める。
【生活文化スポーツ局長】
都は、原油価格高騰の影響を受けた浴場を支援するため、令和4年度及び5年度に「1010クーポン」の配布を行い、若者やファミリー層などの新規利用者の開拓やリピーターの定着につながった。
さらなる利用者の増加に向け、令和6年度は、国内外の観光客を東京の銭湯に呼び込むPRキャンペーンを展開しており、その一環としてクーポンを配布している。
令和7年度は、世界中から多くの人が集まる国際スポーツ大会の開催も機に、東京の銭湯のさらなる認知度向上に向けたキャンペーンを展開していく。
文化振興施策
① 文化財の将来に向けた保存について
【質問】
馬込文士村や大田区内にある古墳群は、地域の歴史的遺産であるだけでなく、都全体の文化的資産としても重要である。
これらの中には国や都の指定となっている文化財もあり、こうした文化財が将来に確実に継承され、適切に保存が図られるよう、都として取り組むべきである。見解を伺う。
※馬込文士村・・・大正末期から昭和初期にかけて、現在の大田区の大森・馬込地域に形成された文化圏。川端康成や北原白秋など約100人もの文士や芸術家が移り住み、創作活動に励み、交流を深めたとされる。
【教育長】
文化財は、地域の歴史や文化を理解する上で都民共有の貴重な財産であり、これを確実に保存して継承していく取り組みは不可欠である。
このため都教育委員会は、貴重な文化財について、国や都で指定をした場合、その所有者による維持や修理などに要する費用の一部に助成を行ってきた。また、文化財の保存を適切に行うことができるよう、技術的な助言を実施している。最近は、近代以降の建築物を文化財指定する事例が出て、維持に係る経費が増える中、令和7年度、歴史上の様々な時代のものを幅広く含め、それらの保存等の支援について拡充を図る。
② 文化的資産を活用した魅力発信について
【質問】
文化的資産は、保存するだけでなく活用を進め、広く発信していくことが、東京の文化の多様性と深みを未来へつなげる重要な取り組みになると考えるが、都の見解を求める。
【生活文化スポーツ局長】
東京には、歴史的な建造物や史跡だけでなく、地域の伝統に根差した芸能やイベントなど多くの文化資源が存在している。
都は、こうした地域の文化資源を活用した事業などを対象に「地域芸術文化活動応援助成」を実施しており、国の史跡を舞台にしたお祭りや地域の歴史を継承したイベントなどに助成してきた。
文化資源を未来に向けて継承するとともに、その魅力を広く発信していく取り組みを支援し、芸術文化を通じた地域の活性化や地域振興を進めていく。