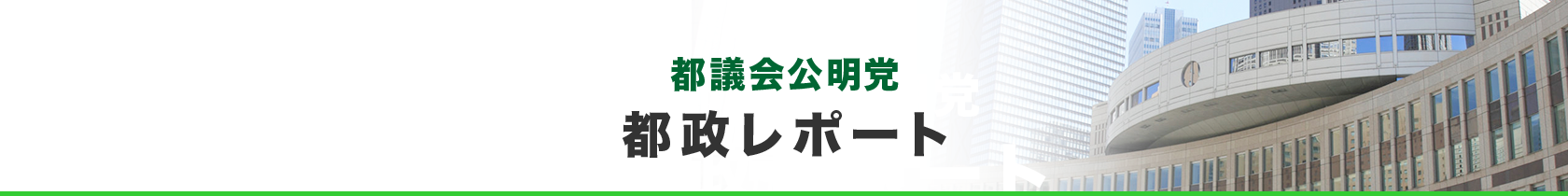持続可能な財政運営
【質問】
都税収入は、リーマンショックにより、平成21年度からの4年間、4兆円台まで落ち込んだ。令和7年度の都の一般歳出は過去最高の6.9兆円規模まで膨らんでいる一方、基金は、目的別基金と財政調整基金と合わせても1兆7,000億円しかない。いつ感染症によるパンデミックやリーマンショックのような経済恐慌が起こるか分からない現在において、これだけの基金で持続可能な財政運営ができるのか心配する声もあるが、持続可能な財政運営に対する知事の見解を伺う。
【知事】
都の歳入構造は、法人2税の占める割合が高く、景気変動の影響を受けやすい特徴を有している。加えて、都は地方交付税の不交付団体でもあり、突発的な財政需要や税収減などに備えるため、都財政にとって基金は重要である。
こうした認識の下、財政調整基金については、税収増の一部等を活用し、令和6年度最終補正予算と合わせて、約1,100億円を積み立てた。
この結果、7年度末の基金全体の残高は、1.7兆円となり、リーマンショック前と同水準を確保するほか、都債残高を着実に減少させるなど、将来を見据えた、財政基盤の確保に努めている。
今後も、予算の執行段階での歳出精査による基金の取崩し抑制や中長期を見据えた積立など、持続可能な財政運営に取り組んでいく。
家計応援計画 現役世帯の年収が増える東京へ
※都議会公明党が掲げる家計応援計画とは、1.教育負担がかからない東京へ、2.現役世帯の年収が増える東京へ、3.物価高に負けない東京へ、4.安全・安心な東京への4つの目標である。
① 持続的な賃上げのための中小企業の設備投資の後押しについて
【質問】
持続的な賃上げには、中小企業の成長が不可欠である。そのためには、設備投資により生産性等を高めて収益を増やす必要がある。賃上げ等により、従業員の生活を豊かにしていきたいと考える成長投資に意欲的な中小企業は増えており、また、設備を新しくしたいが、経費的な負担が大きいため、踏み出せない零細企業もいる。
都は、中小企業の設備投資の更なる後押しをするとともに、その効果を賃上げにつなげるために、支援の充実を図るべきと考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
都は、中小企業が生産性の向上を図るため、DXなどの最新の機械設備等を導入する取り組みへの支援において、賃上げを計画的に進める場合、手厚い助成を行っている。
令和7年度は新たに、サプライチェーンの中核を担おうとする中小企業等が賃上げを行うとともに、下請け企業との間で適正な取引を行うことを宣言した場合は、大型の設備導入にかかる助成限度額を1億円から2億円とする。
また、小規模事業者が競争力の強化を図るために機械設備を導入し、その成果を賃上げに結び付けた場合には助成率を5分の4に引き上げる。
これらにより、持続的な賃上げを後押しする。
② 中小企業のDX導入支援について
【質問】
都は、多くの中小企業がDXの取り組みを進められるよう、支援を拡充すべきと考えるが、令和7年度の取り組みについて、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
これまで都は、ダイレクトメール等によりDXの必要性を周知するほか、600社を超える企業に専門家が訪問し、企業の状況に応じたデジタルツールなどを提案するとともに、導入に係る経費を助成してきた。
令和7年度は、より多くの企業の取り組みを促すため、周知の強化を図るとともに、専門家による企業訪問の規模を1,000社に拡大する。また、システム等を導入した企業にアドバイザーを派遣し、社内の実情を踏まえた活用方法に関する助言や、デジタルに詳しい社員を育成する研修などのフォローアップを新たに行う。
これらにより、中小企業のDXを積極的に後押ししていく。
③ 社員一人一人のスキル向上支援について
【質問】
生産性向上には、DXによる業務効率化に加えて、それを進める人材の育成も必要である。また、最新のデジタル技術に適応するためのスキル向上も欠かせないし、デジタル分野に限らず、従業員が自らの成長や希望するキャリア実現のため、リスキリング等のための時間を作ることも、働きがいが高まり、生産性向上につながると考える。
都は、社員のリスキリングを推進する企業や個人を支援すべきだが、令和7年度予算における具体的な取り組みについて、見解を伺う。
【産業労働局長】
都は令和7年度、従業員がリスキリングに取り組む環境整備を行う企業への新たな支援を開始する。具体的には、専門家が企業を訪問し、リスキリング推進のための助言を行うとともに、社員がデジタル技術の習得などに必要な講座を受講するための経費の支援制度や、受講する際に休暇を取得できる制度などを導入する企業に対し、最大40万円の奨励金を支給する。
また、就職やスキルアップを目指す方への支援アプリについて、AIにより本人の希望や関心に適した職業訓練等の情報を表示するほか、キャリア開発の成功事例の紹介も増やすなど強化を図り、主体的な能力開発を後押しする。
④ 持続的な賃上げ実現に向けた知事の決意
【質問】
持続的な賃上げの実現には、企業の設備投資、DX推進などに向けた社員のリスキリング等により生み出された付加価値を人への投資に振り向けていくことが大切である。
知事のリーダーシップのもと、持続的な賃上げに様々な政策を総動員し、企業による人への投資を促していくべきだが、改めて知事の決意を伺う。
【知事】
中小企業が生産性を高め、それにより得られた付加価値が、働く方々に分配される流れを作っていく。
このため都は、業務改善により得た利益を社員に還元することの重要性を普及するとともに、賃金制度を見直す企業を支援している。
令和7年度は、新たな相談窓口を設け、賃上げを効果的に実現するための労使の関係づくりを後押しする。社員のリスキリングやキャリア形成も促す。
キャリアの幅を広げ、収入増加にもつながる副業の導入などに取り組む企業には、最大230万円の奨励金による支援も開始する。
働く人の手取り時間を増やす取り組みも含め、人への投資を促す多面的な施策を強力に推進していく。
家計応援計画 物価高に負けない東京へ 高齢者向けスマホ購入費助成
【質問】
都議会公明党は、全ての都民を対象にした物価高騰対策を実施すべきと提案し、都は、東京アプリのつながるキャンペーンで、15歳以上、1人7000ポイントを付与することを盛り込んだ令和6年度最終補正予算を提案し、成立した。
都議会公明党は、令和7年第1回定例会代表質問で、つながるキャンペーンについて、スマホを持っていない方に対する手立てを講じるべきと質問し、都からは、新たに高齢者を対象に、購入費の助成を検討していくとの答弁があった。デジタルに不慣れな高齢者もキャンペーンに参加できるよう、デジタルデバイド対策を強化すべきである。
このたびの高齢者を対象とするスマホ購入費助成の検討状況について伺う。
【デジタルサービス局長】
都は、高齢者を対象にスマホ体験会等を開催し、スマホの貸出しも行いながら、操作の習得、利便性の実感につなげてきた。今後、東京アプリの浸透を図るキャンペーンを契機に、スマホをお持ちでない高齢者に向けた支援を強化する。
令和7年度、未所有の高齢者の購入費を助成するため、高齢者施策推進区市町村包括補助の先駆的事業による支援を行う。現在、購入に係る経費の最新状況を調査するとともに、高齢者への後押しとなる効果的な仕組みを構築し、令和7年4月に行う説明会を皮切りに、区市町村と連携して迅速に実施していく。
都民生活が豊かになるDXの推進
【質問】
デジタル化の取り組みは、それ自体が目的ではなく、生活が豊かになるなど、都民の皆様がその恩恵を実感できることが重要である。これまでも都議会公明党は、都政の様々な分野において、デジタルを最大限に活用した取り組みを進めていくことを提案し、デジタルデバイド対策、こどもDXの推進などの取り組みが進んできている。令和7年第1回定例会代表質問においても、介護DXを進めるべきとの提案に対し、知事より前向きな答弁もあった。
こうした課題に対して、都民視点に立った取り組みを加速していく必要があるが、これまでの取り組みを踏まえ、宮坂副知事に、DX推進に向けた今後の展開について伺う。
【宮坂副知事】
都民が真に利便性を実感できるサービスへと更なる進化を果たすため、組織や分野を越えて横串・縦串を刺し、サービス変革を実現する政策DXにより、都民の手取り時間の増加など、新たな価値を生み出していく。利用者目線で推進しているこどもDXに続き、介護DXなど、今後様々な分野で変革を起こしていく。
また、東京アプリは、都民のデジタル体験を大きく変え、暮らしを便利にスマートにするものであり、デジタルに不慣れな方に寄り添った丁寧な対応で浸透を図り、生活を豊かにするDXを推進する。
住宅施策
① 都内マンション価格高騰の抑制策について
【質問】
都内マンション価格は、投機的な取引により高騰し続けている。この投機的な取引を抑制しない限り、マンション価格は高騰し続け、子育て世帯などは周辺県に移住せざるを得ない状況は変わらない。
都が施行した再開発事業で整備した晴海フラッグは、法人が一部の部屋を投機目的で取得するケースが相次いで見られ、不動産仲介サイトには、転売や賃貸に出されているという報道があった。
マンション価格の高止まりにもつながりかねない転売については、都としてしかるべき対策を講じるべきである。そこで、今後の都施行再開発事業におけるマンション建設の投機目的を抑制する取り組みについて、見解を伺う。
【東京都技監】
都が施行する市街地再開発事業においては、施行者である都に代わって、建物の建築・販売等を民間事業者が行う特定建築者制度を活用している。
晴海フラッグでは、申込みが高倍率となったため、状況の改善に向けた対応を特定建築者に要請した。これを受け、1名義につき申込み2戸までとするなどの対策が実施され、倍率が大幅に低下するなどの効果を確認した。
こうした取り組みもあり、現在、晴海フラッグには、7,500人を超える多くの方が居住している。今後の泉岳寺駅地区など、都が施行する市街地再開発事業においては、申込みの制限といった実効性のある対策を特定建築者に対し要請する等、必要な対応を実施していく。
② 都内マンション価格高騰に対する幅広い側面からの検討を
【質問】
神戸市は令和6年、タワーマンションとの関わりのあり方に関する有識者会議を設置し、令和7年1月に取りまとめられた報告書では、タワーマンションの立地に伴い、顕在化し得る課題のうち、特に空き部屋所有者に対する課税等に言及した。こうした神戸市の様々な検討内容は、現在、都が直面しているマンション価格の高騰の一つといわれている投機的取引の抑制効果も期待できる。
都内マンションの価格の高騰に対して、都としても、マンションの実態を十分に把握しながら、幅広い側面から検討し対応していくべきと考えるが、見解を伺う。
【住宅政策本部長】
都は現在、都内全てのマンションの戸数、階数、立地等の基礎情報に加え、空室の状況や修繕の実施状況等の把握のため、マンション実態調査を実施している。
今後、こうした調査結果を活用するとともに、国のマンション関連法改正の動向も注視しながら、マンションの適正管理や、都市機能と居住機能のバランスの取れたまちづくり、マンション価格の高騰など、マンションを取り巻く様々な課題について、住宅政策審議会等において学識経験者や業界団体等の意見を伺っていく。
安全・安心な東京へ 調節池の整備を着実に進めよ
【質問】
調節池は、豪雨に対して大きな効果を発揮することから、住民への丁寧な説明や配慮をしながら整備し、流域の安全度を高めていくことが大事である。さらに、今後は気候変動の影響などによる降雨量の増加に対応していくためにも、都議会公明党のチャレンジエイトにも掲げている調節池の整備を着実に進めていくことが重要である。
そこで、今後の調節池整備の取り組みについて、都の見解を伺う。
【建設局長】
都は、これまで27か所、総貯留量264万立米分の調節池を整備し、現在、神田川の下高井戸調節池など8か所で工事を実施している。
令和7年度は、石神井川等において3か所、合計約65万立米の調節池の本体工事に着手する。また、2035年度までの事業化目標である250万立米の達成に向け、東村山市内の柳瀬川上流部などにおいて、新たな調節池を2か所で事業化し、基本設計に着手する。
こうした調節池の整備を一層推進し、水害に強い都市東京を実現していく。
JR中央快速線のホームドアの早期整備を
【質問】
都議会公明党は令和7年第1回定例会代表質問で、チャレンジエイトの1つである駅のホームドアの設置について質問し、都からは、令和7年度から都が事業者に直接補助する制度を創設し、整備の更なる加速化を実現していくとの答弁があった。
JR東日本の中央快速線は、都民の通勤や通学など、移動の足だが、頻繁に事故や遅延が生じ都民の仕事や暮らしに大きな影響を及ぼしている。一刻も早くホームドアを設置すべきだが、都の補助制度拡充も踏まえた、JR中央快速線の今後の見通しと都の見解を伺う。
【東京都技監】
都は、令和7年2月に開催した協議会において、鉄道事業者との共同宣言として、新たな補助制度の活用や、国と連携した技術的支援により、ホームドアの整備加速に取り組んでいくことを表明した。
JR東日本は、共同宣言も踏まえ、令和7年3月に、今後4年間の計画として、都内53駅の129番線でホームドア整備を進めることを公表した。これにより、中央快速線では、中野駅から西国分寺駅までの各駅などにおいてホームドアが設置されることとなる。
都としては、整備が計画的に進むよう、引き続き、事業者の積極的な取り組みを支援していく。
防災対策
① 特別区消防団の費用弁償の増額と処遇改善を
【質問】
都議会公明党は、令和6年末、令和7年度最重点要望として、消防団の処遇改善について、知事に要望した。
昨今、物価高騰などの社会情勢が大きく変化している中にあって、特別区消防団の活動強化のため、団員に支給される費用弁償の増額など処遇改善を図るべきと考えるが、消防総監の見解を伺う。
【消防総監】
消防団の活動力を強化するためには、訓練を積み重ねるとともに処遇や施設の改善など、消防団員が活動しやすい環境をつくることが重要である。
これまでも、社会情勢の変化等を踏まえ費用弁償を増額するとともに、分団本部施設の規模、機能及び設備が十分でない施設の改築に取り組んできた。
令和7年度は、消防団員に支給する費用弁償について4,000円から4,500円に引き上げるとともに、引き続き、分団本部施設の計画的な整備を行う。
これらの取り組みにより、消防団員が活動しやすい環境づくりを推進し、消防団の活動力の強化を図っていく。
② 災害活動時におけるドローンのさらなる活用について
【質問】
都議会公明党は令和6年第2回定例会で、災害の現場においてドローンの持つ機動力や汎用性は大きな意義があることから、災害活動時におけるさらなる活用について提案し、消防庁より、ドローンの活用方策と効果的な配置について検証し、災害活動体制の強化を図るとの答弁があった。
ドローン技術の進展は目覚ましいものがあるが、昨今のドローンの技術革新の動向を踏まえ、情報収集のみならず、新たな視点で効果的に災害活動に活用すべきと考えるが、見解を伺う。
【消防総監】
ドローンは機動性に優れており、消防活動において様々な活用ができると認識している。
東京消防庁では、これまで災害現場での情報収集や物資搬送にドローンを活用しており、令和6年度は、有線給電により最大30メートルの高さの飛行が可能で、長時間・継続的に災害状況等を把握することが可能な機体を配備し、情報収集体制の強化を図った。
令和7年度は、国内の民間企業等と共同で、消火活動に活用できる新たなドローンの開発を目指す。
これらの取り組みにより、消防活動体制の強化に努める。
③ 消防活動強化へ新たなドローン機能の開発を
【質問】
新たなドローンについては、これまでにない機能を備えることで都民の安全安心を更に高められると考えるが、具体的な機能について伺う。
【消防総監】
新たなドローンは、道路狭隘地域等で、はしご車の接近が困難な中層建物の火災現場において、屋外からの消火活動を迅速に行うことを目的に開発する。
このため、消火弾を火点室に投入できるドローンや、消火用ホースを繋いだ状態で20メートル以上の高さまで飛行し、継続的に放水できるドローンの開発を目指していく。
今後、開発したドローンを効果的に活用し、消火活動体制の充実を図り、都民の安全安心を実現していく。
子ども・子育て施策 家計応援計画 教育負担がかからない東京へ
① チルドレンファースト社会実現に向けて
【質問】
都議会公明党は、チルドレンファースト実現に向けて、都立・私立高校の授業料の実質無償化や、保育料や医療費の無償化などを提案し、小池知事もこれを受け止め、積極的な取り組みをしてこられた。
そこで、チルドレンファースト社会の実現に向け、知事が令和7年度予算案に込めた思いについて、伺う。
【知事】
子供は社会にとって、かけがえのない宝である。私は、知事就任以来、未来の担い手である子供を大切に育むチルドレンファースト社会の実現に着実に取り組んできた。
国全体で少子化に歯止めがかからない中、全ての子供の健やかな育ちを支えるため、取り組みを一歩も二歩も前に進めていく。
こうした思いから、令和7年度予算案では、保育料の第1子無償化や医療費助成の所得制限撤廃、出産子育て応援事業における都独自の支援の拡充など、チルドレンファースト社会の実現に向け、施策全体で1,400億円増の約2兆円を計上している。
この予算を梃子として、未来を担う子供にとって希望に満ちあふれる東京を全力で創り上げていく。
② 医療的ケア児等に育ちの支援を
【質問】
都議会公明党の提案を受け、都は、東京型こども誰でも通園制度ともいえる多様な他者との関わりの機会の創出事業について、令和7年9月から第1子の利用料の無償化を行うこととしたが、一方で、医療的ケア等で地域の保育所等に通えない子供は、支援の対象となっていない。
こうした子供に、保護者の就労の有無にかかわらず家族以外の他者と関わる機会を提供することについて、令和6年第2回定例会で求めたが、令和7年度の都の取り組みについて伺う。
【福祉局長】
都は令和7年度、保育所等を利用できない医療的ケア児等が、他者との関わりの中で健やかに成長できるよう、保護者の就労等の有無にかかわらずベビーシッターによる保育を提供する、医療的ケア児等の育ちの支援事業を新たに開始する。
本事業では、医療的ケア児等の対応に必要な知識・経験を有する看護師や保育士等をベビーシッターとして派遣する事業者に対し、区市町村を通じて必要な経費を補助する。また、令和7年9月から、多様な他者との関わりの機会の創出事業と同様、第1子も含め利用者負担額を無償化する。
今後、区市町村に本事業の実施を積極的に働きかけ、医療的ケア児等の育ちの支援を一層充実していく。
③ とうきょう すくわくプログラムの拡充を
【質問】
都議会公明党は、乳幼児期の集団保育において培われる共感力や忍耐力といった非認知能力の重要性を繰り返し提案してきたが、都は令和6年度から、子供の豊かな育ちを応援する、とうきょう すくわくプログラムを都内全域で展開し、約1,600の幼稚園や保育所などで取り組みが見込まれているとのことで評価する。
令和7年度、より多くの園が、すくわくプログラムに取り組むことができるよう、実施規模の拡大に加えて、対象施設の拡充を図るべきと考えるが、見解を伺う。
【子供政策連携室長】
都は「とうきょう すくわくプログラム」の全域展開に向け、意欲ある多くの幼稚園や保育所等においてプログラムの取り組みが進むよう、実践に係る支援を更に充実し、子供たちの興味・関心に応じた探究活動に取り組める環境を整えていく。
具体的には、実施する園の規模を令和6年度の約1,600園から、令和7年度は2,750園に大幅に拡大する。
また、補助対象の施設について、現在の幼稚園や認可保育所、認定こども園、認証保育所等に加え、新たに企業主導型保育事業所や家庭的保育事業等を追加することで、幅広い施設での多様な体験や経験の機会を創出していく。
④ とうきょう すくわくプログラムの質の向上を
【質問】
すくわくプログラムの取り組みの輪を広げるのと同時に、質を確保していくことも重要である。
令和6年第3回定例会の都議会公明党の質問に対し、都から、優良な活動を行う園が他園に対して、探究活動の内容や方法について実践的な助言を行う仕組みのあり方について検討するとの答弁があったが、令和7年度の質向上に向けた具体的な取り組み内容を伺う。
【子供政策連携室長】
幼稚園や保育所等における質の高いプログラムの実践をサポートするため、都は令和7年度、すくわくナビゲーター園制度を創設する。
具体的には、優良な取り組みを行うナビゲーター園が、新たにプログラムに取り組む園などに対して、疑問や悩みの相談、活動充実に向けた助言などを行い、すくわくプログラム実践園全体のレベルアップを図っていく。
ナビゲーター園については、東京大学CEDEPと連携して実施するワークショップに参加し、プログラムの意義や探究活動への理解を深めた園の中から選定することで、質の高い多様な実践事例の創出につなげていく。
⑤ 不登校児童生徒の保護者へ寄り添った支援を
【質問】
都内の公立学校での不登校児童・生徒は2023年度時点で、小中高合わせて37,059人。
適切な支援が重要とした都議会公明党の提案を受け、都は、令和6年度からフリースクール等の利用者や運営費への財政支援を開始した。こうした支援に引き続き取り組むとともに、不登校の児童生徒を育てる保護者のサポートにも力を入れていく必要がある。
保護者の中には、相談先や各種サービスの情報も十分に把握できていない方も多くいる。不安や悩みを抱え苦しんでいる保護者に一層寄り添った取り組みを行うべきである。都の見解を伺う。
【子供政策連携室長】
都は令和6年度、小中学生の保護者向けに、不登校経験者による講演会や子供の接し方に関するセミナーなど不登校の理解等を深める取り組みを実施してきた。
こうした取り組みに加え、令和7年度は、保護者が相談先や各種支援策など、必要な情報を入手することができるよう、行政の不登校対策やフリースクール等の民間支援などに関する幅広い情報を一元的に掲載するポータルサイトを構築する。
さらに、フリースクール等の具体的な活動内容など、ポータルサイトだけでは得ることができない情報を直接入手することができるよう、多様な学び・居場所に関する相談会を開催する。
⑥ 都立盲学校における歩行訓練士の活用について
【質問】
視覚障がい者が日常生活及び社会生活を安全かつ自由に送るためには、この分野唯一の専門職である歩行訓練士による生活歩行訓練が不可欠である。
都議会公明党は令和6年第4回定例会代表質問で、都立盲学校4校のうち2校に歩行訓練士がいない状況であることから、都立盲学校における歩行訓練士の活用について質問し、都から、歩行訓練士の資格を持つ外部の人材の活用について検討するとの答弁があった。
都立盲学校において、歩行訓練士の力を活用することにより、教員の専門的指導力を向上させるべきと考えるが、具体的な対応を伺う。
【教育長】
視覚障害のある児童や生徒にかかる教育について、その内容を高めるため、優れた知識やノウハウを持つ専門家である歩行訓練士の力を活用することは重要である。
このため都教育委員会は、令和7年度から、都立の4つの盲学校に歩行訓練士の資格を持つ外部人材を週1回程度派遣し、現場での実技の指導に関し、助言等を行う。
また、こうした歩行訓練士が、新たに盲学校へ配属となった教員等に対し、指導の基礎にかかる4回の校内研修を実施する。さらに、様々な場所を想定し適切に歩行できるよう指導する研修を年4回担当する。
これらにより、都立の盲学校の教育のレベルの一層の向上を着実に進めていく。
⑦ 教員のメンタルヘルス対策の支援拡大について
【質問】
児童生徒の育成に携わる教員の心身にわたる健康はとても重要である。教員志望者不足への対応が求められる中で、メンタルヘルス対策は、都として全力を挙げて改善を図るべき喫緊の課題といえる。
メンタルヘルスの不調を未然防止するためには、不調の兆候を早期に発見し、初期段階から適切に支援する取り組みを、中学校や高校、特別支援学校などにも広げるべきである。加えて、取り組みの効果を、校種の違いを越えて一層高めていくべきである。あわせて、見解を求める。
【教育長】
心の病にかかることを防ぐ上で、新規採用の教員が学校現場の新たな職場環境に慣れるための後押しの充実は必要である。
都教育委員会では、公立学校からの要望に応じ、臨床心理士を年間で約12,000回派遣し、全ての職員と面談を行っている。また、公立の小学校に関し、全ての新規採用の教員に面談を行っており、令和7年度はこれを中学校や都立学校にも広げる。
さらに、小学校では、新規採用の教員について、年齢の近い先輩をつけ、相談のできる仕組みを導入しており、令和7年度は、中学校や都立学校にも取り入れる。これらの成果を集め、区市町村や各学校に共有する。
⑧ メンタルヘルスの不調で休職している教員等の復職支援の拡大を
【質問】
都議会公明党は、メンタルヘルスの不調により休職している教員等の復職支援については、発症の直後から、休職中、さらには復職の判断、復職後の支援に至るまで、一気通貫して第三者の専門家が支援していくことが重要であると指摘してきた。特に、採用間もない若手教員の不調の事例が多く、若者の教職離れに拍車をかけている。
これまで新規採用教員は、条件付採用期間に当たるなどの事情から長期休職等にカウントされることなく、復職の支援の取り組みからは漏れがちであったことから、新規採用向けの復職支援を強化すべきである。
また、都教育委員会は、全都立高校で実施する取り組みを区市町村に対しても積極的に情報提供し、ノウハウや成果も共有すべきである。
加えて、希望があれば、区市町村立の小中学校の教員向けにも、モデル的な先行実施事例として、都の復職支援の取り組みを適用拡大していくべき。あわせて見解を求める。
【教育長】
これまで都教育委員会は、公立学校の教員が心の病で休職する中、回復の進む場合、専門家が相談に乗り、職場への復帰訓練をサポートする取り組みを行ってきた。
令和7年度から、都立学校において休職の仕組みのない新規採用教員も含め、休みに入った直後から復職後まで、一貫して臨床心理士等が助言を行う伴走型の支援を開始する。
また、休職する教員等への管理職によるサポートに関し、これまで学校の要請に応じノウハウの提供を行ってきたが、今後は休職者のいる全ての都立学校に対応を行う。
これらの取り組みの成果に関し、区市町村教育委員会に対して説明会を開き、情報提供を行い、今後の小中学校における対応に役立てる。
若者施策 困難を抱える若者をサポート
① 若者たちの意見を聴く若者部会の設置について
【質問】
令和7年3月中には東京都子供・若者計画の改定版が策定され、今後、施策へと展開されていくが、施策の実施状況について、しっかりとフィードバックを行っていくべきである。そのため、若者部会を設置するなどして若者たちの意見を聴いていくべきと考えるが、見解を伺う。
【生活文化スポーツ局生活安全担当局長】
若者支援に当たっては、若者の実態や意識の変化を的確に把握し、施策に反映していく必要がある。
このため都は、計画の検討に際し、20代から30代の若者で構成する部会を青少年問題協議会に設置し、意見を聴いてきた。
今後、計画の進捗状況の把握等を行う子供・若者支援協議会に若者部会を設け、継続して意見を聴いていく。
② 若者の居場所づくりに対する支援拡大を
【質問】
東京都子供・若者計画案には、若者の問題に対応するための新たな居場所の設置支援が盛り込まれているが、若者を対象とした居場所を設置する都内の区市町村は約3割にとどまっている。
都は、この計画を梃に、地域における若者の居場所づくりに対し、一層の支援を行うべきと考えるが、見解を求める。
【生活文化スポーツ局生活安全担当局長】
都は、今回の計画策定に当たって、区市町村に若者の居場所づくりにおける課題をヒアリングしたところ、設置の前段階の実態調査から開設に至るまでの負担が大きい等の意見があった。
これを踏まえ、令和7年度から、若者の居場所を新たに設置する区市町村への支援を充実することとし、これまでの補助上限額300万円を、調査費等については600万円、開設費等については2,000万円まで引き上げる。
③ 出張型の就労支援の拡大について
【質問】
令和6年第4回定例会で、都議会公明党は、これまで女性に重点を置いて強化を図ってきた就労支援を、今後は女性に限らず広げていくべきと提案し、効果的な方策を検討するとの前向きな答弁があった。
就労が困難な様々な状況にある方が安定した生活を手に入れられるよう、都営住宅の集会所などを活用した新しい就職支援を行っていくべきと考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
生活力の向上を目指す方に対し、就労への様々な支援の選択肢を参加しやすい場所で提示し、就職やキャリアアップを後押しすることは重要である。
都は、女性を対象とした生活相談等を組み合わせた出張型の就労支援を実施しており、令和7年度、男女を問わず支援できるよう運用していく。
具体的には、都営住宅や地域の集会所を活用した、就労に困難を抱える方向けの出張相談会を区部と多摩で試行する。相談会では、男性も参加しやすい講座を設けるとともに、都営住宅の居住者向けの広報誌を活用して職業訓練の情報も提供し、スキル習得を後押しする。
若者施策 若者のチャレンジを応援する取り組み
① 奨学金返還支援の負担軽減の経済的メリットについて
【質問】
都議会公明党は、令和6年末の知事への予算要望で、子供から大人へと生活が定着するまでの移行期に当たるユース世代、特に18歳から25歳ぐらいまでの世代を対象に、思い切った支援を求め、大学生向け奨学金制度の構築を最重点項目として要望した。そして、教員や技術系公務員を対象とした奨学金返還支援が令和7年度予算案に盛り込まれた。
東京都の予算発表資料では、奨学金返還支援について、本人にとっては実質的な給付型奨学金であるとしているが、その説明については、都民目線に立って、その意味合いを分かりやすく解き明かす必要があると考える。
そこで、令和7年度予算案に計上している奨学金返還支援による負担軽減について、“経済的メリット”という観点から、具体的な数字で分かりやすい説明を求める。
【子供政策連携室長】
日本学生支援機構における4年制・無利子の大学生向け奨学金貸与スキームのうち、最も金額の大きい私立・自宅外の返済モデルによれば、大学4年間で月64,000円、総額307万2,000円を定額返還方式で借り入れた場合、返還年数は18年となり、返還初年度は原則7か月目から返還開始のため、平年度化する2年目以降の返還額は月約14,000円、年間約17万1,000円となる。
このモデルケースにおいて、奨学金返還支援制度を活用した場合、奨学金返還総額300万円を上限として、その2分の1を10年間に渡り、都が本人に代わって返還することから、年間で15万円、月当たりに換算すると約12,000円支援されることとなり、負担軽減後の本人の返還額は月約2,000円、年間約21,000円となる。
② 代理返還制度の採用で所得税が非課税に
【質問】
令和7年度予算案に計上されている奨学金返還支援の特徴の一つとして、都が本人に代わって奨学金を返還するスキームとある。「本人への直接給付」ではなく、「代理返還制度」を採用したことによる本人にとってのメリットについて見解を伺う。
【子供政策連携室長】
令和7年度創設する奨学金返還支援制度は、貸与型の奨学金を借りていた学生が、都内で勤務する教員や都市の強靭化に携わる技術系公務員になった場合、返還総額300万円を限度として、その半額を都が本人に代わって返還する仕組みであり、代理返還の手法を活用している。
代理返還の手法を活用することで、本人にとってのメリットとしては、支援額が通常の給与と明確に区分され、かつ、支援額が奨学金の返還に充てられるものであることから、税制上、支援額に係る所得税が非課税となり得るとされている。
③ 中小企業を対象とした奨学金返還支援のさらなる対象拡大を
【質問】
都議会公明党の提案で、令和4年度から行われている、中小企業を対象とした奨学金返還支援制度の募集要件を20代まで拡大したことは評価するが、転職時代の労働市場を考えると、30代の転職者も含め、より多くの若者がチャレンジできるようにすべきと考える。都の見解を伺う。
【産業労働局長】
奨学金の返還の負担を減らす支援について、ものづくり分野等の中小企業が優秀な技術人材を幅広く確保できるよう運用していくことは重要である。
都はこれまで、この支援の効果を高めるため、大学と連携したPRを行うなど、学生の利用を増やす工夫を図るとともに、採用後一定の期間、生産や営業の仕事を行う方や、卒業後に転職をする20代の若手も対象に含める見直しも行っている。
今後、労働市場の動向や中小企業の意向などを踏まえた支援の在り方を検討していく。
④ 留学支援事業は地域ごとに物価水準を考慮した制度設計を
【質問】
ユース世代の支援という点では、令和7年度予算案に海外留学に踏み出す大学生等に対する都独自の支援が盛り込まれたことも大きな1歩である。
近年、世界的に物価高が続き、急激な円高も相まって、留学費が高騰している。また、留学先によっては、費用が大きく異なることにも留意しなければならない。
事業の実施に向けては、経済的な問題で海外留学を諦めることがないよう、きめ細かく制度設計すべきと考えるが、都の見解を伺う。
【子供政策連携室長】
海外留学支援制度の創設に向けては、留学先の物価水準を考慮し、地域ごとにきめ細かく支援単価を設定する。
具体的には、物価水準に応じて、留学先の地域を3つ程度に区分し、それぞれの地域ごとに補助上限額を設定する。
区分や対象地域などの詳細は今後、具体的に検討していく。
⑤ 海外留学支援制度はより多くの学生がチャレンジできるよう工夫を
【質問】
海外留学支援制度の実施に当たっては、支援対象者を語学力のみで選ぶのではなく、意欲や主体性なども加味して、より多くの学生がチャレンジできるよう、工夫を凝らすべきと考えるが、都の見解を伺う。
【子供政策連携室長】
未来を切り拓くチャレンジ精神を重視するため、意欲ある大学生等が自ら主体的に海外大学等への留学計画を立てることを支援対象の要件とする予定であり、制度の詳細は今後検討していく。
女性活躍支援
① 女性が能力を発揮できる取り組みの推進を
【質問】
企業では、女性を採用し増やしていくことや、これまで男性がやってきた職務への女性の配置、働きやすい勤務環境の整備などに困難さを感じている状況もある。
こうした状況にあっては、新しい仕事に挑戦し、成長の機会を増やしていきたいと考える意欲ある女性が増えても、女性たちの能力の多くが埋もれてしまうこともある。
そこで、女性が能力を発揮できるよう取り組みを進めていくべきと考えるが、知事の見解を伺う。
【知事】
女性の力は、持続可能で明るい未来を切り拓く最大のエネルギー。女性が能力を生かすことができる社会を実現するためには、働き方や生き方の選択肢を増やし、活躍の場を広げることが必要だ。
都は、家庭と仕事の両立が実現しやすい環境づくりに取り組む企業への支援や、キャリアアップを目指す女性のサポート、経営者の意識改革等、幅広く取り組みを展開している。
さらに、女性が仕事を通じて自己実現できるよう、いわゆる年収の壁の突破や、男女間賃金格差の是正、性別による無意識の思い込みの払拭など、構造的課題の解決に取り組んでいく。
今後、条例の制定に向けた議論を進め、女性活躍の輪を旗印に、新たなステージへ引き上げ、東京から社会へ大きなうねりを起こしていく。
② 建設現場で働く女性の環境整備について
【質問】
男性が大多数を占める建設業界において、近年少しずつ女性が増えてきている。建設や土木の分野での女性活躍を推進するため、現場従事者が快適な環境で仕事ができるよう、中小企業の支援を強化すべきだが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
女性活躍を推進するため、職域の拡大や職場環境の改善に向けた企業の取り組みを支援することは重要である。
都は令和7年度、中小企業における女性の活躍を後押しするため、ハード、ソフト両面から取り組みの充実を図る。
具体的には、工事現場等における女性用トイレや更衣室など、職場環境の整備を支援する助成金について、移動可能な車載型の仮設トイレも助成対象とする。
また、建設等の業界の声も踏まえながら、性別を問わず働きやすい現場環境の整備について、セミナー等により事業主への意識啓発を進めるとともに、企業の先進事例の紹介も行う。
③ 年収の壁の課題解決を
【質問】
短時間労働者の収入が一定額に達するまで税や保険料が免除される年収の壁は、夫婦どちらかがフルタイムで働くことが難しい世帯を保護する一方、女性の社会進出を阻む結果をもたらしている。
年収の壁の課題解決を促進するため、パート労働者の経済的自立に向けた後押しをするとともに、企業の取り組みを支援すべきだが、都の令和7年度の取り組みを伺う。
【産業労働局長】
都は令和7年度、働く方が税や年金制度を理解した上で、希望するキャリアを選択し、生涯にわたる安定した生活を確保するためのサポートを強化する。
具体的には、パートなどで働く方や企業に対するセミナーを拡充し、年収の壁の正確な理解を促すとともに、生涯収入を可視化する独自ツールも活用しながら、働く時間を延ばす後押しを進める。
また、企業への奨励金も強化する。配偶者手当の見直しや、社会保険料の負担を和らげる仕組みづくりに対して、それぞれ30万円、どちらも実施する場合は50万円を支給し、3年間で合計3,900社の規模で支援する。
高齢者施策
① 介護職員等の居住支援特別手当事業について
【質問】
介護が必要な高齢者を支えるために、介護事業者や介護職員などを支援すべきとの都議会公明党の提案を受け、都は令和6年度から、介護職員等の居住支援特別手当事業を開始したが、事業所からの申請がなかなか進まない現状があったなどと聞いている。
居住支援特別手当について、これまでの成果と課題について伺う。
【福祉局長】
都は、令和7年度から、国が介護報酬等について必要な見直しを講じるまでの間、介護職員や介護支援専門員、障害福祉サービス等の福祉・介護職員を対象に、居住支援特別手当を支給する事業者を支援している。
これまで、介護分野では、約15,000事業所の約8割が申請している。障害分野では、介護事業所を併設する事業所で職員が兼務する場合に、介護部門でまとめて申請する事例もあり、約15,000事業所のうち、申請したのは約5割となっている。入所系のサービスでは、申請率が介護分野では約9割、障害分野では約8割である一方、両分野とも、訪問系のサービスなど小規模な事業所の申請率が低いことが課題である。
② 都内全ての事業者が居住支援特別手当事業を活用できる取り組みを
【質問】
小規模事業者の申請率が低いことが課題であるが、都内全ての事業者が活用できるように取り組んでいくべきと考える。令和7年度の取り組みについて伺う。
【福祉局長】
令和7年度は、本事業の申請に当たっての課題を把握するため、全事業者にアンケート調査を実施するとともに、小規模な事業者を中心とした未申請の事業者に対しては、プッシュ型で本事業の周知を図るほか、伴走型で申請手続をきめ細かく支援する。
また、令和6年度申請を行った事業者については、既に入力した情報の活用を可能とすることで、申請手続の負担軽減を図る。
このほか、介護事業所等への就職希望者が、就職先を選択する際の参考となるよう、都のホームページで手当を支給する事業者を公表する。
こうした取組により、本事業の更なる活用を進め、介護職員等の処遇改善に確実につなげていく。
交通施策
① 新たな地域公共交通であるデマンド交通への支援の改善を
【質問】
身近な地域交通の担い手の一つであるバスにおいて、運転手の不足から減便や路線廃止の懸念が現実のものとなっている。一方、高齢化の進展から、都内の市区町村においては、地域交通手段の確保がますます逼迫した課題として重要性を増しており、都は、都内全体の課題としてより本格的な支援に乗り出すべきである。
これまでの補助要件の枠組みを見直し、より多くの自治体にとって取り組みやすく、より多くの都民にとって利用しやすい新たな地域公共交通が育つよう、支援内容の改善を図るべきであるが、見解を伺う。
【東京都技監】
デマンド交通は、運行ダイヤをあらかじめ定めないなど、利用者のニーズに応じて柔軟に運行する手段であり、都内の導入は令和6年度で15自治体と年々増加している。
都は、地域公共交通の基本方針に基づき、新規導入時の運行経費等の一部を区市町村に補助している。
令和6年度、事業を進める上での課題やニーズを把握するため、区市町村にアンケートを実施したところ、乗降場所の確保や車両の更新費用などが必要との意見があった。
今後は、こうした地域のニーズを踏まえ、令和8年度に基本方針の改定を進めていく中で、デマンド交通などの地域公共交通の充実に向け、より幅広く区市町村を後押しする取り組みについて検討していく。
② デマンド交通の乗降場所としてのコンビニエンスストアの活用について
【質問】
都議会公明党は、令和6年の予算特別委員会で、自治体がデマンド交通を導入する際の乗降場所の確保として、駐車施設を自前で備えるコンビニエンスストアの活用が効果的であると提案し、都から前向きに取り組む旨の答弁があった。
従来からの支援に加え、デマンド交通の導入に取り組む自治体を都がより丁寧に支えていくべきと考えるが、コンビニエンスストアの活用に関するこれまでの都による支援の成果と今後の取組内容について見解を伺う。
【東京都技監】
デマンド交通の導入に当たっては、区市町村が関係者と連携を図り、地域ニーズを踏まえた乗降場所の設置等により、利用者の利便性を高めていくことが重要である。
都は、令和7年度、株式会社ローソンと新たな協定を締結するとともに、株式会社ファミリーマートとのワイドコラボ協定を活用することで連携を開始し、杉並区など3区市において、コンビニエンスストアに新たな乗降場所が設置された。
今後は、区市町村との行政連絡会を通じて活用事例を共有するなど、利便性向上に向けて官民連携の取り組みを一層推進し、地域公共交通を主体的に担う地元自治体を支援していく。
デフリンピック
① デフリンピックを通じて共生社会につながる取り組みを
【質問】
聞こえる、聞こえないの壁を越えた交流への意欲や熱意の重要性に、より多くの人が互いに気づき合える環境の創出こそが、今回のデフリンピック大会がもたらす重要なレガシーとなるべきものであり、大会本番の盛り上がりにも直結するものと考える。
都は、今後、デフリンピックへの準備を通じて、共生社会につながる取り組みを一層進めていくべきと考えるが、見解を求める。
【生活文化スポーツ局長】
都は、デフリンピックを契機に、聞こえる人も聞こえない人も一体となって楽しめるよう、手話をベースに動きで応援を伝える「サインエール」を新たに開発した。今後、スポーツイベント等で紹介し、幅広く普及していく。
また、多くの人が集まる節目のイベントにおいて、手話を交えたパフォーマンスやデフアスリートと一緒に楽しむスポーツ体験などを実施する。
大会に向け、様々な機会を捉えて、都民がろう者の文化に触れ、理解を深めるきっかけを創出していく。
② パラスポーツへの民間からの支援について
【質問】
デフリンピックを契機に、デフスポーツを含めたパラスポーツに対する民間部門からの支援の取り組みを、資金面からの貢献も含めて、より一層充実させていくべきである。見解を求める。
【生活文化スポーツ局長】
都はこれまで、企業によるパラスポーツへの支援の充実を図るため、パラアスリート雇用などの先進的な取組事例をセミナーで紹介するほか、競技団体との交流会も開催し製品提供などにつなげている。
令和7年度は、これに加え、新たにオンライン上で交流できるプラットフォームを構築し、デフスポーツを含む競技団体のニーズと企業のノウハウや製品を継続的にマッチングしていく。より多くの企業がこの仕組みを活用してパラスポーツを支援いただけるよう、今後、企業のCSR部門等に働きかけていく。
健康施策
① 働き盛り世代が運動習慣を身につけられるさらなる取り組みを
【質問】
働き盛り世代のうちから将来を見据え、より無理なく運動習慣を身に着けてもらえるよう、さらなる取り組みを進めるべきだが、見解を伺う。
【生活文化スポーツ局長】
都はこれまで、業界団体と連携した運動能力測定を様々な地域イベント等で実施してきた。
その際、測定結果を記録するアプリにより体力の評価や運動アドバイスを行い、自らの身体の状態を知ってもらうことで、運動に取り組むきっかけを提供してきた。
令和7年度は、新たに従業員のスポーツ支援に取り組む企業等と連携し、スポーツ実施率の低い働き盛り世代を対象に職場での測定を実施する。
また、区市町村が実施するアプリを活用した運動能力測定への補助を行い、都民の運動習慣の定着につなげていく。
② 企業の健康経営の推進を
【質問】
生活文化スポーツ局による体力テストアプリを活用した取り組みとの連動や、表彰制度の創設など、働き盛り世代の健康増進を強力に推し進めるため、健康経営をさらに推進していくための効果的な取り組みを展開するべきと考えるが、知事の見解を求める。
【知事】
多くの企業が集積する東京において、働く世代の健康を維持・増進するためには、職場での健康づくりが重要である。
都は、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践する健康経営に取り組む企業を増やすため、事業者団体と連携して、経営層への普及啓発などに取り組んでいる。
令和7年度は、企業が従業員の食生活や運動習慣などを定量的に把握し、継続して検証できる仕組みの構築により、健康経営の取り組みを一層促進していく。
今後、健康づくりの動機付けにつながる体力測定など、企業の好事例を広く周知するとともに、健康経営に対する意欲を更に高められるよう取り組んでいく。
③ 高齢者の健康づくりのためのデータ活用について
【質問】
令和7年度にアプリを活用した高齢者の健康づくり推進事業を開始して、区市町村を通じて、高齢者にアプリとスマートウォッチを配布し、区市町村のフレイル対策等を進めるとのこと。また、家族等の見守りや医療機関等との連携も図るとのことで、期待する。
具体的な令和7年度事業の取り組みと今後の展開について見解を伺う。
【福祉局長】
都は現在、東京都健康長寿医療センターの知見を活用し、バイタル情報や身体活動量から健康状態を把握するアプリの開発を進めており、令和7年度は、区市町村のフレイル予防事業等に参加する高齢者に本アプリを提供する。
本アプリには、高齢者自らが健康づくりに主体的に取り組めるよう、身体活動量等の変化に応じて行動変容を促すメッセージを発信する機能のほか、別居の家族等が高齢者の日々の活動状況を確認できる機能も実装する。
今後、こうした計測データをかかりつけ医等が有効に利用できる仕組みを検討するなど、本アプリの活用により、高齢者の一層の健康維持・増進に取り組んでいく。