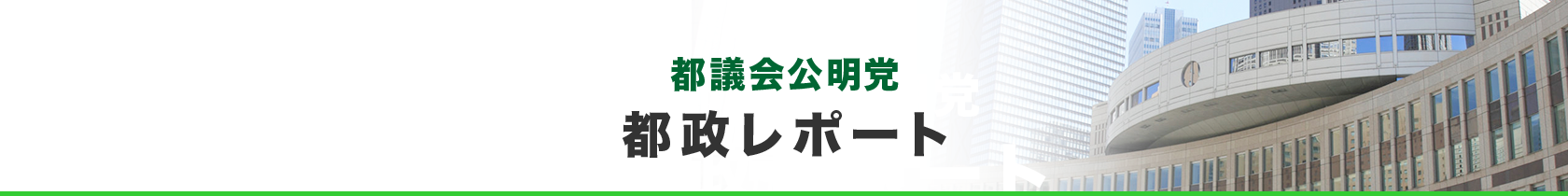防災対策
① 東部低地帯である中川、新中川における堤防の耐震対策
【質問】
東京の東部低地帯は、地盤が海水面よりも低いゼロメートル地帯が広がっている。現在、この地域に約250万人が生活しており、万が一にも堤防が決壊しないよう、地震や豪雨に耐え得る強い河川堤防でなければならない。
都は、令和3年度に東部低地帯の河川施設整備計画の第二期計画を策定し、葛飾区の中川、新中川においても堤防の耐震補強工事が切れ目なく行われているが、両河川における堤防の耐震対策の進捗状況と令和7年度の取り組みについて伺う。
【建設局長】
中川、新中川においては、東日本大震災を受けて策定した計画に基づき、堤防の変形を抑制する地盤改良などの耐震補強工事を実施している。
令和6年度末までに、中川では対策延長約15キロメートルのうち約9キロメートル、新中川では対策延長約9キロメートルのうち約5キロメートルを整備し、いずれも対策延長の約6割が完了する見込みである。
令和7年度は、中川では平和橋上流左岸など2区間で約0.7キロメートル、新中川では細田橋上下流右岸など4区間で約1キロメートルの工事に着手していく。
引き続き、令和13年度の完了に向けて耐震補強工事を着実に推進し、地域の安全性を高めていく。
② 葛飾区奥戸一丁目地区におけるスーパー堤防整備に向けた取り組み
【質問】
地道な堤防耐震対策工事とともに、さらに安全性を高めるため、川沿いの再開発と併せてスーパー堤防の整備事業が行われている。
中川においては、奥戸一丁目地区で、民間企業の大規模工場跡地の再開発をする際に、一部をスーパー堤防化すると聞いているが、既に新しい物流倉庫の再開発工事が始まっている。当該地区におけるスーパー堤防整備に向けた取り組みについて伺う。
【建設局長】
都は、地震に対する安全性と河川環境の向上を図るため、沿川の開発等と一体的にスーパー堤防の整備を進めている。
葛飾区の奥戸一丁目地区では、令和6年7月に、都と再開発事業者及び区の三者でスーパー堤防の整備に向けて施工区分等を定めた確認書を取り交わした。都は、これまでに測量などを実施してきた。
現在、事業者により物流倉庫の建築工事が進められており、令和7年度は、都において築堤工事の設計に着手するとともに、三者間で工事工程等の調整を進めていく。
引き続き、スーパー堤防の整備を推進し、安全で魅力ある水辺空間を創出していく。
③ 広域避難施設と移動手段の確保
【質問】
堤防整備に加え、万が一、大規模水害の発生が予想される場合には、都は浸水エリア外へ避難する広域避難を呼びかけている。
令和6年第2回定例会一般質問で、広域避難の実効性について質問した時には、今後、区が作成する広域避難計画のモデルを作成する等の答弁であった。
今後、当該区が計画のモデルを活用し、実効性のある広域避難計画を策定していけるよう、都として広域避難先施設を確保するとともに、当該施設までの輸送手段の確保についても積極的に取り組むなど、区を支援していく必要があると考えるが、都の見解を伺う。
【総務局長】
都は、大規模風水害時の広域避難先として、都有施設を活用することに加え、国や企業、大学等19団体と施設利用の協定を締結している。
また、都と区が運営する大規模な広域避難先施設の開設運営及び警備等の業務を円滑に実施するため、令和7年1月、警備会社と協定を締結し、運営体制を強化した。
輸送手段については、年度末に作成する広域避難計画のモデルにおいて、鉄道の増発やバスの確保等を要請する際の時期や手順を示し、円滑な避難につなげていく。
令和7年度は、広域避難先施設の確保をさらに進めていくとともに、災害時におけるバスの確保や運用の具体化を図るなど、区の計画策定を支援していく。
④ 面的な液状化対策の推進を
【質問】
能登半島地震における液状化被害を踏まえ、首都直下地震が迫る中、地震後においても自宅にとどまれるよう、都議会公明党は令和6年の予算特別委員会で、面的な液状化対策の支援を急ぐべきと質問し、検討を加速するとの答弁をいただいた。都は令和6年度、有識者会議を立ち上げて、対策工法の検討などに取り組んだこと、令和7年度予算に面的液状化対策が盛り込まれたことを評価する。
改めて、面的液状化対策を推進していくことが必要と考えるが、都の見解を求める。
【東京都技監】
首都直下地震等における被害想定では、東部低地帯など広範囲で液状化の被害が示されており、液状化対策の推進が重要である。
令和6年度は、有識者会議において、地震後においても自宅での生活継続が可能となるよう、宅地内のライフラインの機能維持に資する工法等について検討してきた。
今後は、開発事業などによる土地利用の転換を契機とした、効率的な面的液状化対策のモデル実施等について検討を進めていく。
こうした取り組みにより、東京の液状化対策を推進し、都民の安全・安心の向上を図っていく。
⑤ 区市が制度を設けていない場合の液状化対策の支援について
【質問】
面的な液状化対策は時間がかかるため、あわせて、個人への液状化対策も必要である。
都は、個人住宅への液状化対策の推進に向けて、令和6年度から新築住宅を対象とした液状化判定調査費等への補助制度を創設するなど取り組んできた。しかし、区への間接補助であり、現在、この液状化対策の補助制度を有しているのは葛飾区のみにとどまっている。そこで、区市の補助制度の有無にかかわらず、都民が対策に踏み出せるよう、使いやすい制度とすべきと考えるが、見解を伺う。
【東京都技監】
戸建て住宅等の液状化対策を進めるためには、建物所有者が液状化による被害のリスクを把握できる環境を整えることが重要である。
このため、令和7年度は、一人でも多くの方の取り組みを後押しできるよう、区市等が制度を設けていない場合においても、都が建物所有者に対して、液状化対策のための地盤調査費の2分の1、かつ最大10万円を直接助成する。
また、都民の利便性向上のため、通常必要とされている事前の申請を不要とするなど手続の簡素化を図ることで、補助を活用した取り組みを促し、戸建て住宅等の液状化対策を一層推進していく。
⑥ 既存住宅の液状化対策の工法の早期確立を
【質問】
既存住宅の液状化対策については、まず都民が安心して使える工法の確立が必要である。
都は令和6年度、都議会公明党の要望を踏まえて、令和6年末に工法の認定取得に関わる事業者へ助成を開始したところだが、申請に至った案件はまだないと聞いている。
今後、液状化対策が当たり前に行われるようにしていくため、早期に工法を確立すべきと考えるが、見解を伺う。
【東京都技監】
既存住宅の場合、工事スペースや施工方法に制約があることから、有効な工法を確立することが重要である。
このため、令和7年度は、工法の認定取得に係る事業者への補助率を4分の1から2分の1へと大幅に引き上げ、最大650万円を助成する。
今後、既存住宅向けの工法を有するコンソーシアムの構成員に対し、拡充する補助制度を活用して認定を取得するよう積極的に働き掛けていくことなどにより、既存住宅の液状化対策を推進していく。
⑦ 地下街等の浸水対策強化を
【質問】
気候変動により、豪雨の増加が懸念されている。都は、地下空間浸水対策ガイドラインを策定しているが、策定から10数年経過し、当時と比べ、降雨状況やまちの形態も大きく変わっている。そこで、気候変動による影響やまちづくりの現状を踏まえ、地下街等の浸水対策を一層強化していくべきと考えるが、都の見解を伺う。
【東京都技監】
気候変動による予想を超える豪雨への備えとして、多くの都民が利用する地下鉄や地下街等の地下空間において対策を強化していくことは重要である。
これまで都では、大規模地下街等の管理者と連携した浸水対策計画の策定、都民参加型の避難訓練などを実施してきた。
令和6年度は、他都市の地下街管理者や避難計画の主体となる地元自治体へのヒアリング、地下街の対策状況について調査した。これらを踏まえ、令和7年4月に、有識者や地元自治体等による検討委員会を立ち上げ、具体的な対策強化に向け、地下空間浸水対策ガイドラインの改定に着手していく。
⑧ 検討委員会の構成員に気候変動対策の専門家を
【質問】
令和7年4月に立ち上げる検討委員会の組成に当たっては、地下街の関係者のみならず、気候変動問題に精通した専門家も入れるべきと考えるが、見解を伺う。
【東京都技監】
地下空間浸水対策ガイドラインの改定に当たっては、近年、豪雨災害が激甚化、頻発化していることから、気候変動による影響を踏まえることが重要である。
一方、民間開発などにより、地下施設の範囲が広がることで、利用者の動線が複雑になっており、水害時の安全確保が急務である。
このため、検討委員会の構成員として、地元自治体、地下鉄事業者、河川や下水道の管理者に加え、気候変動対策の専門家などを選定し、ガイドラインの改定を進めていくこととしている。
⑨ 福祉避難所の整備促進について
【質問】
特に配慮を要する方が避難生活を送るための福祉避難所の確保は重要であるが、その確保はまだまだ十分とは言えない。そこで、区市町村による福祉避難所の整備を後押しするため、都が支援すべきと考えるが、見解を伺う。
【福祉局長】
都はこれまで、区市町村に対し、高齢者などの要配慮者の避難先となる福祉避難所の整備を働きかけるとともに、福祉避難所となる施設に対し、避難所運営を支える職員を確保するため、宿舎借上経費を補助してきた。
令和7年度は、福祉避難所を整備する区市町村に対し、必要な資器材や備蓄物資の確保、施設のバリアフリー化などに要する経費の補助を開始するほか、整備を円滑に進めるコーディネーターの配置を支援する。
こうした取り組みを通じて、区市町村における福祉避難所の確保を後押ししていく。
高齢者施策
① 認知症の早期診断・早期対応等の施策推進
【質問】
急速な高齢化に伴い、我が国の認知症のある方は増加しており、都内でも、令和7年には高齢者の6人に1人の割合で発症が見込まれている。都は、認知症のある方が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らせるよう、認知症施策を推進すべきと考えるが、知事の見解を伺う。
【知事】
認知症は誰もがなり得るものであり、私たち一人ひとりが認知症を自分事として考え、理解を深めながら、認知症のある人やその家族が地域で安心して生活できる環境を整えていくことが必要である。
そのため、都は、本人や家族の御意見も丁寧に伺いながら検討を重ね、令和7年3月、東京都の認知症施策に関する基本的・総合的な計画である認知症施策推進計画を初めて策定する。
計画には、早期の気付きや、早期診断・早期対応に向けた医療提供体制の強化、家族に寄り添った相談の実施など様々な施策を盛り込んでいく。
これらの施策を強力に推進し、認知症になってからも尊厳を保ちつつ、希望を持って暮らすことができる東京を実現していく。
② 認知症の家族介護者の負担軽減を
【質問】
認知症については、介護をする家族の負担はとりわけ大きい状況にある。都は、家族等の孤立を防ぎ、家族等も自分らしい生活ができるよう、取り組みを進めるべきである。都の見解を伺う。
【福祉局長】
都は、認知症のある人を介護する家族の負担軽減に向け、認知症疾患医療センターの専門職による相談支援や医療機関と連携して家族介護者同士の交流会等を行う区市町村への支援を行うほか、特別養護老人ホームを整備する際に、レスパイトに有効なショートステイを地域の実情に応じて併設できるよう補助している。
令和7年度は、家族会等の民間団体と連携して、家族介護の経験者がピア相談員として不安や悩みなどに寄り添いながら相談に応じ、家族介護者の心理的な孤立を防止する取り組みを新たに開始する。
こうした取り組みを通じ、家族介護者の一層の負担軽減を図っていく。
③ 認知症のある方への意思決定支援について
【質問】
認知症になっても自らの意思で社会生活を営めるよう、介護や医療の現場において、意思決定への適切な支援が行われる必要があると思うが、都の見解を求める。
【福祉局長】
都は令和7年度、介護や医療の現場において、認知症のある人の本人意思を尊重した支援や診療が広がるよう、従事者向けの研修を新たに開始する。
具体的には、介護サービス事業所の管理者や、診療所に勤務する医師・看護師等に対し、意思決定支援の重要性や具体的な実践方法等についての講義をオンライン形式で実施する。
こうした取り組みにより、介護・医療現場で意思決定支援が適切に行われるよう、さらに支援していく。
④ 区市町村における高齢者見守り体制の強化支援を
【質問】
高齢者の見守りについては、各区市町村において、民生児童委員や自治会、生活関連企業等によるネットワークづくりが進められ、個別訪問等の取り組みが行われている。
今後、単身高齢者の増加が見込まれる中、都としても、区市町村が行う高齢者の見守りの取り組みをさらに後押しすべきだが、見解を伺う。
【福祉局長】
一人暮らし高齢者等が地域で安心して暮らすためには、地域包括支援センター等が中心となり、自治会や企業など多様な主体と連携した見守り体制の構築を推進することが必要である。
都は令和7年度、見守り相談拠点における高齢者へのアウトリーチや地域の見守りネットワークの構築等を促進するため、専門職員の増配置等に取り組む区市町村への補助を拡充する。
また、都内の理美容業や銭湯など、高齢者に身近な生活関連サービス業の業界団体などと緩やかな見守りに係る協定を締結し、研修を実施するほか、見守りで気付いた情報を共有できるアプリの開発なども進め、区市町村における見守り体制の強化を更に支援していく。
⑤ スマートメーターを活用した単身高齢者の見守りサービスの拡大を
【質問】
水道局が推進するスマートメーターは、単身高齢者の見守りなど幅広い活用が見込まれている。都議会公明党は以前から、全戸展開や見守りサービスの拡大を要望しているが、スマートメーターの導入を加速させていくべきである。
今後のスマートメーター導入拡大に向けた取り組みについて伺う。また、見守りなどの機能を、より多くの都民に利用していただくことも必要と考えるが、併せて見解を伺う。
【水道局長】
水道局では、令和7年度からスマートメーターの導入を加速し、今後、4年間で、学校、公園などの公共施設や検針困難箇所等を中心に、約100万個を設置する。
特に、都営・公社住宅には全戸設置し、関係部署とも緊密に連携しながら、単身高齢者やファミリー層など、多様なお客さまのニーズを把握することで、見守り機能等の更なる改善や新たなサービスの創出につなげていく。
また、自治会等と協力しながら、スマートフォンによる設定方法や機能の説明会の開催など、きめ細かなサポートを実施し、利用者の拡大を図っていく。
今後とも、スマートメーターを通じたお客さまサービスの向上に、積極的に取り組んでいく。
環境政策
① グリーン水素製造拠点のさらなる整備を
【質問】
水素については、脱炭素に資する次世代のエネルギーとして注目している。都議会公明党は、これまで福島の水素エネルギーフィールドや、水素の活用が進む浪江町の取り組みを確認して、その有用性や課題を整理してきた。
水素は、再エネ電力から製造するグリーン水素の活用でなければ意味がなく、また、地産地消で活用されることがより効率的である。都として、都内での水素活用の普及拡大とグリーン水素の製造を同時に進めるべきと考える。
都は令和6年度、大田区京浜島で大規模なグリーン水素の製造を進めているが、将来に向けて、グリーン水素の東京での製造の取り組みを更に進めるべきと考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
今後増大が見込まれる水素需要に対応するため、その需要地である都内での水素製造を増やす取り組みは重要だ。
都は、大田区京浜島において、グリーン水素を製造する拠点の整備を進めている。令和7年度は、従来より小型で高効率な水電解装置1基を年内に先行稼働する。また、さらなる製造能力の増強に向け2基目、3基目の整備も進めていく。
これに加え、中央防波堤埋立地においても、太陽光発電を活用したグリーン水素製造施設の整備に向けた基本設計等に着手する。
こうした取り組みを通じて、都内でのグリーン水素の供給量の増加につなげていく。
② 都営バス営業所内水素ステーションの整備について
【質問】
都の水素の需要の創出に貢献しているのが都営バスである。交通局は水素を燃料とする燃料電池バスを80両導入しているが、さらなる導入車両の拡大と併せて、水素ステーションの整備も必要である。
営業所内での水素ステーションの整備状況と、燃料電池バスの今後の導入拡大の考えについて伺う。
【交通局長】
交通局では、環境負荷低減のため、燃料電池バスを国内バス事業者で最大の80両導入している。
さらなる拡大に向けて、有明自動車営業所内に整備している水素ステーションについては、既に最終検査を終え、開所に向けた準備を進めており、令和7年4月、運用を開始する予定である。
今後、令和9年度までに燃料電池バスの導入を100両まで拡大する計画であり、こうした取り組みを通じて、ゼロエミッション東京の実現に貢献していく。
③ ZEV普及促進事業について
※ZEV(ゼロ・エミッション・ビーグル)…走行中に温室効果ガスや大気汚染物質を一切排出しない乗物のこと
【質問】
都は、ゼロエミッション東京の実現に向けて、ZEVを含めた非ガソリン車の割合を100パーセントにしていくとの目標を掲げている。ZEV等の普及に向けての課題はあるが、都は、そうした課題を乗り越えるために様々な助成を行っている。
これからも普及を進めるため、ユーザーが安心して乗り続けられる環境づくりや、生産から廃棄に至るまで、ZEVのライフサイクル全体で環境負荷の低減を自動車メーカーにしっかり促していくことが重要と考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
東京の脱炭素化に向け、ZEVを利用しやすい環境整備やライフサイクルを通じた環境負荷の低減を図ることは重要である。
これまで都は、ZEVの購入支援において、自動車メーカー別のZEVの販売実績に応じて補助額を加算し、開発や販売を促してきた。
令和7年度は、これに加え、販売店への充電器の設置や、バッテリーリサイクルの取り組みなどを幅広く評価して、各メーカーの補助額に反映させることで、EVを購入した場合の補助額を最大で100万円に引き上げる。
こうした取り組みを通じて、ZEVを持続的に活用できる環境構築を後押しし、その普及を着実に進めていく。
④ EVバス・EVトラック導入促進事業について
※EV…電気自動車
【質問】
乗用車だけでなく、都内の公共交通や事業活動を支えるバス、トラックなど商用車のZEV化も必要である。商用車のZEV化を促進するため、支援を強化していくことが必要と考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
都は、EV商用車の本格導入を見据え、2035年までに都内においてEVバスを1,300台、EVトラックを7万台導入する目標を新たに掲げることとし、その普及に向けた取り組みを加速させる。
令和7年度は、車両を導入する際の補助について、国産車も含めて車種の充実が進む、様々なバスやトラックに対応できるよう、上限額を1台当たり3,500万円から4,200万円に引き上げ、事業者の負担軽減を図る。
その上で、各メーカーの販売計画に基づき、予算規模を令和6年度の約300台から約1,800台へと大幅に拡充する。
これらにより、商用車におけるZEVの導入を強力に後押ししていく。
デフリンピック
① インターネットを活用した大会PRについて
【質問】
運営組織では、大会時にインターネットによる競技配信を行う予定と聞いているが、今のうちから、そのネットを活用して魅力的なPRをすることが大切である。ネット配信だからこそ、若い世代にも共感を生む可能性もある。
ネットの利点を存分に生かしたデフリンピックの情報発信を行うべきと考えるが、都の見解を求める。
【生活文化スポーツ局長】
都は、直近の調査で大会の認知度が低かった若年層の関心を喚起するため、影響力のあるインフルエンサーなどの協力も得て大会の魅力を発信するほか、動画やバナー広告なども活用してPRしていく。
また、多くの人たちにスポーツの素晴らしさや共生社会の大切さを知ってもらうため、特設WEBサイトで、デフアスリートや社会で活躍する聴覚障害者を紹介する。インターネットを活用して、大会に関する様々な情報をタイムリーに発信していく。
② デフリンピックのマラソンの盛り上げについて
【質問】
デフリンピック東京大会では、マラソンがKK線(東京高速道路)で開催される。沿道に大勢の応援者が詰めかける一体感が不足する懸念もあり、用意周到に準備をするべきであるが、デフリンピックのマラソンの盛り上げに向けて、どのように取り組むのか、見解を求める。
【生活文化スポーツ局長】
マラソン競技の会場は、選手が都心のビルの間を駆け抜け、東京ならではの景色を肌で感じることができるKK線を活用する。
今後、関係機関と連携しながら、コースの設計や観客が選手を間近で応援できるエリアの設置など、会場運営計画を作成していく。
また、大会時のインターネットによる映像配信において、競技の状況を分かりやすく伝えるだけでなく、選手に届く応援の声を紹介する。
デフリンピックのマラソン競技を盛り上げ、より多くの人が楽しめるよう準備を進めていく。
青砥橋のバリアフリー化
【質問】
既存橋梁のバリアフリー化については、都議会公明党が折に触れて質問し、進捗を確認してきた。優先整備の6つの橋の一つである葛飾区の中川にかかる青砥橋のバリアフリー化の取り組み状況と令和7年度の予定について伺う。
【建設局長】
高齢者や障害者など、全ての人が安全で円滑に移動するためには、橋梁を含めた道路のバリアフリー化を進めていくことが重要である。
青砥橋のバリアフリー化については、令和6年度、エレベーター等の設置に向け、設計に必要な測量、地質調査を実施した。その後、令和7年3月に基本設計の契約を締結した。
令和7年度は、引き続き基本設計を進め、エレベーター等の位置や橋梁との接続方法の検討を行うとともに、地元区と維持管理などの調整を行い、青砥橋のバリアフリー化を推進していく。