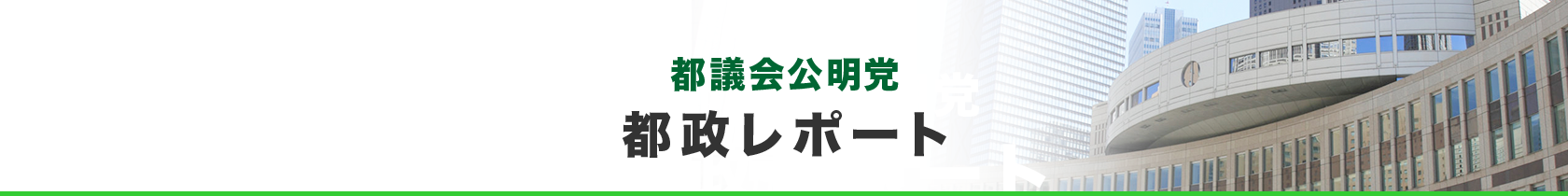若者・子ども・子育て施策
① 私立高校授業料の無償化への知事の思い
【質問】
今般、国が高校生の授業料の実質無償化に向けて踏み出したが、都は、国に先駆けて取り組んできており、令和6年度からは所得制限が撤廃された。こうした取り組みは、都議会公明党が一貫して推進してきたが、令和7年度以降、都の先駆的な取り組みがついに全国に波及していくこととなる。これまで無償化に力を注いできた知事の思いを伺う。
【知事】
教育は子供の健全な育ちを支える基盤であり、保護者の所得に関わらず、子供たちが将来にわたり安心して学べる環境を実現することが重要である。
私は、こうした考えのもと、都独自に私立高校の授業料負担の軽減に取り組み、チルドレンファーストの大きな流れを作ってきた。
子供は未来の東京を担う大切な宝であり、全ての子供が希望を持って健やかに成長できるよう、今後も子供たちの育ちを全力で支えていく。
② 国制度の就学支援金申請の必要性を保護者へ周知を
【質問】
令和7年度から国の就学支援金の所得制限が撤廃される。これにより、高校生の子供を持つ全ての保護者が就学支援金の申請が必要となるが、どのように申請すればよいかわからない保護者も多数いると思われる。保護者が混乱しないよう進めていくべきだが、見解を伺う。
【生活文化スポーツ局長】
令和7年度は、これまで対象でなかった方も含め、私立高校に通う全ての生徒が就学支援金の対象となり、こうした方々にも制度を理解し、確実に申請していただくことが必要である。具体的な申請スケジュール等については、現在国において検討中であり、都は、国からの情報収集に努めるとともに、学校と緊密に連携し、生徒・保護者への周知を適時適切に行っていく。
③ 都立高校の魅力向上へグローバル人材の育成を
【質問】
私立高校授業料の実質無償化の流れの中で、都立高校がより選ばれる高校になっていくには、その魅力向上が必要であり、その一つが、グローバル人材の育成であると考える。
ネーティブ講師のマンツーマンレッスンによるオンライン英会話事業など、英語をより一層学ぶ機会を作り、在学中に使える英語力をバランスよく育成することが重要である。令和7年度の取り組みについて見解を伺う。
【教育長】
都立高校の魅力を高める上で、その生徒に対し、将来の進学先での学習や入社後の職場において、英語を適切に使うことのできる教育を行うことは効果的である。
このため、都教育委員会は、令和7年度、15の都立高校を選び、大学での英文レポート作成や会社での英語を使う実務に対応できる力を伸ばす教育をモデル的に実施する。
具体的には、生徒の書いた数多くの英文についてAI技術を活用し速やかに添削し、その内容を踏まえ、教員がきめ細かい指導を行う。これに加え、都内の海外企業等に職場体験をする機会を設け、英語を使い仕事をする現場の雰囲気に触れ、将来の職業を考えるきっかけを提供し、学習意欲を高めるサポートを実施する。
④ より実践的な人材育成に取り組み農業の都立高校の魅力向上を
【質問】
区部3校、多摩・島しょ地域に5校設置されている農業の都立高校は、教室での座学だけでなく、農場や実習施設での体験学習が充実しており、実践的なスキルを身につけることができるとの特徴がある。
令和6年の文教委員会で、最新技術を活用した農業教育、スマート農業教育について質疑をし、次代の農業を担う若き人材育成の重要性について言及したが、東京においては、農業はもとより、食品関連産業を支える人材も求められており、その育成を担う農業の都立高校の役割はますます重要になっている。
こうした状況を踏まえ、農業の都立高校の魅力向上を図るため、より実践的な人材育成に取り組むべきと考えるが、教育長に見解を伺う。
【教育長】
都立高校で農業を学ぶにあたり、基本的な生産の技術や新たなデジタルのスキルのほか、農作物の納品先となる企業に係る知識を身に付けることは重要である。
このため、都教育委員会は、令和7年度、農業に関する技術や技能の資格検定を受ける場合に必要となる費用の2分の1を助成する取り組みを開始する。
また、ビニールハウス等の中でデジタル技術を活用し、栽培に最も適した環境を作るスマート農業を学ぶ学校を3校から5校へ拡充する。
さらに、農作物を仕入れ、商品を作る食品関連の会社で職場体験をする機会を提供し、農業をビジネスとして行う知識やノウハウの習得に向けたきっかけ作りに役立てる。
⑤ 子供や若者の自殺を防ぐため総合的な対策を進めよ
【質問】
この30年、毎年新たに2万人以上もの尊い命が自殺によって失われているのが日本社会の現状だが、昨今、とりわけ深刻なのが、子供の自殺である。小中高生の自殺者数は、2020年に400人を超えて以降、高止まりの状況が続いており、2024年は暫定値で、過去最多の527人の子どもが自殺で亡くなった。G7の中で、10代から20代の死亡原因の第1位が自殺であるのは日本だけであり、子供や若者の自殺は極めて深刻な社会問題である。そこで、都としても、総合的な自殺対策を進めるべきと考える。都の見解を求める。
【保健医療局長】
都は、若年層の自殺防止を自殺総合対策計画の重点項目に位置付け、令和6年度、こころといのちのサポートネットに子供サポートチームを設置し、学校等が把握した自殺リスクの高い子供を地域での継続的な支援につなげるなど、教育機関等との連携の強化を図っている。
また、自殺対策強化月間には、若年層が利用しやすいSNS相談の体制を拡充しており、令和7年度の強化月間はSNSの公式アカウントによる広報を強化するなど、子供や若者がより一層不安や悩みを打ち明けられるよう、相談窓口等の情報提供を充実する。
今後、福祉、教育等の関係機関と連携し、社会全体で子供や若者の自殺を防ぐ取り組みを一層推進していく。
⑥ 生徒の心身の変化を把握するシステムを小中学校にも導入を
【質問】
都議会公明党は、これまで、潜在的なリスクを抱える児童生徒を教員が見過ごすことのないよう、児童生徒の心のケアを訴えてきた。これを受けて、都教育委員会では、2020年度から、全ての都立高校で生徒の心身の変化を把握するためのシステムを導入している。学校での1人1台端末を活用し、このシステムを小中学生も利用できるようにするなど、総合的な児童生徒の心のケアを進めるべきと考えるが、都教育委員会の見解を伺う。
【教育長】
都内の子供たちが、小中学校の段階から、心の健康を意識し、その状況を教員も共有することのできる仕組みを作り上げることは重要である。
都教育委員会は、全ての都立高校生等を対象に、心の健康の状態を早期に確認できるオンラインシステム「コンディションレポート」を導入している。これにより、生徒が教員とともに健康状態を管理し、心理士等と相談のできる窓口の紹介も行っている。
令和7年度は、紹介する窓口の数を18カ所増やすとともに、この仕組みについて、区市町村との連絡会において、小中学校への導入に向け、メリットや活用事例の紹介等を行う。
⑦ 不登校などの子供たちに仮想空間を活用する自治体への支援について
【質問】
都教育委員会は、不登校などの子供たちの居場所、学びの場として、仮想空間上にバーチャル・ラーニング・プラットフォーム(VLP)の運用を開始し、現在28区市町で実施されている。VLPで朝の会に参加し、1日のリズムをつくったり、VLPで校外学習の事前授業を受け、当日は適応指導教室に通う子供たちと一緒に参加できたりした事例が報告されているが、練馬区の保護者からも、VLPを利用できないかとの声が寄せられている。そこで、VLPについて、より多くの子どもたちが利用し、充実した支援を受けられるようにすべきと考えるが、見解を伺う。
【教育長】
不登校の児童や生徒の居場所を用意するために、仮想空間を活用する工夫を進めることは効果的である。
このため、都教育委員会では、都内の28の自治体と協力し、不登校の児童等がデジタルの空間に入り、子供同士で交流できるバーチャル・ラーニング・プラットフォームを提供している。この取り組みにより、仮想空間の中で子供たちは、読書の感想を述べあうほか、手芸を一緒に学びながら友人関係も作る事例などが出ている。
こうした事例に関し、各自治体の担当者を集め、定期的に共有し、より効果の高い対応に役立てる支援をしている。
令和7年度は、これに参加する自治体に関し、練馬区を含め32に増やし、不登校の児童等のサポートの充実を図る。
⑧ 若者施策を連携推進する体制を
【質問】
都議会公明党は、子供から大人へと生活が定着するまでの移行期に当たるユース世代、特に18歳から25歳ぐらいまでの世代を対象とした支援を重視している。
この世代に対して行う新たな取り組みである奨学金返還支援制度と海外留学支援制度は、複数の局等が事業の実施を担うが、制度を充実したものとするため、各局の取り組みが統一感等を持って、迅速かつ円滑に行われるよう、関係各局の連携を推進していく体制を作るべきと考える。見解を伺う。
【総務局長】
都の重要な政策については、政策企画局が戦略などを通じて方向性を示すとともに、総合調整を行い、各所管局が施策を総合的、一体的に推進している。
その上で、奨学金返還支援や海外留学支援といった、思春期の子供から学生を含む成人への移行期を対象とする、これまでの枠組みに収まらない新たな重要施策については、政策企画局の本庁組織である子供政策連携室に新たに課を設置し、事業を所管する各局の連携を推進していく。
防災施策
① DXの活用で都道の無電柱化のさらなる加速化を
【質問】
過去の大震災では、多くの電柱が倒壊し、避難や救援活動に非常に大きな影響が生じた。無電柱化の取り組みは、首都直下地震の切迫性が高まる中、急ぎ対策を強化すべきである。都議会公明党は、令和6年の第3回定例会において、DXの活用による無電柱化事業のさらなる加速化を求めたが、都道の無電柱化の加速化について、都の見解を求める。
【建設局長】
無電柱化は、都市防災機能の強化や安全で快適な歩行空間の確保などの観点から重要な事業である。
事業の実施に当たっては、設計段階から、地下埋設物の状況を正確に把握することで、施工時の手戻りをなくし、効率化を図る必要がある。
このため、令和6年度から、地下埋設物の位置や設計の3Dデータ化を進めている。
令和7年度は、その規模を5路線から13路線へ拡大するとともに、関係事業者間の情報共有などを円滑に行うためのシステム構築の検討を深めていく。
こうしたDXの取り組みにより、無電柱化を加速していく。
② 区市町村道の無電柱化促進に向けさらなる後押しを
【質問】
東京の防災機能の強化に向けては、有事の際に避難所までの重要な道路である区市町村道の無電柱化を進めることが重要である。都道の無電柱化が進捗しても、消防署など防災拠点につながるその先の区市町村道が無電柱化されていなければ、災害時における迅速な救急活動の支障となる。
都は、無電柱化チャレンジ支援事業制度などにより、区市町村への様々な支援を実施しているが、防災上重要な区市町村道の無電柱化促進に向け、さらに区市町村を後押しすべきであると考えるが、都の見解を求める。
【建設局長】
東京全体の防災機能を強化するためには、都道のみならず、都道と区市町村道との連続した無電柱化を図ることが重要である。
このため都は、令和6年度設置した区市町村との協議体において、都道から災害拠点病院など防災上重要な拠点につながる区市町村道を優先的に整備する路線として提案し、無電柱化推進計画に位置付けるよう働きかけを行っている。こうした路線の整備促進のため、令和7年度から設計費等の補助率を2分の1から4分の3に引き上げるなど支援制度を拡充する。
今後とも、安全で強靭な都市東京の実現に向け、都内全域で無電柱化を積極的に推進していく。
③ 震災時の水道管の接合部の破損を防ぐ耐震継ぎ手化の推進を
【質問】
令和6年の能登半島地震では、耐震化が図られていない管路が破損し、その復旧に多くの時間と労力を要した。首都直下地震の対策に当たっては、水道システムの中でも都民に近く、被害が断水に直結する管路の耐震継ぎ手化をこれまで以上に強力に推進していく必要がある。首都機能が集積する都心部特有の困難な課題に適切に対応することが、工事のスピードアップ、ひいては災害時における都民の水の確保につながると考える。そこで、管路の耐震継ぎ手化に向けた見解を伺う。
【水道局長】
震災時の断水被害を軽減する、水道管路の耐震継ぎ手化をさらに加速させるためには、工事時間の制約や地下埋設物の輻輳等、高度に都市化が進展した東京の地域特性を踏まえた課題に適切に対応することが重要である。
このため、水道局では、令和7年度から掘削を伴わない工法の対象を拡大するとともに、想定外の埋設物による手戻りを防止する設計段階での試験掘りの徹底や、デジタル技術の活用等により、更なる迅速化を図っていく。
また、事業者と協働した現場見学会の開催など、事業への都民の理解を一層深める取り組みを積極的に進めていく。これらにより、管路の耐震継ぎ手化を強力に推進し、震災時における給水安定性を更に向上させていく。
④ 都の救援物資倉庫のオートメーション化で円滑な物資供給を
【質問】
都議会公明党は、立川の備蓄拠点などを視察し、当時、パレット積みすらされていない現状や、横開き荷台のトラックを横づけ駐車できない課題などを指摘してきたが、東京が直接の被害地となる大規模災害では、救援物資などの搬送に必要なドライバーの確保、荷台への荷積みに必要な人員の確保が大きな課題である。その意味では、今後はDXの力を活用するなどして、物資搬送に可能な限り人員を要しない省力化を図るべきである。また、荷積みに際しては、人の手を借りずに物資を荷積み場所まで移動させられるオートメーション化を推進するべきである。
救援物資倉庫や建て替えが予定される立川市の広域物資拠点において、最新技術力を活用するなどにより、支援物資の搬入・搬出が円滑にできるよう取り組むべきであるが、見解を伺う。
【総務局長】
発災時に、都の備蓄物資を避難者へ迅速に届けられるよう、現在、都内16か所の都備蓄倉庫に保管する物資の適正配置の検討を行っており、今後、その結果を踏まえ、各倉庫における搬出の効率性向上に取り組んでいく
また、多摩広域防災倉庫においては、令和7年度に建替えのための基本計画を策定する予定であり、その中で民間事業者や物流専門家の意見等も聴き、車両動線や必要となる設備について検討していく。
こうした取り組みを進める中で、DXの活用も含めた検討も行い、より一層円滑な物資の供給に努めていく。
⑤ 災害時の物資輸送の実効性向上を
【質問】
現在、都は、東京都トラック協会をはじめ、団体や大手企業体を相手方に、災害時の物資輸送の協定を結んでいるが、協定に基づく取り組みが、東京が被害を受けた場合であっても本当に機能するのか、発災時に物資を円滑に届けるべく、シミュレーションを通し、予め課題を洗い出し、平時から着実に解決を図るべきである。見解を伺う。
【総務局長】
都はこれまで、東京都トラック協会等の協定団体と物資輸送に係る図上訓練や、都の指示に基づくトラック搬送を行う実動訓練を継続的に実施し、官民の連携手順を確認しながら改善を図ってきた。
令和7年度は、さらに、都から物資搬送の要請を受けた協定団体が、会員の運送事業者に車両手配を行う手順の確認を行うなど、より実践的なシミュレーション訓練を実施し、災害対応の実効性を一層向上させていく。
⑥ 都立公園の防災機能強化について
【質問】
都立公園の駐車場は、公園利用者のためのものだが、災害発生時や夜間帯の活用方法については、都民全体の付加価値の向上に資するように、柔軟に対応すべきと考える。
災害時では、立地位置によっては、全国や都内各所から届く救援物資などの荷さばき場としての活用が期待される。また、太陽光発電装置や蓄電池を装備して、停電が続く場合であっても、公園内の照明や通信を保証できる整備や、上下水道施設を余裕をもって配置し、都議会公明党がかねてから主張しているフェーズフリートイレも備えておく必要がある。さらに、災害時に、駐車場にトラックの出入りが可能となるようにするべきであるが、今後の改善の見通しについて伺う。
【建設局長】
都の防災公園では、管理所の非常用電源設備や停電時でも点灯する照明、災害用トイレなどの設置を進めるとともに、地元自治体から災害廃棄物の仮置き場確保などの協力要請がある場合、救出救助活動拠点の機能との調整を図り、適切に対応している。
今後、防災機能のさらなる強化を図るため、管理所の改築等にあわせ、太陽光発電設備等の設置を進めるとともに、避難場所の運用主体である地元自治体とも調整しながら、災害用トイレの設置を拡充する。また、地元自治体から、災害時の救援物資の荷さばき場として駐車場の利用要請がある場合、大型バス駐車場へのトラックの出入りを可能とするなど、適切に対応していく。
⑦ トラックの一時待機場所として都立公園駐車場の夜間活用を
【質問】
平時であっても、夜間は空いている都立公園の駐車場を社会的な目的に沿って使わせてもらいたいとの声がある。都立舎人公園付近は、周辺道路にトラックターミナルや北足立市場などもあり、トラックの待機車両が夜から朝まで長時間駐車していることが多い状況であることから、公園駐車場の夜間のトラック向けの開放を望む声が上がっている。
都立舎人公園駐車場の有効活用に向けた進捗と、令和7年度の取り組みについて伺う。
【建設局長】
舎人公園の第一駐車場については、夜間利用が少なく、大型車両の駐車が可能な場所があることから、地域への貢献として、公園周辺の路上に滞留している大型トラックの一時的な待機場所として活用に向けた検討を進めている。
また、舎人公園では、近年、来園者の多い時期に、駐車場への入庫待ちにより、周辺道路で渋滞が発生していることから、実態を把握するため、現在、駐車場周辺の交通量調査を行っている。令和7年度は、この調査結果を踏まえ、交通管理者との協議等を進めるとともに、駐車場の改良に向けた設計を実施し、駐車場の利用方法や負担のあり方などについても、引き続き、検討を進めていく。
⑧ 女性・要配慮者のための避難所の環境改善を
【質問】
都議会公明党は、令和7年第1回定例会代表質問で、避難所の環境改善について、TKB(トイレ、キッチン、ベッド・バス)に加えて、子供の居場所の確保など、女性や子供をはじめとする多様な視点で、環境改善を進めていくことが重要であると指摘し、知事から、避難所改革に着手し、女性や子供など要配慮者への対応など防災対策を強化するとの答弁があった。今般、都は、避難所運営指針の素案を公表したが、女性、要配慮者の方も安心して避難できる避難所の環境改善に向けて取り組むべきと考えるが、見解を伺う。
【総務局長】
素案では、女性や要配慮者の運営メンバーへの参画による意見の運営への反映、特に女性については、運営メンバーの4割とし、正副リーダーのいずれかに配置することとしている。また、避難所の女性用トイレの数を男性用の3倍とすること、さらに、専門的な介護・医療までは要しない要配慮者の一次避難所として、ホテル・旅館等の活用など、区市町村が直ちに取り組むべき具体的方策をガイドラインとしてまとめている。
令和7年度は、指針の内容を丁寧に説明するとともに、専門家によるセミナーの開催等、区市町村を支援し、避難所における女性や要配慮者への対応の改善を図っていく。
⑨ 子供の視点に立った避難所改革を
【質問】
子供は、避難所の集団生活で大声を出してにぎやかに遊ぶ環境がなく、窮屈であっても、声を上げられずに我慢を強いられることで、精神状態が悪化し、PTSDなど将来へ禍根を残すおそれも指摘されている。このため、TKBに加えて、子供空間であるC(チャイルド)の視点の整備が必要である。
2050東京戦略案においても、セーフティを進めるために避難所改革が盛り込まれており、子供の視点に立った避難所改革を最優先すべきである。限られた避難所空間の中で、子供の居場所の確保や、保育士や子供のケアをサポートする人材などの配備に向けた取り組みが必要と考えるが、見解を伺う。
【総務局長】
避難所において、子供のためのスペース確保や見守る体制づくりは重要である。
そのため都は、素案においてキッズスペースや学習スペースの確保、子供の意見を聴くことによる避難所生活上のニーズの把握、保育士や保健師の人的支援など、具体的取り組みを示している。
令和7年度は、在宅避難を含めた避難者支援のあり方を検討していくこととしており、その中で、子供への配慮についても、さらに検討を深めていく。
脱炭素・エネルギー対策
① 脱炭素社会へ炭素を貯蔵する機能をもつ木材の利用を
【質問】
令和4年、脱炭素社会の実現に向けて、炭素を貯蔵する機能を持つ木材の建築物での利用を促進させるための建築基準法の改正がされたが、都においても、この機を捉え、進展を図るべきである。
都議会公明党は、令和6年の予算特別委員会において、都内で中高層木造建築物の実例を増やしていくために、木造建築物の量産に取り組んでいる北欧諸国に職員を派遣し、知見を積むべきと提案したが、先行諸国での成果を都内で生かすとともに、耐熱・耐火性の検証に真摯に取り組みながら、都市計画的な見地から責任をもって、中高層建築物におけるCO2排出量が少ない木材利用の普及を図るべきと考える。見解を伺う。
【東京都技監】
建築物における脱炭素化を促進するためには、炭素を貯蔵している木材を活用することが有効である。
木材の活用に当たっては、火災への安全性確保が重要であり、耐火性能についての認定取得や消火設備の設置に対し、都独自の支援制度を創設している。
また、令和6年12月には、先進的に取り組んでいるスウェーデンへ職員を派遣し、木材利用を促す方策や情報発信の重要性について、知見を深めてきた。
今後、新たに開設するポータルサイトを通じて、魅力的な情報発信を行うとともに、支援制度の活用を促し、中高層建築物の木材利用促進に向け取り組んでいく。
② 多摩産材を円滑に調達できる仕組みの構築を
【質問】
我が国の森林は、コスト面から有効活用の道が開かれず、林業は次第に衰退し、担い手不足から、技術継承のタイムリミットが目前の危機として差し迫っている中、数少ない豊富な国内資源の一つである国産木材の有効活用は、待ったなしの課題である。とりわけ、多摩産材の利用は、森林資源の循環を促し、都内でのカーボンニュートラルに寄与する重要な取り組みである。近年では、強度や耐火性のあるCLTなどの技術開発が進んでおり、多摩産材の利用を図るチャンスが到来している。
一方で、都内では、生産地と消費地が距離的に近いというメリットに恵まれながらも、生産と輸送のプラットフォーム化が進んでおらず、木材をタイミングよく調達したいという建築現場で働く関係者などからの声もあり、切実な課題となっている。
東京から林業経営の立て直しを図るべく、多摩産材の利用が一層進むよう、需要の創出を図るとともに、木材の利用者が円滑に調達できる仕組みを構築すべきと考えるが、令和7年度の取り組みについて、知事の見解を伺う。
【知事】
東京の森林は、木材を供給するほか、二酸化炭素の吸収を通じ、環境負荷を減らすなど都民に多くの恵みをもたらしている。この貴重な森林を守り育てるには、多摩産材を積極的に活用し、森林循環を促進していくことが重要である。
都は、大消費地である強みを生かし、日本各地の木材製品を集めた展示商談会を開き、多摩産材をはじめとする国産木材の利用拡大に取り組んでいる。多くの都民が訪れる公共施設や商業施設などでの利用を後押ししており、今後も新たな需要に応えていく。
さらに、多摩産材の流通を一層促すため、令和7年度は、伐採や利用者のニーズに関する情報をデジタル技術を活用して、リアルタイムで把握できるシステムの構築にも着手する。こうした取り組みにより、「木の都市・東京」を実現していく。
③ 低炭素化の取り組みを評価し建築主の意欲を高めよ
【質問】
都議会公明党は、令和6年の予算特別委員会で、木造建築の重要性を提唱し、都が国に先駆けて普及を進めるべきと提案し、推進を図ってきた。CO2排出量の少ない木材など低炭素建材の普及に向け、都は、建築主の意欲を高めるため、低炭素化の取り組みを積極的に評価すべきと考えるが、今後の取り組みについて見解を求める。
【環境局長】
都は、低炭素建材の利用の促進や、建設時におけるCO2排出量の把握等の取り組みの評価などを追加し、建築物の脱炭素化を促す、改正建築物環境計画書制度を令和7年4月から全国に先駆けて開始する。
具体的には、適切に保護、管理され、持続的に利用が可能な国産木材や低炭素コンクリートなど、環境に配慮された建材の積極的な活用を建築主に促していく。あわせて、こうした建材の製造時や建設時のCO2排出量を算定し、その削減に努める取り組みを誘導していく。
これらの取り組みを公表し、建築主の意欲を高めるとともに、現在、国が行っている、建設から解体までのCO2排出量の把握等に向けた制度化の検討にも貢献していく。
④ 建築の環境性能の向上へBIMの活用を
※BIM…ビルディング・インフォメーション・モデルリングの略で、建築物、個々の建材の低炭素情報などを3Dモデル化した設計ツールのこと。様々なツールと組み合わせて使うことにより、建物の見える化が可能となり、環境に配慮した設計についての建築主からの理解を得やすいというメリットがある。
【質問】
都は、環境に配慮した建築設計の手法がさらに広く浸透していくよう、幅広い年代層の設計者によるBIM活用を強く後押しをして、省エネ建築の進展につなげていくべきと考える。見解を求める。
【環境局長】
都は、環境性能の優れた建物を広げていくため、低炭素な資材の情報を設計の段階から取り入れることが可能なBIMの活用を推進してきた。
具体的には、その有効性や方法等の理解を促す専門セミナー等を計5回開催し、延べ1,000人超の参加を得た。また、設計者向けに、BIMと解析ツールを合わせた操作講習会を開催し、定員を超える応募があった。
令和7年度は、操作講習会の継続に加え、新たに、BIMを用いて環境配慮設計を行う際のシステム利用料や、専門家によるサポート費等への支援を開始する。
こうした環境配慮設計手法の普及により、建物の脱炭素化を一層推進していく。
⑤ 既存住宅の省エネ性能表示の推進を
【質問】
都内の建築物の大半は、既存の建築物であり、そうした既存建築物で、環境性能の高い建物が選択されていることにつながる評価の仕組みが大事である。
光熱費は、都民にとって大変にわかりやすい指標であり、光熱費の削減という視点から、環境性能の高い住宅を都民が選択できるようにしていけば、住宅の大多数を占める既存住宅での脱炭素化の取り組みがより進みやすくなるものと考える。特に、賃貸住宅には、都内の世帯の約半数が居住しており、賃貸住宅を選ぶ際に、光熱費などの過去の実績情報を得られやすくしていくことが効果的である。
2030年カーボンハーフの実現に向け、都は、既存の賃貸住宅について、環境性能の表示がなされた物件を増やす取り組みをしていくべきと考えるが、見解を伺う。
【環境局長】
環境性能表示の普及拡大に向け、都は、令和6年度から、断熱改修等に取り組む賃貸住宅のオーナーを対象に、改修後の光熱費の目安等が分かる省エネ性能診断・表示に係る経費を全額支援している。
令和7年度は、この取り組みを大幅に拡充し、支援規模を現在の25棟から5,000棟とするほか、助成制度の活用を働きかけるキャンペーンを展開する。
また、省エネ性能表示を活用した物件選びが広がるよう、入居者の年齢層などの属性に応じた広報を展開し、高断熱住宅の経済性や健康面の効果とともに、性能表示の内容等を広く周知していく。
賃貸オーナー、入居者双方への取り組みを通じ、環境性能の高い物件の資産価値が高まる社会環境を構築していく。
都営住宅へのカメラつきインターホンの設置
【質問】
昨今、特殊詐欺事件や闇バイトによる凶悪強盗事件の頻発化に伴い、防犯対策への関心が高まっており、支援の充実が必要である。都は、都議会公明党の要請に応え、令和7年度予算案に、個人住宅などに向けた防犯カメラなど防犯機器等購入緊急補助事業を盛り込んだ。さらに、戸建て、集合住宅、持家、賃貸など、居住形態に応じて、都民が購入しやすい補助制度にすることを提案した。都が2分の1補助としている本制度について、今後、利用者の経済状況などに応じて、さらに負担の緩和を図る区市町村の取り組みが進んでいく可能性があると考えられる一方、都営住宅において、経済的な困窮や身体的な状況などから、補助制度を利用しにくい事情を抱えた居住者もいると思われる。自治体の制度の相違により、カメラつきインターホンを設置できないといった状況が生じないよう、都が都営住宅の設置者として、踏み込んだ支援策を講じるべきである。
手や足が不自由で、玄関まで出向いて来訪者との対応が困難な身体状況にある障がいのある方や要介護状態にある方を対象に、都が責任を持ったカメラ付きインターホンの設置促進策を図るべきと考える。見解を求める。
【住宅政策本部長】
カメラ付きインターホンについては、防犯性の向上等の観点から、民間住宅では普及が進んでいるが、公営住宅では標準的な設備としては採用されていないことから、今後、国の方針等について確認しつつ、国と意見交換を行っていく。
あわせて、都としても、手や足が不自由で、玄関までの移動や対面での対応が困難な身体状況にある居住者を対象に、調査としてカメラ付きインターホンを設置して、機器仕様や設置方法、コスト等を検討し、課題を整理していく。
農業・農地施策
① 農の風景育成地区指定の推進について
※農の風景育成地区制度…比較的農地等がまとまって残る地区を指定し、地域のまちづくりと連携しながら、農のある風景の保全、育成することを目的に創設された都の制度
【質問】
近年、東京の農業を取り巻く社会情勢や都市環境は大きく変化しており、新鮮な農作物の供給や都市における緑地としての機能など、その価値はますます高まっている。
こうした状況の中、地区指定の推進が重要であると考えるが、本制度に関するこれまでの都の取り組みの状況について伺う。
【東京都技監】
都は、農地を保全し、農のある風景を将来に引き継いでいくため、平成23年度に「農の風景育成地区」制度を創設し、これまでに7地区、約366ヘクタールを指定している。
制度の運用に当たり、都は、区市町が行う候補地選定に向けた調査や農地の保全・活用等に関する計画策定、指定後3年間の普及啓発イベントやボランティア育成等について、その経費を補助するなど、区市町と連携して農の風景の育成を図っている。
さらに、令和6年度は、制度活用の好事例を伝えるシンポジウムや、区市町の担当者を対象としたワークショップを開催する等、指定拡大に向けた取り組みを進めている。
② 地区指定拡大に取り組む区市町への支援について
【質問】
令和6年の各会計決算特別委員会の都議会公明党の質疑で、指定地区内の農家から、地域の方々や地区外に向けて、制度の意義をもっとPRすべきとの声や地区内での取り組みを将来にわたり続けられるか不安があるなどの意見が寄せられていることを指摘したが、地域や農家による取り組みが、自立的に継続していくためには、取り組みの中心を担う区市町への中長期にわたる支援が必要と考えるが、見解を伺う。
【東京都技監】
都市の中で農のある風景を保全し、育成していくためには、農家による営農や周辺住民等による農への参画などが、長期的に担保されることが重要であり、これに向け、農家と住民の交流拠点の整備や、その運営体制の確保などが必要である。
このため、令和7年度には、関係局と連携し、区市町や地域の関係者に対する支援ニーズ等の調査を行うとともに、農業やまちづくりの専門家の意見も聴きながら、区市町との連携強化策について検討を行う。
今後も農の風景育成地区の指定拡大を図るとともに、地域の取り組みの活性化や、自立的な継続を促し、農のある風景を将来に引き継いでいく。
DXの推進
① 医療費助成の利便性向上へPMH接続促進を
※PMH…パブリック・メディカル・ハブの略で、国が開発した医療機関や薬局と自治体の情報連携基盤。医療費助成分野においては、このPMHに接続することで、マイナンバーカードを受給者証として利用が可能となり、都民は、紙の受給者証を持参する手間がなくなるなど、利便性が向上する。また、医療機関側での医療保険の資格情報や受給者証情報などの手動入力が不要となるなど、業務の効率化が図れるなどのメリットがある。
【質問】
医療DXの一環として、国は現在、PMHの普及に取り組んでいるが、接続に当たっては、改修に伴う費用負担がかかっており、導入に向けたハードルとなっている。また、医療機関の負担軽減に向けては、医療機関等の接続とともに、自治体側の接続も必要となるが、まずは医療費助成分野の医療機関等と東京都のシステムの接続に向けた都の取り組み状況を伺う。
【保健医療局長】
都は令和6年度、全ての医療機関や薬局に対し、PMHへの接続に向けた働きかけを行うとともに、システム改修を行う医療機関等に、国の補助に加えて都独自の支援を実施しており、令和7年3月24日時点で、870施設への補助を決定している。
都が実施する医療費助成のうち、令和6年度は、難病や小児慢性特定疾病等のシステム改修を先行して行っており、令和7年3月末には、PMHに接続した医療機関等でマイナ保険証を受給者証として利用することが可能となる。
令和7年度は、医療機関等への都独自の支援を継続するとともに、接続する医療費助成分野の拡大に着手していく。
② 区市町村の子供医療費助成のPMH接続支援を
【質問】
医療費助成については、受給対象者が多い子供分野でDXの取り組みを進めていくことが利便性を高める観点から重要である。乳幼児医療費助成などの子供医療費助成においては、区市町村を窓口としていることから、区市町村がPMHに接続していく必要があるが、都において区市町村の子供医療費のシステム改修への働き掛けを行っているものの、令和6年度中に接続を予定しているのは4市町と聞いている。
区市町村でPMHへの接続がさらに進むよう、都として支援していくべきと考えるが、令和7年度の都の取り組みについて見解を求める。
【デジタルサービス局長】
都は令和7年度、区市町村が子供医療費助成に関するシステムのPMH接続を行う場合、国の補助に加え、500万円を上限にシステム改修経費の2分の1を区市町村に補助する制度を新設する。
改修に当たっては、GovTech東京が技術支援を行うなど、区市町村の取り組みを強力に後押ししていく。
また、都内で令和6年度中に接続が予定される先行4自治体の好事例を共有するなど、説明会等を通じて、接続のメリットを伝えていく。
こうした取り組みを通じて、子育て世代の利便性向上につなげていく。
③ 介護DXで事務負担軽減とサービスの質の向上を
【質問】
介護人材の確保に向けて、デジタルを活用した生産性向上が重要である。介護ソフトなどの導入は進んできているものの、居宅介護事業者と居宅サービス事業者とのケアプランのやり取りは、郵送やファックスを使用しているケースも多いと聞く。
国は、自治体や事業所の事務負担の軽減やサービスの質を高めるため、利用者本人、区市町村、介護事業所、医療機関といった関係者が利用者に関する情報を共有、活用できるよう、介護情報基盤の整備、いわゆる介護DXを2026年度から始める方針を示している。そのため、国はオンラインで完結できる仕組みとして、ケアプランデータ連携システムを推奨しているが、導入に当たっては、導入コストやランニングコストもかかっており、支援を求める声がある。
そこで、ケアプランデータ連携システムなどの導入促進を含め、介護現場のデジタル化をさらに進めるべきと考えるが、令和7年度の都の取り組みについて見解を伺う。
【福祉局長】
都は、介護現場における生産性の向上を図るため、介護記録の作成に要するソフトウェアなどの導入経費や、デジタル機器の選定、活用方法についてのコンサルティング経費を補助している。
令和7年度は、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所とのケアプランのやりとりをオンラインで完結できる「ケアプランデータ連携システム」のさらなる普及に向け、利用状況調査や事業者の利用料負担軽減、導入時の伴走型支援などを行う区市町村に対し、最大3,000万円を新たに補助する。
こうした取り組みを通じて、介護現場における生産性向上を一層推進していく。
外国人従業員の支援に取り組む宿泊事業者のサポートを
【質問】
都は、都議会公明党の求めに応じて、2023年度から若手人材の確保や定着に向けた中小企業の取り組みを支援する助成事業を開始している。とりわけ、インバウンド需要への対応が急務となっている宿泊業の団体からは、外国人材を雇用しようと考えても、都内の家賃が高止まりしている状況では確保が困難であり、こうした事例に対応した助成事業を求める声が寄せられている。
外国人従業員の居住や生活面の支援に取り組む宿泊事業者をサポートすべきと考えるが、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
増加する外国人旅行者を着実に受け入れるため、都は、現在、中小の宿泊事業者に対し、社員の採用や育成などに必要となる経費の3分の2について300万円を上限に助成している。
令和7年度は、外国人社員向けの住宅の借上げ等に要する初期費用や、特定技能外国人を受け入れる際の生活支援を委託する場合の経費などを新たに助成対象に加える。
あわせて、こうした外国人活用を図る取り組みに必要な経費については、助成率を4分の3に引き上げ、人材確保への需要の高まりに応じた支援の拡充を図る。
これにより、宿泊事業者の取り組みを適切にサポートする。
就労支援
① 都における障害者活躍推進計画の今後の取り組みについて
【質問】
都議会公明党は、令和6年の第4回定例会において、障害者活躍推進計画の改定年度であることから、計画の改定に当たっては、必要に応じて障がい者団体などからも意見を聴取するなど、障がいを有する職員にとって働きやすい職場づくりに努めていくことを求めた。都庁における障害者活躍推進計画及び東京都教育委員会における障害者活躍推進計画が改定されるにあたり、総務局、教育庁、それぞれの今後の取り組みについて伺う。
【総務局長】
「都庁における障害者活躍推進計画」の改定に当たっては、職員へのアンケートや障がい者団体へのヒアリング等を実施し、障がいを有する職員への更なる理解の促進や活躍の場の拡充などについて意見を伺った。
これらの意見を計画に反映し、令和7年度からは、上司などに障害特性等を伝えるコミュニケーションシートの導入を進めるとともに、知的障害を有する職員がオフィスサポートセンター内で行う業務に加え、各部局に赴き、事務補助等を行う取り組みの拡大などを進めていく。
こうした取り組みにより、障がいを有する職員が、長期的・安定的に勤務できるようにするとともに、職場満足度を向上させていく。
【教育長】
障がい者が、意欲や適性に応じ、その能力を発揮できるよう、教育の職場の中で活躍のできる機会を増やす効果的な対応を進めることは重要である。
そうした取り組みに関する新たな計画を作成するに当たり、障がい者団体と意見交換を行った。その中では、学校現場の事務の一部を仕事の対象とすることや柔軟な働き方の導入等に係る要望があった。
このため、令和7年度、障がい者の働く場を増やすため、5人程度のグループで現場を巡回し、事務補助を行うほか、学校からデータ入力等の作業を請け負う仕組みを導入する。また、短時間勤務を取り入れ、時差勤務の一層の活用を進めるほか、関係局と連携し、効果的な求人の働きかけを行う。
② 政策連携団体の障害者雇用率について
【質問】
都議会公明党は、政策連携団体の障害者雇用率達成を訴えている。例えば、知的障害を有する職員が働くオフィスサポートセンターなど、都庁が培ってきたノウハウを都庁グループ全体で共有するなど、達成に向けて取り組みを強化していくべきと考えるが、見解を伺う。
【総務局長】
都は、これまでも、政策連携団体に対して、ハローワーク講師による講義や都庁のオフィスサポートセンターの取り組み等を紹介する研修会を開催するなど、障害者雇用の促進に向け、理解を促す取り組みや働きかけを行ってきた。
こうした取り組みにより、令和7年2月現在、法定雇用率の適用団体のうち、1団体を除き、雇用率を達成している
今後は、令和8年7月の法定雇用率の引き上げも見据え、政策連携団体がオフィスサポートセンターの取り組みを導入することに必要なマニュアルや募集要項等を提供し、団体からの相談にきめ細かく対応するなど、支援をより強化していく。
芸術・文化施策
① 障がいのある方の芸術文化における鑑賞サポートについて
【質問】
都議会公明党は、かねてより、障がいのある方も分け隔てなく芸術文化に親しみ、楽しめる環境をつくるために、民間によるアクセシビリティーの向上の取り組みを一層進め、障がいのある方の鑑賞の機会を充実すべきと主張してきた。これを受け、都では、令和6年度、鑑賞サポート助成を創設し、デフリンピックが開催される令和7年度の予算案においては、鑑賞サポート助成の予算を拡充している。令和6年度の成果と今後の取り組みについて見解を伺う。
【生活文化スポーツ局長】
都は、鑑賞サポートを民間にも広げるため、令和6年度助成制度を開始し、62事業で活用された。字幕や音声ガイドを通じ、展覧会や演劇などの公演を存分に楽しむことができたなど、多くの方から好評を得ている。
デフリンピックが開催される令和7年度は、大会が実施される秋を中心に、鑑賞していただける公演等を増やすため、助成規模を約3倍に拡充する。また、より多くの当事者の方々が楽しめるよう、福祉局とも連携し、鑑賞サポート付公演等の情報を積極的に発信していく。
今後、大会の開催を契機に、障がいの有無に関わらず、誰もが芸術文化を鑑賞できるよう、都内全体でアクセシビリティーの向上を一層推進していく。
② 文化財の保存・活用のためのデジタル化の取り組みについて
【質問】
文化財のデジタル化は、文化財の保存・活用の両面で有効と考える。都としても、文化財のデジタル化に向けた取り組みを進めるべきと考えるが、見解を伺う。
【教育長】
東京の様々な文化財について、デジタル技術を用い、電子データを作ることは、その保存と活用を進める上で重要な取り組みである。
これまで、都教育委員会は、文化財の指定をした近代建築物の屋内をデジタルのカメラで撮影し、あらゆる角度から鑑賞のできるコンテンツ等の作成の支援を実施した。
また、文化財について、デジタルによる画像を作り、解説を多言語で行う取り組みに係る国の支援について、区市町村を通じ、所有者に紹介している。
今後は、こうした紹介にあたり、文化財の保存と活用に関し、デジタルの力を使うメリットや優れた事例の説明を行うほか、所有者のニーズ等に関し、研究する。
デジタル化による償却資産税の申告手続の省略化
【質問】
申告期間が短く、中小事業者の負担となっているため、東京都としても、国と連携して、償却資産税の申告手続の省略化を進めていくべきであるが、見解を伺う。
【主税局長】
償却資産の申告は、法人税等と申告期限が異なっているとともに、申告までの期間が短くなっていることから、事業者の負担となっていると認識している。
これまで都は、申告・申請の電子化など、納税者のQOS向上に努めており、申告の簡素化は、事業者の事務負担軽減や適正な申告の促進による課税事務の効率化の観点から有効である。
このため、納税手続のデジタル化の進展などを踏まえ、制度を所管する国に対し、申告期限の見直しを含む制度の簡素化に向けた検討を進めるよう要望していく。
犯罪被害者への経済的支援
【質問】
被害者等に対する経済的支援について、都議会公明党は、転居費用助成金の給付要件の改善を訴え、都は、令和6年10月から給付要件を見直し、被害場所にかかわらず、対象とすることとした。犯罪被害者等の生活再建を支えるため、早期に経済的支援を拡充すべきと考えるが、知事の見解を伺う。
【知事】
犯罪の被害に遭われた方及びその御家族は、犯罪による身体的、精神的被害に加え、経済的に困難な状況に直面しており、被害直後から途切れることのない支援が必要である。こうした考え方の下、都は、見舞金や転居費用の助成等の支援を行ってきた。
とりわけ、被害者の方が、安心して住める住居を確保することは重要である。令和7年度からは、物価高騰の状況を踏まえ、転居費用助成の上限を20万円から30万円に引き上げる。制度改正前に被害に遭われた方も対象とするなど、一人ひとりに寄り添った支援を行う。
さらに、現在、被害者の方がおかれている現状やニーズを把握・分析している。その結果も踏まえ、令和7年度改定を予定している犯罪被害者等支援計画を策定する中で、国の動向等も踏まえながら、より効果的な支援の在り方について検討していく。