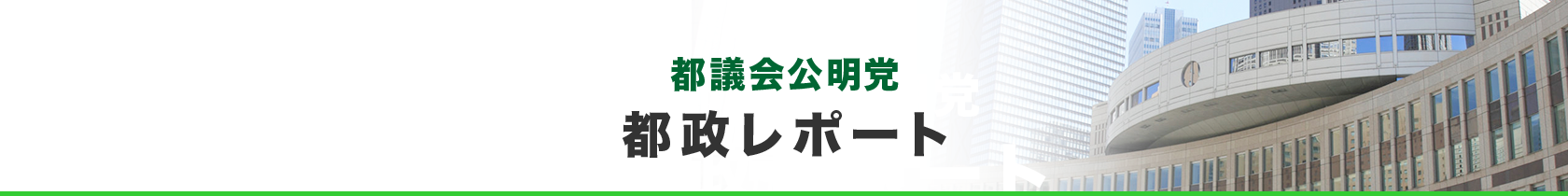有権者の信頼を損ねる大変な不祥事、違法性認識せず
参考人質疑で、公明「単なる不記載で聞き流せない」と糾弾

東京都議会は23日、政治倫理審査会を開くための条例制定を目指す第7回目の政治倫理条例検討委員会(委員長:高倉良生議員)を開いた。今回は都議会自民党の政治資金の不記載問題を巡り、収入の一部が不記載だった2019年のパーティー開催時に幹事長だった鈴木章浩議員への参考人質疑を行った。
この中で公明党の中山信行議員が「不記載に対する違法性は認識していなかったのか」と質したのに対し、鈴木氏は「認識していなかった。私の至らぬところが招いた」と謝罪。その上で、中山議員は「政治活動が目的の資金は所得税の対象外。報告がないと違法になる。単なる不記載では聞き流せない」と糾弾し、再発防止に向けた努力を質した。
中山議員、北口議員が条例案に明記すべき内容を提案

一方、この日は、有識者からの意見聴取ということで、長らく地域政治や地方自治、公共政策を専門に研究され、地方議会制度の専門家でもある大正大学の江藤俊昭教授からの意見聴取とこれに対する質疑も行われた。冒頭、江藤教授からは、「『政治とカネ』の問題が今期の議会で浮上して、都民からの不信を招いているとすれば、今期の議会の中でどういう方向性を示していくかを条例化して、今、選挙前にしっかり出すことが必要である」との見解が強調された。これに対し、公明党の北口つよし議員からは、第三者の専門家による審査会を常設化し、特定事案の審査だけでなく、継続的な研修・周知・注意喚起にも関与してもらうべきとして見解を求めたのに対し、江藤教授は、北口議員の提案に賛同するとし、事前・事後の研修も必要であるとした。条例制定後に検証と修正で内容を強化したり、議員自身が政治倫理を学ぶ研修を開催したりする必要性も強調した。
これらを踏まえて、委員会の最後に条例案の検討が行われ、中山議員が、前文、責務、政治倫理基準、附則や見直し規定等について、明記すべき事項についてそれぞれ具体的に提案し、東京都議会ならではの魂のこもった条例にしていくべきと主張した。(主な提案は、以下の通り)
▶「前文」については、政治倫理の確立が必要であるという都議会としての決意を端的に示すことと、政治資金に対する都民の不信に応えるという決意を明示すべきである。
▶「責務」については、対象者が法令遵守に加え、高い倫理的義務を自覚し、自己規律・自己規制を実施することが求められる。政治的・道義的批判を受けた場合には、事実解明と説明責任を果たすこと、審査会の求めに真撃かつ誠実に対応する義務も明記すべきである。
▶「政治倫理基準」については、審査会が政治倫理違反を認定した場合には、対象者がどの基準に違反したかを明確に整理し、評価を行った上で請求を行う必要があるため、できる限り具体的に定めることが望ましく、さらに、法改正を見越して前倒しで遵守すべきことを第二項に明記することも検討するほか、審査会の判断に柔軟性を持たせることも必要である。さらに、ハラスメントの禁止や、異議を招く恐れのある収入に関して自主的に納税義務を果たす旨を盛り込むべきであり、政治と金の問題への対応に加え、資金管理団体の透明性をどう実現するかについても踏み込んだ記載が必要である。
▶「附則」や「見直し規定」について、任期中に1度は点検することを明記すべきであり、新たな法改正や事案に対応できる柔軟な仕組みを条例に盛り込み、初回の見直しは「附則」に、定期的な見直しは「本則」に記載するのが妥当である。
▶「審査会の常設化」について、平時における通報や相談を受け付ける窓口を設置し、必要に応じて調査や審査請求へつなげる制度を整えるべきである。議長に調査を求める仕組みや、議会運営委員会への報告、審査会の判断で請求可否を議会に促す手続きも、条例で明確にしておく必要がある。