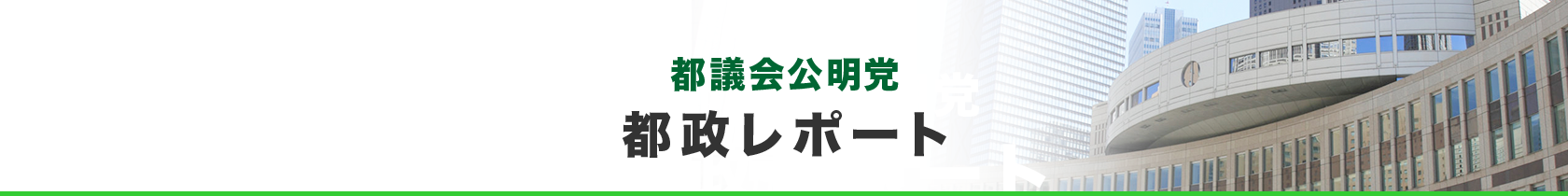多文化共生社会の形成
① 日本語指導ガイドラインの効果
【質問】
日本語を母語としない児童生徒について、都教育委員会は、学校現場における日本語指導の課題を踏まえ、令和6年度末に日本語指導のガイドラインを作成したが、作成した効果について明らかにするべきである。見解を求める。
【教育長】
外国人児童・生徒等が日本語を的確に使い社会生活を送るため、日常会話の言葉に加え、学習に必要な語学力を確実に学ぶことは重要である。
都教育委員会は、令和6年3月、そうした児童・生徒の学びを担当する教員向けに指導の進め方などを示すガイドラインを作成した。その中では、日常生活の言語能力に加え、学習で使う言語に関して、担当教員が計画的に指導する必要があるとした。
また、児童等の状況を12のモデルに分け、それを踏まえたきめ細かな指導計画の作り方等も示した。さらに、小中高校を6つ選び、ガイドラインに基づく教育をモデル的に進めた。こうした取り組みにより、各学校の日本語指導のレベルは着実に向上している。
② 多文化共生の視点で都立高校の日本語指導の拡充を
【質問】
海外における在住外国人への言語学習の体制に学んで、日本語指導は特に社会に巣立つ直前の都立高校において、日本語を母語としない生徒たちが、自らの「長所や強み」を活用し、可能性を発揮できるよう、また、多文化共生という視点で、日本語指導を拡充するべきと考える。都教育委員会の今後の取り組みについて見解を求める。
【教育長】
グローバル化が進展する東京において、子供たちが異なる文化や価値観を理解できるよう、後押しすることは重要である。
都教育委員会は、在京外国人等の生徒の受入れの枠をもつ都立高校について、現在の8校から令和7年度は更に4校増やす。新たな4校に関し、日本語を教える国家資格をもつ教員を採用して配置し、指導内容のレベルを高める。また、これらの学校から、リモートにより日本語を教えるニーズの高い高校に対し、講座も行う。さらに、在校する外国人生徒の出身地に出向き、交流を行うほか、様々な海外の文化を学ぶ講演会などを実施する。
こうした取り組みにより、ダイバーシティ教育を推進する。
③ 日本語習得の機会のない保護者に地域で学習機会の提供を
【質問】
保護者が日本語習得の機会を得られていない場合、子供が学校からのお知らせ等の通訳を担うことになるため、言語の介助という側面で、子供が親の面倒を見なければならない。
こうした言語面のヤングケアラーを生まないための取り組みは重要な視点である。
都は令和4年度から、区市町村が地域日本語教室の設置などを行う際に支援をしており、なかなか日本語学習につながることのない大人などへ学習機会の場を提供することとしているが、地域日本語教室につながる工夫を進めるべきと考える。都の見解を伺う。
【生活文化スポーツ局長】
都は、自治体が主導して地域の日本語教育の体制づくりを行う場合に、設置や運営に関する区市町村へのアドバイスや財政支援を行っており、現在14の区市で取り組みが進んでいる。
その中には、日本語学習だけでなく、生活相談や交流、生活に必要な情報を得られるなど、教室を居場所とすることで、地域の外国人が積極的に参加しているところもある。
今後、このような好事例を参考に、各区市町村の実情に合った効果的な体制づくりを支援していく。
朝の子供の居場所づくり
① 朝の子供の居場所づくり事業を始める背景と目的
【質問】
都は、多様なニーズに応えた子供の居場所づくりとして、始業前の2時間の範囲内で、小学校を活用した子供の居場所を設けるが、朝の子供の居場所づくり事業を始める背景と目的について伺う。
【教育長】
小学校の授業が始まる前に保護者が出勤をする事例は増え、そうした児童に関し、朝の時間を安全で安心に過ごす場所を確保することは重要である。
このため、都教育委員会は、令和7年度、始業前の2時間に関し、地域住民や民間等の力の活用により、小学校に児童の居場所を提供する区市町村の取り組みへの支援を開始する。具体的には、子供を見守る人材に係る経費のほか、現場で速やかに連絡を取り合うための携帯電話の導入に係る経費等の3分の2について、地元自治体へ助成する。
これにより、子供が始業前に安全で安心に過ごすための環境を作り上げる。
② 朝の子供の居場所づくり事業は教員に負担をかけない配慮を
【質問】
朝の子供の居場所づくり事業を実施するに当たっては、教員への負担をかけないように配慮することは重要なため、都は、その観点に配慮して実施されている他地域の先行事例を実施自治体に示すべきと考えるが、見解を伺う。
【教育長】
小学校の児童が始業前に過ごす環境を作る上で、民間等の力を効果的に活用し、教員への負担を増やすことがないよう取り組むことは重要である。
都教育委員会は、令和7年度から、小学校の児童に朝の居場所を提供する区市町村の取り組みを支援する中で、教員の負担の増加に結びつかないよう工夫を進める。
このため、始業前に児童が校内にいる場合、子供を見守る民間等の人材が様々な業務を幅広く担えるよう後押しする。具体的には、学校の門を開け、遊びや自習の様子を見守るほか、緊急的な対応が生じた場合の連絡対応等も実施できるよう、区市町村に働きかける。そのため、道府県の自治体の様々な事例を集め、情報提供などを進める。
③ 育児しやすい職場づくりに取り組む企業への支援を
【質問】
朝の子供の居場所づくりについては、子供やご家庭の判断で、家庭でも、行政が用意する居場所でも、どちらでも選べる体制になることが理想であるので、さらに子育てと仕事の両立支援を進めていくべきである。また、経営者に子育ての大変さを実感していただくような取り組みも進めるべきと考えるが、併せて都の見解を伺う。
【産業労働局長】
育児と仕事の両立に向け、子供と過ごす時間を十分に確保することができるよう後押しすることは重要である。
令和7年度は、育児がしやすい職場づくりへの奨励金を強化する。具体的には、子育て中の社員が、朝や夕方などの様々な場面で直面する状況を経営層等が体験し、理解する研修を行う場合に、20万円を加算する。
これらにより、社員が子供と関わる時間を確保できるよう配慮する企業の拡大に取り組んでいく。
若者のチャレンジ支援
① 若手アーティストの支援について
【質問】
「夢を抱いてチャレンジする若手アーティストを応援する東京」というメッセージにつながるよう、若手アーティストの育成支援を充実させるべきと考えるが、知事の見解を伺う。
【知事】
東京の魅力の源泉であるアートシーンを拡大させていくためには、未来を担うアーティストの新たな挑戦と持続的な活動をサポートすることが重要である。
このため、アーティストとしてのキャリアをスタートして間もない若手を対象に、企画展や舞台公演を行うための助成を実施し、その表現の場を広げる後押しをしている。
また、東京芸術文化相談サポートセンター「アートノト」では、活動資金の作り方やセルフプロデュースの方法など、活動に必要な知識やノウハウを届けるため、令和7年度、大学やアートイベントでのアウトリーチ活動を充実させていく。
こうした取り組みを多面的に展開し、東京の若きアーティストが夢に向かって羽ばたけるよう支援していく。
② 若手アーティスト等の海外での活動支援を
【質問】
将来、世界で成功するためには、早い段階から世界を視野に活動を展開していくことが重要だが、経済的な理由から海外でのオーデションチャレンジに躊躇するとの声を聞く。また、アーティストが活躍の場を広げていくためには、若手アーティストの状況をよく知り、チャンスを与えてくれる演出家やプロデューサーなどの育成も必要である。
芸術文化の担い手が海外で活躍するための支援を充実させていくべきと考えるが、見解を伺う。
【生活文化スポーツ局長】
意欲溢れる担い手の挑戦を後押しするため、都は、演出家やキュレーターなどの若手のアートマネジメント人材を対象に、海外への派遣事業を実施している。
この事業では、エディンバラ・フェスティバルやヴェネツィア・ビエンナーレなどの舞台芸術祭、美術展に幅広い人材を派遣して、最先端の舞台美術や展示手法に触れ、著名なディレクターなどと交流することで、帰国後、国際的な視点に立った創作ができるよう支援している。
令和7年度は、派遣先を映画祭などにも拡充し、世界で活躍できる東京の若い人材をさらに育てていく。
マンション防災
① 町会・マンション みんなで防災訓練事業の対象拡大を
【質問】
都は、令和6年度より、「町会・マンションみんなで防災訓練」を開始し、管理組合が組織されている分譲マンションから取り組みを始めた。地元の方より、自治会などの組織がない集合住宅でも都の様々な防災対策に申請したいとの声があり、改善に向けて、委員会等で質問を重ねてきた。
管理組合等を持たない場合でも、本事業に参加できるようにすべきである。令和7年度の変更点について見解を伺う。
【生活文化スポーツ局長】
都は、令和6年度、町会とマンションの合同防災訓練をきっかけに、災害時に備えて、地域のつながりを強化する取り組みを支援している。
本事業では、事前の打合せや住民への呼びかけなどが行える分譲マンションの管理組合を対象としていた。
令和7年度は、オーナーや住民組織がこうした活動をできる場合には、賃貸マンションや公営住宅なども連携の対象とする。
② 東京とどまるマンションの申請サポートを
【質問】
町会・マンションみんなで防災訓練に参加したマンションは、住宅政策本部の東京とどまるマンション事業の防災備蓄資器材の補助を受けることができるが、防災訓練実施前に補助金申請をするため、申請に間に合わなかったとの声があった。
東京とどまるマンション事業を多くの管理組合に利用いただくためにも、補助制度をより分かりやすく伝えたり、利用しやすくするための一層の工夫が必要と考えるが、見解を伺う。
【住宅政策本部長】
都は現在、東京とどまるマンションの登録マンションを対象に、防災備蓄資器材の補助を実施している。
実施に当たり、申請の手引等をホームページで周知したほか、令和6年11月には、申請受付に迅速かつ丁寧に対応するため、専用の補助金申請窓口を新たに設けた。
令和7年度は、東京とどまるマンションの登録申請も同じ窓口で受け付ける予定であり、登録申請から補助金申請まで相談も含め、一貫してきめ細かく対応していく。あわせて、書類の記載例や申請手順等を分かりやすく説明する動画も作成し、管理組合等が初めての補助金申請でも困らないよう、円滑な申請をサポートしていく。
③ マンション防災に係る関係局の連携について
【質問】
これまでマンション防災の事業に取り組んできた総務局、生活文化スポーツ局、住宅政策本部などの関係局での情報共有を一層進めるなど、連携をこれまで以上に深めるべきと考えるが、見解を伺う。
【総務局長】
都はこれまで、マンション防災の強化に向け、関係局で議論を重ね、連携して事業を推進してきた。具体例として、東京とどまるマンションに登録し、町会と合同で防災訓練を行う管理組合等に対し、防災備蓄資器材購入費の補助率を引き上げることで、相互の連携を促してきた。さらに、イベントやセミナー等では、各局が相互に協力して、普及啓発を行っている。
マンション防災は、住民の防災意識の向上、資器材等の確保、地域との連携を一体的に促進する視点が欠かせない。今後、情報共有など、関係局のさらなる連携強化を図ることで、実効性のある取り組みを一層推進していく。
浸水対策
① 区部における下水道の浸水対策の取り組み状況について
【質問】
都は令和5年12月、東京都豪雨対策基本方針を改定し、気候変動に対応した豪雨対策に取り組んでいる。現在、この方針に基づき、内水氾濫による被害を防止するため、ハード面の対策を推進しているが、区部における下水道の浸水対策の取り組み状況について伺う。
【下水道局長】
下水道局では、時間75ミリ降雨を目標整備水準とし、くぼ地や坂下など浸水の危険性が高い67地区を重点化し、施設整備を進めている。
重点化した67地区のうち、令和5年度までに、28地区で事業が完了し、20地区で工事に着手しており、19地区で設計を実施している。
令和6年度は、事業中の20地区のうち、文京区千石、豊島区南大塚地区での対策が完了する。
② 重点地区における取り組みの推進を
【質問】
浸水被害を早期に軽減するため、現在、事業に取り組んでいる重点地区の対策を一層推進するべきと考えるが、令和7年度の取り組みについて伺う。
【下水道局長】
令和7年度は、平成21年度から事業を進めてきた足立区千住地区で、千住関屋ポンプ所を稼働させるなど2地区で対策を完了させる。
また、新たに板橋区西台、徳丸地区において、排水能力を増強する下水道管の整備に着手する。
さらに、一部完成した施設を暫定的に貯留施設として稼働するなどの工夫により、早期に整備効果を発揮させる取り組みを進めていく。
これらの取り組みを推進し、安全・安心の確保に積極的に取り組んでいく。
高齢者等に対する地域の見守り活動の強化
【質問】
高齢者や弱者を狙った闇バイト強盗や特殊詐欺が各地で発生しているが、地域の見守り活動を強化することで、防犯効果がさらに発揮されると考える。
日常的に高齢者の方々と直接接する事業者の協力を得て、顔を合わせて声を掛け合う見守り活動を強化するべきである。そこで、地域を巡回する事業者にもご協力いただき、防犯体制を強化していくべきと考えるが、見解を伺う。
【生活文化スポーツ局生活安全担当局長】
都では、地域を巡回する民間事業者等に、高齢者への声掛けなど、まちの防犯活動に協力してもらう、ながら見守り連携事業を進めており、現在、35の事業者等と協働している。
連携事業者等には、適宜、不審者情報等を共有するほか、令和6年末には、いわゆる闇バイトに関する啓発資料を配布するなど、効果的な活動を支援している。
さらに、令和7年度は、個人宅へ定期的に訪問する連携事業者等を中心に、都が新たに開始する住宅向け防犯カメラ等の購入・設置の緊急補助事業に関する情報の発信についても協力を求めていく。
デフリンピック
① ボランティアの活躍の場の拡大について
【質問】
大会開催に当たっては、ボランティアの方々に、聴覚の有無という壁を越えて、選手と観客の一体感を高める担い手として活躍できるよう準備を進めるべき。また、ボランティアの抽選に漏れた方々にも、大会の盛り上げを担っていただけるよう工夫すべき。さらに、大会後もデフスポーツのサポーターなどとして活躍いただけるよう取り組むべき。見解を伺う。
【生活文化スポーツ局長】
運営に携わるボランティアは、聞こえる人・聞こえない人が一体となって大会をつくり上げる上で重要な役割を果たす。このため、選手や観客に寄り添ったサポートができるよう、ろう者の文化やタブレットを使ったコミュニケーションなどを学ぶ研修を実施する。
当選しなかった方についても、引き続き大会を応援してもらうため、大会情報を定期的に提供するほか、会場に足を運んでもらえるような企画を今後検討していく。
さらに、今回の応募を機に、継続的なボランティア活動につながるよう、ボランティアレガシーネットワークや障スポ&サポートへの登録を全員に呼びかけていく。
② 競技の臨場感を体感できる先進機器の活用を
【質問】
先進機器を積極的に活用して、聴覚の有無を越えた一体感の創出が大きく前進する大会とすべきと考えるが、見解を求める。
【生活文化スポーツ局長】
デフリンピックでは、会場の一体感を創出するため、聞こえる人も聞こえない人も競技の臨場感を体感できるよう、デジタル技術を活用することとしている。
先般実施した「みるカフェ」では、音を振動で感じる機器を来場者に体験してもらった。また、大会時に卓球競技が行われる会場で、ラリー音を場内のビジョンに文字で表示する取り組みも行った。
今後、関連イベントのほか、競技大会など様々な場面でこうした技術の実証を積み重ね、大会本番に向けて準備を進めていく。
住宅政策
【質問】
アフォーダブル住宅が一部の地域だけではなく、ニーズの高い地域に整備されるよう取り組んでいくべきと考えるが、見解を伺う。
【スタートアップ・国際金融都市戦略室長】
令和7年度、都が組成するファンドは、アフォーダブル住宅の供給を先導的に進めようとする事業者の取り組みを支援することで、民間での供給の促進につなげていくものであり、対象地域は都内全域としている。
今後、民間事業者から、供給する住宅の種類、想定する家賃水準と引下げの方策、供給予定戸数や対象地域などを含めた事業提案を募り、審査を通じて優れた運営事業者を複数選定し、中古ビルや空き家の活用など、創意工夫を生かした多様な住宅の供給を進める。住宅供給状況について適時適切に公表するなど、ファンドの成果等を共有し、民間主体の供給機運の醸成につなげることで、子育て世帯等が住みやすい環境の形成に取り組んでいく。
都営地下鉄の子ども連れの利便性向上
【質問】
都営地下鉄において、トイレに子供用の補助便座がなくて困ったとの声があった。子ども連れでの外出をしやすくするための取り組みを充実させるべきであるが、見解を伺う。
【交通局長】
都営地下鉄ではこれまで、車両への子育て応援スペースの導入、駅トイレへのベビーチェアやベビーシートの設置など、子育てを支援する様々な取り組みを行ってきた。
加えて、赤ちゃんや小さなお子様とのお出かけをサポートする、こどもスマイルスポットを大江戸線上野御徒町駅など3駅に展開し、育児用品自動販売機の設置や、ベビーカーレンタルサービスの提供などを行っている。
今後とも、他事業者の事例等も参考にしながら、お子様連れのお客様により安心してご利用いただける環境づくりに努めていく。
町会施策
① 町会・自治会活動の参加率向上を政策目標とした趣旨と背景
【質問】
町会、自治会のコミュニティの力は、今後の東京、日本に伝え残さなければならない文化である。都は、2050東京戦略の中で、町会・自治会活動への参加率の向上を政策目標に設定しているが、この目標を設定した趣旨と背景について、見解を求める。
【生活文化スポーツ局長】
令和6年に実施した町会・自治会活動に関する調査では、加入者のうち、活動に参加しているのは約4割であった。
町会・自治会活動の持続や活性化には、加入者の主体的な活動の促進が必要であるため、活動への参加率を目標として設定した。
② 町会・自治会加入促進事業には異なる課題を持った自治体の選出を
【質問】
都は令和7年度、区市町村と実施する町会・自治会加入促進事業に取り組むとしているが、加入促進に取り組む上での課題は、それぞれの地域の特徴に応じて異なっている。
そこで、本事業の実施に際しては、異なる課題を持った自治体が選出され、それぞれに応じた加入促進策が示されていくべきと考えるが、見解を求める。
【生活文化スポーツ局長】
本事業は、区市町村から、町会・自治会の加入促進につながる共同事業の提案を受けて、他の自治体にも展開できる好事例の創出を目指すものである。
事業の採択は、地域の特性や課題を踏まえた提案か、高い効果が期待できるかなどの視点から行う。
③ 地域とつながる若者フォーラム事業について
【質問】
都は令和7年度、都民提案事業である地域とつながる若者フォーラム事業に取り組むが、フォーラムに参加した若者が、町会に参加してみよう等と思っていただくための工夫が必要である。
そこで、若者フォーラムを開催する際は、若い世代と町会・自治会関係者との交流を図るとともに、フォーラムの成果を都内の町会・自治会に還元していくべきと考えるが、見解を求める。
【生活文化スポーツ局長】
令和7年度開催するフォーラムには、若い世代だけでなく町会・自治会の関係者や有識者などにも参加いただく。
若者の側から地域活動に気軽に参加したくなるアイデアを発表してもらい、意見交換を行うなど、双方にとって有意義なものとする。
フォーラムの結果は、ホームページ等で公表し、区市町村や町会・自治会の関係者などとも共有する。
東京都教育支援機構(TEPRO)の人材バンク機能
【質問】
都は令和7年度、人材バンク機能の充実に向けた取り組みとして、TEPROの人材バンクシステムにAIを活用していくとのことだが、AIの活用を進める際も、丁寧なマッチングが重要であると考える。見解を求める。
【教育長】
TEPROにおいて、公立学校と教員のサポートを希望する人材を円滑にマッチングする仕組みとして人材バンクシステムを導入している。これにより、年間で約1,600人が学校の教育活動や業務運営の支援を行っている。
今後、学校と人材とのマッチングについて、より迅速に効率的な対応のできる機能を高めるため、最先端のAI技術の導入を進める。具体的には、そうした機能に関して人材の情報を詳しく分析し、学校のニーズに一層適切に対応するAIを活用する設計等に着手し開発を進める。また、人材バンクでマッチングを実現した事例について、TEPROがそれぞれに問合せをし、その内容をデータとして蓄積し、将来のAI活用に役立てる。