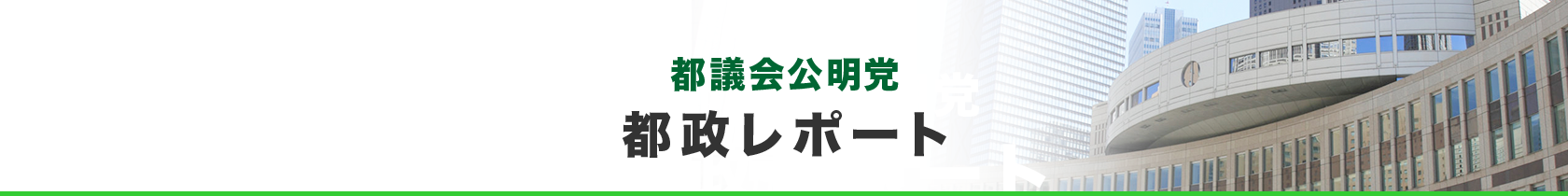安全・安心な東京の構築
① 災害時の医療提供体制について
【質問】
災害時に被災者の命を守るためには、救援、救助活動とともに、医療は極めて重要である。大規模災害時における医療支援の重要性について、知事の見解を伺う。
【知事】
令和7年は、阪神・淡路大震災から30年。いつ起きるか分からない大規模災害から都民の命を守るためには、災害対応で得られた経験を教訓として生かしていかなければならない。
都はこれまで、災害拠点病院の指定や病院の耐震化への支援、東京DMATの創設、東京都ドクターヘリの整備など、ハード・ソフト両面から体制を整備してきた。
一方で、能登半島地震などで、被災自治体の受援体制の構築や災害関連死の防止などの新たな課題が浮き彫りになっており、関係機関とも協議しながら対策を急ぐ必要がある。
このため、現在、外部有識者等の意見も聴きながら、関係機関が連携した、より実効性の高い災害医療体制の検討を進めており、こうした取り組みを加速させ、都民の命と健康を守る「首都防衛」を実現していく。
② ドクターヘリの広域連携について
【質問】
災害時の空からの医療支援について、都議会公明党は、東京型ドクターヘリに加えて、全国的に展開されているドクターヘリの導入を訴えてきた。2019年の第4回定例会代表質問において、知事は、東京型ドクターヘリと連携したドクターヘリの導入に向けて検討を進めていくと答えられ、その後、ドクターヘリが東京に導入された。
都議会公明党は、近隣県との相互活用に向けて協定を結ぶよう訴えてきたが、先月、山梨県とドクターヘリの広域連携に係る基本協定を締結した。これにより、どのような連携が可能となるのか、また、今後は近接する他県とも相互運航できるようになるのか、併せて伺う。
【保健医療局長】
都は令和7年2月、山梨県とドクターヘリの広域連携に係る基本協定を締結した。
これにより、令和7年3月末から、災害により多数の傷病者が発生した場合に、都県全域を対象とした相互運航が可能となる。また、平時においても、複数の出動要請を受けた場合などは、陸路搬送ではより時間を要する山間地域を中心に運航を開始し、対象地域を順次拡大していく。
今後、山梨県以外の近隣県についても、ドクターヘリの相互運航が可能となるよう、連携体制の構築に取り組んでいく。
③ 災害用モバイルファーマシーの他県との相互活用について
※モバイルファーマシー…調剤設備を持たせた災害対策医薬品供給車両のこと
【質問】
災害時の陸上からの医療支援策の一つとして、都議会公明党はモバイルファーマシーの導入を提案し、令和7年度予算案にモバイルファーマシー導入のための経費を盛り込んだことを高く評価する。
能登半島地震でも、他県から10台を超えるモバイルファーマシーが現地に駆けつけ、医療支援に活躍した。
都のモバイルファーマシーについても、災害時に他県との相互活用ができるよう体制を整えるべきと考える。都の見解を伺う。
【保健医療局長】
現在、全国にあるモバイルファーマシーは、主に各地の薬剤師会が所有しており、能登半島地震では、日本薬剤師会が中心となって関係機関と調整を行い、被災地に13台派遣された。
都は、都内で災害が発生した場合には、区市町村の被災状況に応じて、都のモバイルファーマシーを迅速に派遣するほか、大規模災害の場合には、能登半島地震と同様の対応になることも想定されるため、今後、都薬剤師会をはじめ関係機関と緊密に連携を図りながら、適切に運用していく。
④ 災害用モバイルファーマシーの平時活用について
【質問】
モバイルファーマシーは、災害時だけでなく、平時にも都民のために積極的に活用すべきと考える。都の見解を伺う。
【保健医療局長】
モバイルファーマシーを既に導入している地域では、車両に搭載された調剤設備を用いた災害対応訓練や、薬剤師を対象とした研修、住民向けの普及啓発イベントでの車両の展示などを行っており、平時においても様々な方法で活用されている。
今後、都は、都民への周知も図りながら、災害時にモバイルファーマシーを円滑に運用するための訓練などを実施するとともに、薬剤師会等の関係機関や既に導入している地域の関係者と意見交換を行い、平時における効果的な活用方法を具体的に検討していく。
⑤ 妙正寺川における洪水対策について
【質問】
一貫して取り組んできた妙正寺川の水害対策について、西武新宿線鷺ノ宮駅より上流のエリアにおける現在の整備状況と、今後の取り組みについて伺う。
【建設局長】
妙正寺川については、年超過確率20分の1規模の降雨に対応する護岸や調節池の整備を進めている。
令和5年度末までに、4.6キロメートルの護岸と、貯留量約35,000立米の鷺宮調節池など5か所の調節池の整備が完了している。
令和6年度は、中杉通りの八幡橋下流の護岸約100メートルと、妙正寺川の洪水も貯留する環七地下広域調節池の整備を進めている。加えて、約68,000立米の洪水を貯留する仮称妙正寺川上流調節池を中野区立鷺宮運動広場等の地下に整備することとした。令和7年度から事業化し、関係機関との協議を進めながら、基本設計を実施していく。
こうした取り組みを着実に進め、妙正寺川の安全性を高める。
⑥ 視覚障がい者への情報保障について
【質問】
都議会公明党は、都内の視覚障がい者団体の方々とともに、耳で聴くことのできるハザードマップについて、視覚障がい者が都内どこでも利用できるようにすべきと都に要請してきたが、その取り組みについて伺う。
※ハザードマップ…自然災害が発生した際に想定される危険な場所や避難経路、避難場所の情報を地図上にまとめたもの
【総務局長】
都は、令和7年度から民間事業者が提供する視覚障害者向け音声版ハザードマップサービスを都内全域で試験的に導入する。
視覚障害のある方が、このアプリをスマートフォン等にインストールすることにより、音声読み上げ機能を活用し、気象情報、水害リスク、避難場所、経路案内といった避難行動に必要な情報を聞くことができる。
今後、区市町村と連携して導入効果を検証した上で、視覚障害のある方への効果的な災害情報の提供につなげていく。
⑦ 全都立学校にマンホールトイレの整備を
【質問】
マンホールトイレについては、区市町村では、避難所となる小中学校への整備を進めているが、区市町村との協定により、避難場所として指定されている都立高校など219校の都立学校についても整備を進めていくべきである。
都立学校におけるマンホールトイレの整備状況と、整備の促進に向けた今後の取り組みについて、教育長の見解を伺う。
【教育長】
災害時に避難所となる都立学校の受入態勢を充実する上で、校内の敷地にマンホールトイレを整備する取り組みを促進することは重要である。
これまで都教育委員会は、新築や改築等の計画のある都立学校の工事に併せ、マンホールトイレの整備を進めてきた。この取り組みに当たっては、避難場所となる体育館やトイレに水を供給するプールの位置を踏まえ、排水管等を設ける工夫を行い、現在までに35校で導入している。今後、当面の新築や改築等の予定のない都立学校についても、マンホールトイレの整備を進める。このため、令和7年度、そうした対応に適した箇所等を調査する取り組みに着手する。
⑧ 特別区消防団員の防火服の更新について
【質問】
消防団の方々に力を発揮いただくためには、装備をはじめ、活動の安全確保をさらに進めていくことが必要である。国際基準に準拠した防火服への更新を計画的かつ速やかに行うべきと考えるが、消防総監の見解を伺う。
【消防総監】
安全な消防団活動を行うためには、防火服の性能を更に向上させることも重要である。
このことから、防火服の動きやすさや暑さ対策に係る検証を行うとともに、デザインについても魅力あるものとするため、全団員に対しアンケート調査を実施した。
これらを踏まえ、新しい防火服はデザインを刷新するとともに、ISO規格に準拠し、耐熱性に優れた生地の採用や露出部分の無いズボン型へと形状を変更することで安全性を高めた。新しい防火服は、令和7年度より、消火活動に従事する消火班から優先的に配置し、5年計画で全団員に整備する。
交通対策
① 西武新宿線連続立体交差事業により廃止となる踏切の代替施設について
【質問】
西武新宿線中井駅から野方駅間の連続立体交差事業によって廃止となる沼袋第4号踏切の代替施設について、現在の検討状況を伺う。
【建設局長】
西武新宿線中井駅から野方駅間の連続立体交差事業は、中野通りなど7か所の踏切を除却することで交通渋滞や地域分断を解消するとともに、地域の活性化にも資する極めて効果の高い事業である。
沼袋第4号踏切については、掘割区間に位置することから廃止することとし、代替施設として、歩行者と自転車が利用できる横断歩道橋の設置を検討してきた。
横断歩道橋については、中野区の意向を踏まえ、斜路付き階段とすることとし、現在、構造や設置箇所について、区や鉄道事業者と協議を行っている。
引き続き、区や鉄道事業者と連携し、検討を深度化していく。
② 西武新宿線野方駅から井荻駅付近の連続立体交差事業について
【質問】
西武新宿線野方駅から井荻駅付近における鉄道立体化に伴う、野方第1号踏切の除却に向けた都と区の取り組み状況を伺う。
【建設局長】
西武新宿線の野方第1号踏切について、都は、この踏切を除却するには、既設の道路立体箇所の再整備が必要となることから、残存することで検討している。
一方、中野区においては、まちづくりを考える上で重要な課題として、本踏切の除却が必要と考えている。
そのため、都は、鉄道事業者に区が行う調査への協力を依頼し、令和6年10月、区と鉄道事業者が協定を締結して具体的な検討を開始した。また、事業範囲や費用負担に関する課題等について、区と意見交換を行っている。
引き続き、地元区や鉄道事業者と連携しながら、鉄道立体化に向けて着実に取り組んでいく。
③ 東村山駅付近における連続立体交差事業について
【質問】
西武新宿線東村山駅付近における、連続立体交差事業の今後の取り組みについて伺う。
【建設局長】
西武新宿線東村山駅付近の連続立体交差事業は、府中街道など5か所の踏切を除却する事業である。
現在は、高架橋において線路の敷設を行うとともに、高架駅の昇降施設などの工事を実施している。令和7年6月には、新宿線下り線を地上から高架橋へ切り換える。これにより、府中街道などの4か所の踏切において遮断時間が短くなる。
また、切換前には、地元の皆様などを対象に、施設見学の機会を設ける予定である。
引き続き、地元市や鉄道事業者と連携し、本事業を積極的に推進していく。
④ 中野駅のホームドアの整備について
【質問】
中野駅は、1日20万人以上の利用者があり、8つもホームがあるターミナル駅である。地元のホームドア早期整備の要望も多い。
現在、中野駅は駅ビルが建設中で、ホームが狭く危険である。中野駅のホームドアの早期整備に向けた取り組みについて、都の見解を伺う。
【東京都技監】
中野駅には、東京メトロとJR東日本が乗り入れている。
東京メトロが管理するホームについては、令和7年度末までにホームドア整備が完了する予定である。JR東日本が管理するホームについては、令和7年3月に公表した計画において、2028年度までに整備する予定としている。
新たに創設する事業者へ直接補助を行う制度の活用や、国と連携した技術的支援により、ホームドア整備の更なる加速を実現していく。
環境施策
① 一般廃棄物処理業務委託における契約手法の適正化について
【質問】
市区町村が中小の廃棄物処理事業者に委託する一般廃棄物収集運搬処理事業の委託料、契約方法が適切に行われていないため、令和6年9月、環境省から適正化を求める局長通知が発出され、これを受けて知事から、都内区市町村長宛ての通知が令和6年10月に発出されている。
最高裁判決でも、一般廃棄物処理業は自由競争に委ねられるべき性格のものではないと明確に示されているが、いまだに価格競争のみに委ねる契約を行っている市が8市も存在していた。環境省通知の趣旨に反し、事業者からヒアリングを行わないで委託料設定をしている区市もある。
これらを踏まえ、都議会公明党は、都が前面に立って、都内自治体における契約実態の把握や契約手法の適正化に取り組むよう強く求めてきたが、現在の状況について伺う。
【環境局長】
都民生活を支える中小の一般廃棄物収集事業者の安定した事業運営に向け、これまで都は、業界の特性を踏まえた契約実態の把握や契約手続きの確保に努めてきた。
具体的には、市区町村を対象に調査を実施し、一部自治体で、事業者からの意見聴取や原価計算が不十分であることや、コスト高騰時における対応の遅れ等が生じている事例を確認した。
また、業界団体へのヒアリングを通じ、価格交渉の困難性や数年間に及ぶ価格の据え置きなど、事業者の実情を把握した。
さらに、自治体に対し、最高裁判決を踏まえた対応を行うよう繰り返し求めてきた結果、改善が必要な8自治体全てが、契約改定時に価格競争のみに依らない方法で行う方針を示すなど進展が図られた。
② 一般廃棄物処理業務の実情を踏まえた支援について
【質問】
自治体から業務を受託する中小事業者は、契約時において大変弱い立場にあり、十分な価格交渉ができないまま、契約に応じざるを得ない状況にある。業界団体は、令和6年12月に行われた都への要望の中で、技術的支援や財政支援などを求めており、都は区市町村任せにするのではなく、広域自治体として積極的な役割を果たすべきである。
一般廃棄物処理事業者を取り巻く環境は、大変厳しい状況にある。このため、市区町村の契約の実態や事業者の実情を踏まえ、契約の適正化等に向けた具体的な取り組みを行うべきと考えるが、見解を求める。
【環境局長】
物価上昇や人手不足、猛暑日の増加など急激な環境変化に対しては、市区町村による適切な対応が必要であるが、その緊急性を踏まえ、都は集中的な支援を実施する。
まず、都は、業務の確実な履行の基盤となる契約の適正化に向けたマニュアルを作成し、業務改善を求めるほか、専門相談窓口を設置し、自治体や事業者からの相談にきめ細かく対応する。加えて、働き方改革等に向け、適正かつ合理的な取り組みを行う自治体に対し、経費の2分の1、3,000万円を上限とする新たな支援を実施する。これらにより、市区町村の契約の適正化や労働環境の改善に向けた積極的な対応を促していく。
生物多様性 野生動物のための森づくり
① 多摩地域の森林再生について
【質問】
山間部に生息する野生動物の生息環境を維持・向上させるには、動物の食物が豊富にある広葉樹の確保・再生を図る必要があるほか、熊などの野生動物との偶発的な接触による人身被害を防ぐための森づくりも必要である。こうした課題に対する都の取り組みを伺う。
【環境局長】
都は、林業経営が困難な荒廃したスギやヒノキの人工林を間伐し、針葉樹と広葉樹の混ざり合った針広混交林化を目指す森林再生事業に取り組んでいる。
9,000ヘクタールの私有林を対象に、これまでに約9割の8,100ヘクタールで間伐を実施しており、その結果、実のなる広葉樹が育つなど、森林が再生されつつある。
令和7年度は、事業対象を市町村が所有する森林に広げ、都が間伐費用の半分を負担して整備を促進することで、野生動物の生息環境の更なる改善につなげていく。
また、新たに民家等と接する林縁部の皆伐を行い、緩衝帯を創出することで、熊等との予期せぬ遭遇を防いでいく。
② 人と熊との共存に向けた対策について
【質問】
都は、奥多摩町など6市町村と連携して、森と人里との間の雑木林を切ってバッファーゾーン、緩衝地帯を設けること等、熊が人里に近づかないようにする対策を進めている。
また、熊の被害を防ぐには、食べ物の匂いなど引き寄せてしまう誘引物の除去等、住民自身が取れる対策もあることなど、正しい知識や情報を発信していくことも必要である。
専門家やノウハウを有する民間団体等と意見交換などを行いながら、人と熊との共存に向けた対策を進めていくことが重要と考えるが、都の見解を求める。
【環境局長】
地域に熊を引き寄せない環境づくりに向けて、都はチラシやポスターを作成し、関係市町村の施設や鉄道駅ビジターセンターなどで、都民等が取れる対策の周知を図っている。
具体的には、果樹等の誘引物を撤去すること、自宅やごみ集積場の戸締りを徹底することなど、一人ひとりの心がけが人身被害の防止につながることを呼びかけている。
熊対策については、自然環境保全審議会の専門家や市町村などの関係者と議論を重ね、随時、取り組みに反映させている。現在進めている鳥獣の保護管理に関する計画改定のプロセスにおいても、ノウハウを有する様々な関係者と意見交換を行い、対策の充実につなげていく。
③ 熊スプレーの活用について
【質問】
熊にばったり遭遇してしまった際、追い払う有効なツールとして熊スプレーがある。この活用をさらに推進すべきだと考えるが、都の見解を求める。
【環境局長】
熊スプレーについては、都が市町村とともに進めている防除対策事業において、市町村がスプレーや熊鈴などの対策備品を購入できるメニューを用意し、地域のニーズに応じて活用されている。
令和7年度はこれに加え、予期せぬ地域での出没等に対応するため、都として一定数を購入し、備蓄をしていく。
また、登山者向けのチラシや、令和7年度から新たに実施する地域住民等を対象とした熊対策の出前講座等で、スプレーの有効性や使用方法を解説するなど、普及啓発に取り組んでいく。
都行造林
① 都行造林について
【質問】
多摩地域の森林には「都行造林」というものがあるが、どのような仕組みか伺う。
【産業労働局長】
都行造林とは、条例に基づき、水源の涵養や地域の林業振興などを目的に、都が土地所有者に代わって行う森林整備の制度である。
具体的には、土地所有者と都が契約を結び、将来、樹木を伐採した際に得られる収益を分け合う条件で一定期間、都がスギ・ヒノキの植林や保育作業を行うものである。
現在、多摩地域に約800ヘクタール、島しょ地域に約100ヘクタールの造林地があり、各造林地の生育状況に応じた森林整備を進めている。
② 山奥にある都行造林地への対応について
【質問】
山の奥にあるため、また、植林した木々は土地所有者と都の共有財産であるために手をつけにくいといった課題がある、伐採・搬出の難しい都行造林にどのように対応していくのか、都の見解を伺う。
【産業労働局長】
都は、搬出が難しい山奥での伐採を進めるため、間伐材をヘリコプターで搬出する試みを始めており、安全性や効果的な搬出について検証のうえ、普及を図ることで多摩産材の供給量の拡大につなげていく。
都行造林については、こうした取り組みを含め、土地所有者の意向を聞きながら、契約の更新時期に合わせて、適切に対応していく。
福祉・医療施策
① 多摩北部医療センター整備基本計画について
【質問】
都立病院機構は令和7年2月、多摩北部医療センター整備基本計画案を公表した。
都議会公明党は、センター整備について、北多摩北部医療圏に出産できる病院が少ないことから、分娩を取り扱う産科を整備することや、感染症への備えの強化などを求めてきた。新病院の整備にあたっては、地域に必要な医療機能を強化していくべきであるが、見解を伺う。
【保健医療局長】
新病院では、地域の医療ニーズに対応するため、新たに分娩を取り扱う産婦人科病棟を整備する。
病棟には、母体の負担軽減やプライバシー確保のため、陣痛から産後の回復までを同じ部屋で過ごせる個室を設けるとともに、帝王切開や内科合併症のあるミドルリスク妊産婦等への対応に必要な処置室等を設置する。
また、災害や感染症等への対応に必要な医療機能を強化するため、屋上へリポートや、救急外来に感染症の疑いのある患者専用の入口や診察室を整備する。
こうした機能強化により、平時・有事ともに、安全・安心で質の高い医療を提供できる病院を整備し、より一層、地域医療に貢献していく。
② ケアリーバー支援について
※ケアリーバー…児童養護施設や里親などの社会的養護のケアから離れた子どもや若者のこと
【質問】
自立に向けて社会に出る際に困難を抱えるケアリーバーは少なくない。都は、ケアリーバー当事者や施設運営者など現場の声を聴き、実態に即した支援策をこれまで以上に講じていくべき。また、都議会公明党がこれまで求めてきた、施設退所後も施設の近くで生活できる場の整備も進めるべきである。併せて見解を求める。
【福祉局長】
都は、都内の家賃の水準や当事者の状況等も踏まえ、令和7年度から、居住費支援の単価を月額53,700円から72,000円に増額するほか、児童養護施設等がケアリーバーとの交流を継続するために必要な経費を新たに支援する。
令和6年4月、改正児童福祉法が施行され、施設等において、退所者に共同生活の場などを提供し、日常生活の援助や就業支援等を行うことが国制度の対象となったことから、今後、こうした取り組みの実施を施設等に対して働きかけていく。
動物施策 獣医系大学との協働事業
【質問】
これまで提案してきた獣医系大学との協働事業が、令和7年度予算案に盛り込まれたが、その内容を伺う。
【保健医療局長】
動物愛護管理施策の推進に当たり、専門的な知見を持つ獣医系大学との協働は重要であり、都は、大学教員から助言を得ながら、動物愛護相談センターに保護された動物の飼養管理を行っている。
こうした取り組みを更に進めるため、都は令和7年度、都内の大学と協働事業に関する協定を締結し、大学教員がセンターの職員に対して、動物の治療やトレーニングに関する専門的な研修を実施するほか、センターの職員が大学教員にオンラインで相談できる体制を整えていく。
また、大学祭を活用して、動物愛護に関する普及啓発を実施するなど、大学との協働を進めていく。